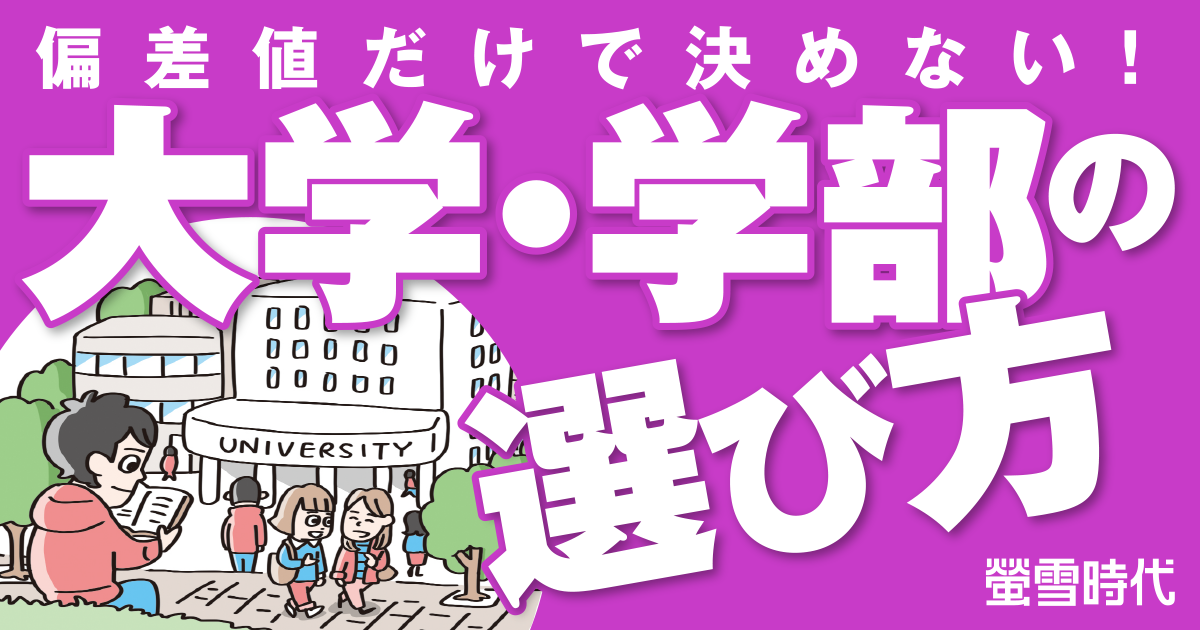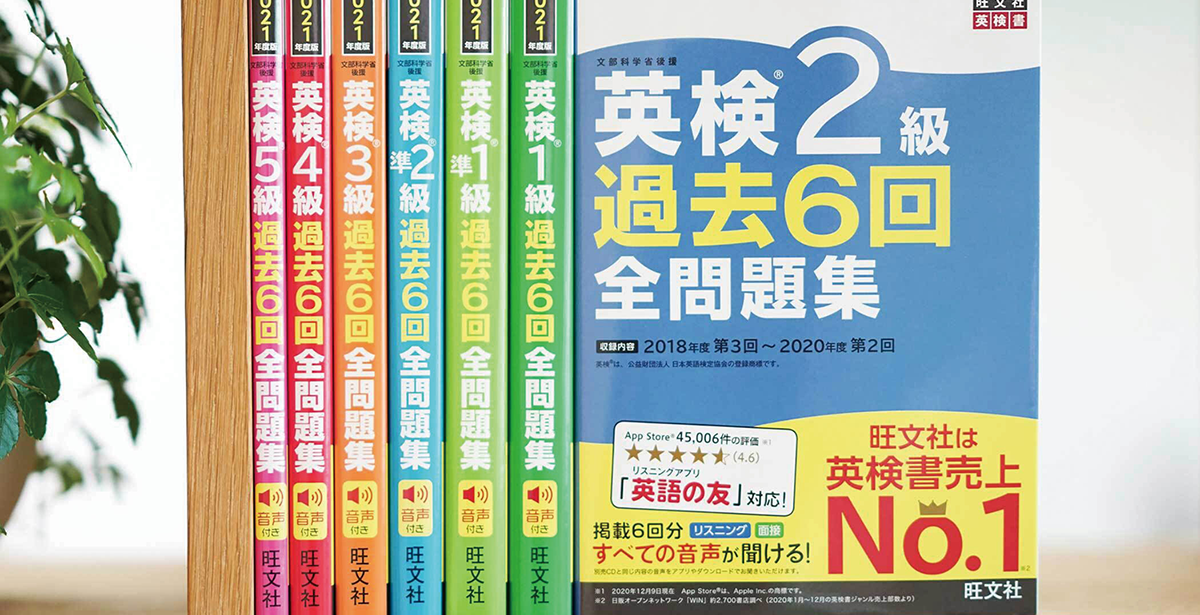保護者も必見!!受験生の脳に効く最強の“低GI”食事術
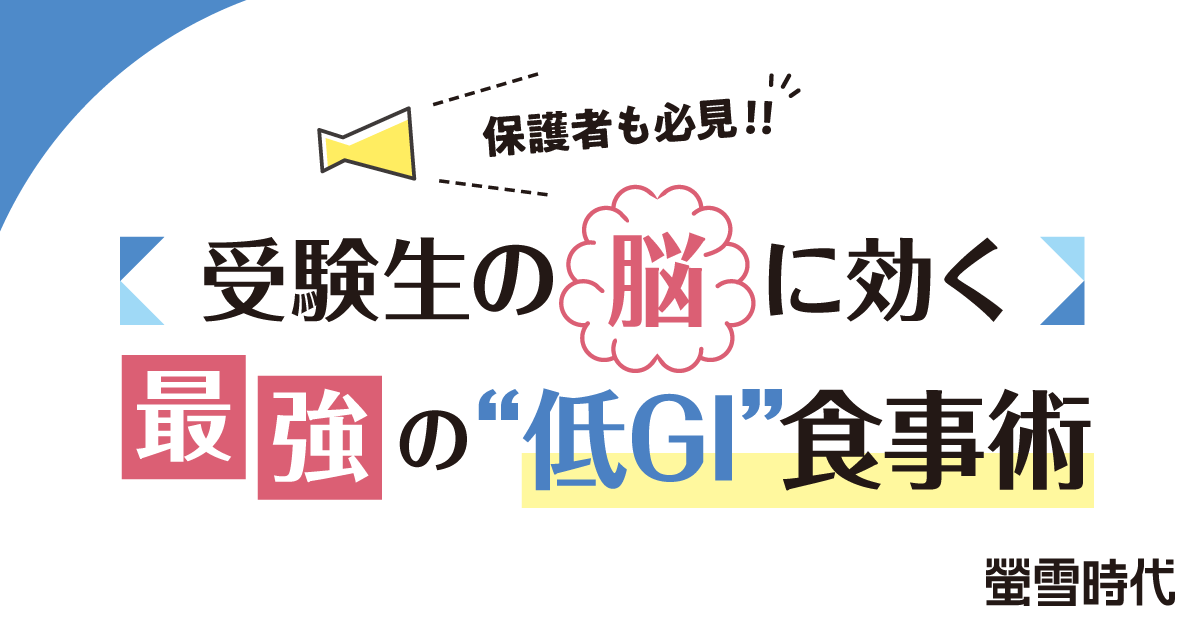
受験勉強の効率を高めるため、食事面からアプローチしてみてはどうだろう。この記事では、脳科学者の西剛志先生に、集中力や記憶力の向上が期待できる“低GI”食事術について解説いただく。受験生に食事を用意している保護者の方にもぜひ参考にしてもらいたい。
イラスト◎高村あゆみ

にし・たけゆき◎東京工業大学非常勤講師や特許庁を経て、T&Rセルフイメージデザインを設立し、3万人以上のパフォーマンスアップを支援。メディア出演多数。著書に『脳科学者が教える集中力と記憶力を上げる 低GI食 脳にいい最強の食事術』などがある。
- 低GI食で血糖値の急激な上下を防ぎ集中力や記憶力をアップさせる!
受験勉強に効く 低GI食のポイント - 学習効果をアップする低GI食実践法
受験生も実践しやすい朝食・昼食・夕食もご紹介 - 忙しい受験生&保護者必見!低GI食テクニック
無理なく低GI食を取り入れる
低GI食で血糖値の急激な上下を防ぎ集中力や記憶力をアップさせる!
脳をしっかり働かせるには大量のエネルギーが必要
受験勉強には、脳のパフォーマンスを長時間維持することが求められます。脳は人体において2%ほどの質量しかありませんが、消費するエネルギーは体全体の20~25%にも及びます。大量のエネルギーを消費する脳をしっかり働かせるためには、食事がとても重要になります。受験生の皆さんは、大前提として朝食を抜くようなことは避けてください。
食事で摂取する栄養素のうち、最も脳のエネルギーになるのが糖質です。しかし、単純に糖質を含む食品をたくさん食べればいいかというと、そうではありません。
皆さんは、食べ過ぎて満腹になり、食後に頭がぼんやりするという経験をしたことがあるでしょうか。これは、脳が“血糖値スパイク”という状態になっているために起こります。この血糖値スパイクを起こさないような食事をすることで、学習効果のアップが期待できます。そのためにおすすめしたいのが、“低GI”食と呼ばれる食品を取り入れた食事術です。
血糖値スパイクによって脳がエネルギー不足になる
血糖値スパイクについて、もう少し詳しく説明します。食事で糖質をたくさん摂ると血糖値が急上昇し、インスリンというホルモンが大量に分泌されます。このインスリンの働きにより、急上昇した血糖値は急激に下がります。これが血糖値スパイクです(下のイメージ図参照)。

血糖値スパイクにより低血糖になると、脳のエネルギーも不足します。この結果として、眠気や倦怠感が起きたり、不安や苛立ち、空腹感などに襲われたりするのです。せっかく食事でエネルギーを摂ったのに、血糖値スパイクで脳がエネルギー不足になってしまったらもったいないですよね。これを解決する手段になるのが、低GI食を取り入れた食事術です。
GIとは、グリセミック・インデックスの略で、食品を食べた後の血糖値の上昇を示す指標です。この数値が高いほど食後の血糖値が急激に上がり、数値が低いほど血糖値の上昇はゆるやかになります。つまり、受験生の皆さんが集中力や記憶力を上げたいという場合、低GIの食品を取り入れると、血糖値スパイクを起こさずに脳にエネルギーを供給できます。
また、糖質の摂り過ぎがよくないのはこれまで説明してきた通りですが、糖質をまったく摂らないのもよくありません。脳は糖質不足で血糖値が下がり過ぎると、アドレナリンというホルモンを分泌し、無意識のうちに攻撃的になってしまいます。血糖値スパイクを起こさないように糖質を摂る低GI食によって、脳のパフォーマンスを向上させていきましょう。

この続きを読むには

に登録(無料)が必要です
まなびIDに登録すると、
パスナビの記事が読み放題!!
さらに旺文社のサービスで
- Point 1過去問が1年分無料で閲覧できる!
- Point 2自分だけの志望大学リストを作成可能!
- Point 3英検の自己採点が簡単にできる!
この他にも便利な機能が!
詳しくはこちら
受験お役立ち記事を探す
- 受験生必見!勉強・生活・メンタルを最適化する5つのTo do2025/3/17合格への近道はここに!
勉強法・生活環境の見直し・メンタルについてなど、志望校合格に必要な5つのTo doを紹介。今すぐ始められる実践的アドバイス満載!2025/3/17
- 志望校合格と青春の両立!その成功事例と効果的な学習戦略2025/3/17部活と勉強を両立させる方法を知りたい人必見!
厚木高校の生徒がどのように受験と部活を両立しているのか、具体的な成功事例と共に、時間管理のコツや効果的な勉強法を解説します。2025/3/17
- 学習計画が合否を分ける!受験までの学習計画の立て方のポイント2025/3/17受験勉強を成功させるには、計画的な学習が不可欠!螢雪手帳を活用して学習目標と計画を立てましょう。
また、時期ごとの学習計画の立て方、学習法のポイントについても詳しく紹介します。2025/3/17
- 受験生必見!勉強・生活・メンタルを最適化する5つのTo do2025/3/17合格への近道はここに!
勉強法・生活環境の見直し・メンタルについてなど、志望校合格に必要な5つのTo doを紹介。今すぐ始められる実践的アドバイス満載!2025/3/17
- 志望校合格と青春の両立!その成功事例と効果的な学習戦略2025/3/17部活と勉強を両立させる方法を知りたい人必見!
厚木高校の生徒がどのように受験と部活を両立しているのか、具体的な成功事例と共に、時間管理のコツや効果的な勉強法を解説します。2025/3/17
- 学習計画が合否を分ける!受験までの学習計画の立て方のポイント2025/3/17受験勉強を成功させるには、計画的な学習が不可欠!螢雪手帳を活用して学習目標と計画を立てましょう。
また、時期ごとの学習計画の立て方、学習法のポイントについても詳しく紹介します。2025/3/17
- 受験生必見!勉強・生活・メンタルを最適化する5つのTo do2025/3/17合格への近道はここに!
勉強法・生活環境の見直し・メンタルについてなど、志望校合格に必要な5つのTo doを紹介。今すぐ始められる実践的アドバイス満載!2025/3/17
- 志望校合格と青春の両立!その成功事例と効果的な学習戦略2025/3/17部活と勉強を両立させる方法を知りたい人必見!
厚木高校の生徒がどのように受験と部活を両立しているのか、具体的な成功事例と共に、時間管理のコツや効果的な勉強法を解説します。2025/3/17
- 学習計画が合否を分ける!受験までの学習計画の立て方のポイント2025/3/17受験勉強を成功させるには、計画的な学習が不可欠!螢雪手帳を活用して学習目標と計画を立てましょう。
また、時期ごとの学習計画の立て方、学習法のポイントについても詳しく紹介します。2025/3/17
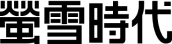 2024年12月号より転載
2024年12月号より転載