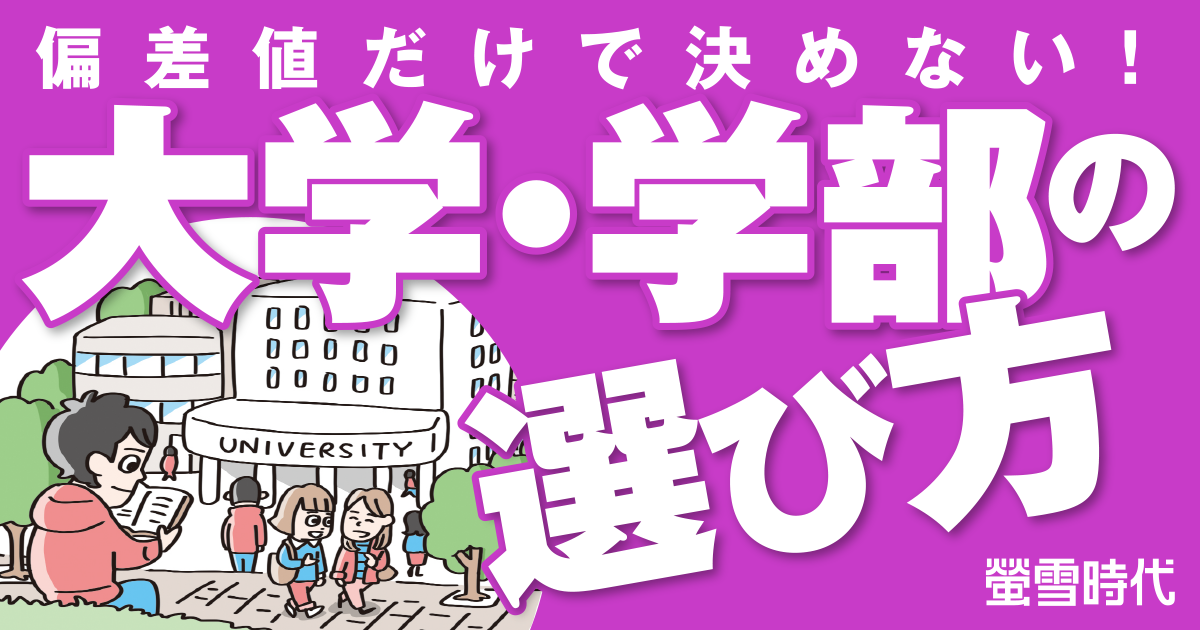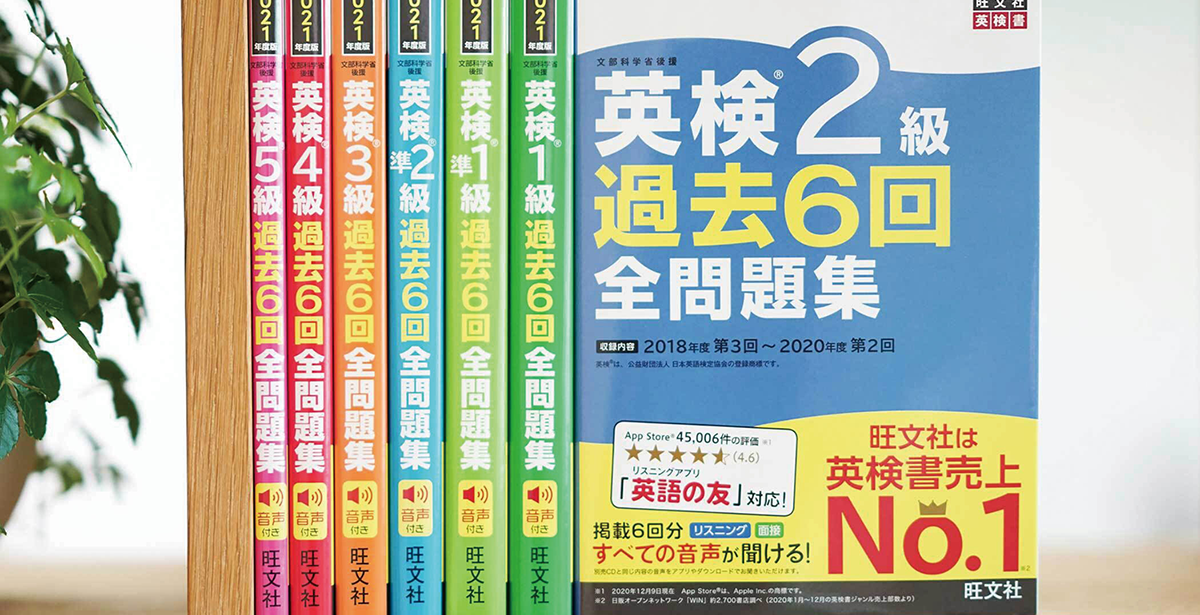- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
歴史
設置 2014
学科定員
国際資源120*
*留学生枠5名分を含む
学部内容
地球規模の課題である資源・エネルギーに関する文理融合型の教育により、資源を網羅的かつ多角的に学ぶ。国際的視野を持つ資源スペシャリストの育成を目指す。以下の3コースを設置。
◆資源政策コースでは、世界の資源情勢を正確に分析・考察する力や資源国との交渉力を身につけた資源戦略を担う人材を育成する。
◆資源地球科学コースでは、世界を対象にした資源分布の予測と新たな地球資源の可能性を探究する最先端地球科学分野の技術者・研究者を養成する。
◆資源開発環境コースでは、限りある地球資源を持続的かつ有効に活用するため、地球環境に配慮した資源開発と資源循環系社会の形成に寄与できる技術者・研究者を養成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男66%・女34%
◆資源政策コースでは、世界の資源情勢を正確に分析・考察する力や資源国との交渉力を身につけた資源戦略を担う人材を育成する。
◆資源地球科学コースでは、世界を対象にした資源分布の予測と新たな地球資源の可能性を探究する最先端地球科学分野の技術者・研究者を養成する。
◆資源開発環境コースでは、限りある地球資源を持続的かつ有効に活用するため、地球環境に配慮した資源開発と資源循環系社会の形成に寄与できる技術者・研究者を養成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男66%・女34%
歴史
設置 1949、改称 1998
学科定員
計190 学校教育課程110、地域文化80
学部内容
学校教育課程は、2025年5コースから以下の3コースに再編予定。
◆初等中等教育コースでは、実践的な学びを通し、高度な指導力、専門性を備えた教員を養成するため、2025年に以下の3プログラムを配置予定(プログラムは入学後に選択可能)。
教育実践プログラムでは、小学校教員の養成を主とし、中学校教員養成も含めて、子どもの心身成長発達についての理解を深め、全国トップクラスの学力を支える高度な実践力を持った教員を養成する。
英語教育プログラムでは、小中高の連携による英語教育を実践できるとともに、秋田の次世代のグローバル人材を育てるために、英語力だけでなく異文化間コミュニケーション能力を持った教員を養成する。
理数教育プログラムでは、理数系の体系的な知識と指導法を身につけ、小中高連携のもとで理科や数学のおもしろさを子どもに伝えることができ、実感を伴った理解へと実習を発展させることのできる教員を養成する。
◆特別支援教育コースでは、発達の特性や特別なニーズに対応した支援を実践できる、特別支援教育の担い手を養成する。
◆こども発達コースでは、幼稚園教諭・保育士の養成を主とし、小学校教員養成も含めて、人間の生涯にわたる発達過程や、幼児教育・保育と学校教育の全課程を見通しながら省察できる人材を育成する。
地域文化学科は、社会科学・人文科学の枠を超え、学際的な立場から地域社会とそこに暮らす人びとの生活・活動を客観的・相対的にとらえる試みとしての「地域学」の構築と、その立場からの実践的な教育による人材育成を基本理念とする。以下の3コースを設置(コースは1年次終了時に選択)。
◆地域社会コースでは、教室(理論)と現場(体験)を往還して社会の仕組みを実践的に学ぶ。地域の多様な生活資源、環境資源、文化資源などの再発見と評価・活用を行い、産業・働き方・生活のこれからの方向性を提案し、その実現に貢献できる人材を育成する。
◆国際文化コースでは、日本を含むアジア、欧米など、世界の多様な文化を学び、グローバルな視点から地域を考える。伝統文化の継承・伝承、地域文化の現状把握、将来に向けてのあるべき姿の構想など、地域の現状に即した問題解決力を持つ人材を育成する。
◆心理実践コースでは、人間の心の動きに関心を寄せ、心理学の幅広い領域について基礎から実践まで体系的に学び、応用できる力を育てる。認定心理士資格を取得でき、公認心理師取得のための科目にも対応。大学院では臨床心理士資格取得を目指すために必要な知識や技術を習得できる。
△新入生の男女比率(2024年) 男43%・女57%
◆初等中等教育コースでは、実践的な学びを通し、高度な指導力、専門性を備えた教員を養成するため、2025年に以下の3プログラムを配置予定(プログラムは入学後に選択可能)。
教育実践プログラムでは、小学校教員の養成を主とし、中学校教員養成も含めて、子どもの心身成長発達についての理解を深め、全国トップクラスの学力を支える高度な実践力を持った教員を養成する。
英語教育プログラムでは、小中高の連携による英語教育を実践できるとともに、秋田の次世代のグローバル人材を育てるために、英語力だけでなく異文化間コミュニケーション能力を持った教員を養成する。
理数教育プログラムでは、理数系の体系的な知識と指導法を身につけ、小中高連携のもとで理科や数学のおもしろさを子どもに伝えることができ、実感を伴った理解へと実習を発展させることのできる教員を養成する。
◆特別支援教育コースでは、発達の特性や特別なニーズに対応した支援を実践できる、特別支援教育の担い手を養成する。
◆こども発達コースでは、幼稚園教諭・保育士の養成を主とし、小学校教員養成も含めて、人間の生涯にわたる発達過程や、幼児教育・保育と学校教育の全課程を見通しながら省察できる人材を育成する。
地域文化学科は、社会科学・人文科学の枠を超え、学際的な立場から地域社会とそこに暮らす人びとの生活・活動を客観的・相対的にとらえる試みとしての「地域学」の構築と、その立場からの実践的な教育による人材育成を基本理念とする。以下の3コースを設置(コースは1年次終了時に選択)。
◆地域社会コースでは、教室(理論)と現場(体験)を往還して社会の仕組みを実践的に学ぶ。地域の多様な生活資源、環境資源、文化資源などの再発見と評価・活用を行い、産業・働き方・生活のこれからの方向性を提案し、その実現に貢献できる人材を育成する。
◆国際文化コースでは、日本を含むアジア、欧米など、世界の多様な文化を学び、グローバルな視点から地域を考える。伝統文化の継承・伝承、地域文化の現状把握、将来に向けてのあるべき姿の構想など、地域の現状に即した問題解決力を持つ人材を育成する。
◆心理実践コースでは、人間の心の動きに関心を寄せ、心理学の幅広い領域について基礎から実践まで体系的に学び、応用できる力を育てる。認定心理士資格を取得でき、公認心理師取得のための科目にも対応。大学院では臨床心理士資格取得を目指すために必要な知識や技術を習得できる。
△新入生の男女比率(2024年) 男43%・女57%
歴史
設置 1970
学科定員
計230 医学124、保健106
学部内容
医学科では、豊かな教養に支えられた人間性、学問の進歩に対応しうる柔軟な適応能力と課題探究・問題解決能力を養い、医学・健康科学に対する十分な理解をもとに人びとの健康と福祉に貢献できる国際的視野を備えた人材を育成する。
この目的のため、モデル・コア・カリキュラムに準拠した統合型カリキュラムを適用している。医学教育のグローバル化に対応したカリキュラムを導入しており、診療に参加しながら医学・医療を学ぶ機会が多くなっている。
1年次では、教養基礎教育科目に加え、専門教育科目として基礎医学を学習する。
2年次では、基礎医学を中心とした講義・実習が行われ、人体の構造と機能、個体の反応、原因と病態について学習する。
3年次では、臨床医学および社会医学に加え、学内の研究室に配属され、基礎研究を学ぶ。
4年次では、臨床講義に加えて、臨床実習に備えた基本的な診療知識・技能などを学習し、統一試験および共用試験(OSCEとCBT)が行われ、合格者にはスチューデントドクターの認定証が与えられる。
4年次秋から6年次7月までの74週間は、診療参加型臨床実習を行う。6年間の医学教育を修了し、医師国家試験に合格すると、2年間の卒後臨床研修を受け、その後、希望する専門科における研修を継続することになる。
保健学科は、看護学、理学療法学、作業療法学の3専攻からなり、看護師、保健師(選択)、助産師(選択)、理学療法士、作業療法士を養成する。
◆看護学専攻では、さまざまの健康レベルにある人びとに質の高い看護を提供し、健康維持・増進、病気予防の保健活動に関わる人材を育成する。
◆理学療法学専攻では、身体に疾病や障害のある人に対して、運動療法、日常生活活動の指導、温熱・寒冷・電気などの物理療法を施して、基本的動作能力の回復を図るために治療・援助できる人材を育成する。
◆作業療法学専攻では、作業活動を介して身体や精神の諸機能の回復や維持・開発を行うための治療・訓練・指導・援助ができる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男44%・女56%
△2024年医師国家試験合格率(新卒) 98.4%
この目的のため、モデル・コア・カリキュラムに準拠した統合型カリキュラムを適用している。医学教育のグローバル化に対応したカリキュラムを導入しており、診療に参加しながら医学・医療を学ぶ機会が多くなっている。
1年次では、教養基礎教育科目に加え、専門教育科目として基礎医学を学習する。
2年次では、基礎医学を中心とした講義・実習が行われ、人体の構造と機能、個体の反応、原因と病態について学習する。
3年次では、臨床医学および社会医学に加え、学内の研究室に配属され、基礎研究を学ぶ。
4年次では、臨床講義に加えて、臨床実習に備えた基本的な診療知識・技能などを学習し、統一試験および共用試験(OSCEとCBT)が行われ、合格者にはスチューデントドクターの認定証が与えられる。
4年次秋から6年次7月までの74週間は、診療参加型臨床実習を行う。6年間の医学教育を修了し、医師国家試験に合格すると、2年間の卒後臨床研修を受け、その後、希望する専門科における研修を継続することになる。
保健学科は、看護学、理学療法学、作業療法学の3専攻からなり、看護師、保健師(選択)、助産師(選択)、理学療法士、作業療法士を養成する。
◆看護学専攻では、さまざまの健康レベルにある人びとに質の高い看護を提供し、健康維持・増進、病気予防の保健活動に関わる人材を育成する。
◆理学療法学専攻では、身体に疾病や障害のある人に対して、運動療法、日常生活活動の指導、温熱・寒冷・電気などの物理療法を施して、基本的動作能力の回復を図るために治療・援助できる人材を育成する。
◆作業療法学専攻では、作業活動を介して身体や精神の諸機能の回復や維持・開発を行うための治療・訓練・指導・援助ができる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男44%・女56%
△2024年医師国家試験合格率(新卒) 98.4%
歴史
設置 1949、改組 2025予定
学科定員
計315* 応用化学生物100、環境数物科学90、社会システム工125
*留学生枠27名分を含む
学部内容
2025年理工学部を改組し新設予定の学部。以下の3学科を設置。
応用化学生物学科は、以下の3コースを設置している。
◆生物学コースでは、生物学の専門分野に重みを置き、化学と生物学を総合した考え方と高度なバイオテクノロジーを修得するため、生化学、分子生物学、細胞生物学、生物化学工業などの生物学系専門分野を重点的に学ぶ。
◆有機・高分子化学コースでは、有機化学、高分子化学、有機材料科学などの専門分野を重点的に学び、医薬品や農薬および化学素材の製造や化学的検査・分析における諸課題を解決できる人材を養成する。
◆応用化学コースでは、無機材料科学、電気化学、反応工学、エネルギー変換材料科学などの化学の専門分野を重点的に学び、クリーンエネルギーの創出、環境浄化、脱炭素化社会の実現における諸課題に取り組む人材を養成。
環境数物科学科は、以下の2コースを設置している。
◆数理科学・地球環境学コースでは、数学の代表的な分野(代数学、幾何学、解析学、離散数学等)、理論物理学、地球科学の各分野において、基礎から発展的な内容まで教育し、地球の環境と持続可能社会の実現に貢献する人材を養成する。
◆機能デバイス物理コースでは、材料の機能や用途、デバイスの動作原理や特性、材料機能と電子デバイス特性の相関を学び、数理科学・地球環境学コースとの分野融合で効率化を目指す。
社会システム工学科は、以下の3コースを設置している。
◆モビリティコースでは、機械工学の基礎を成す四力学(材料力学、熱力学、流体力学、機械力学)、モビリティを構成する素材の材料科学・工学までを網羅した教育研究を行う。ほかの2コースと連携した教育研究も実施。
◆電気システムコースでは、輸送機の電動化、再生可能エネルギーの社会導入などを目指し、知的な電気機器や制御システムの設計・開発、電気エネルギーの発生・変換・貯蔵・利用、人間と環境の関わるエンジニアリングデザインに関する教育研究を行う。
◆社会基盤コースでは、持続可能で強靭な地域社会を支える社会基盤の構築とその維持管理を目的として、環境負荷低減機能を重視した新たな地域社会基盤を創出する知識と技術を身につけるための研究と教育を行う。
△新入生の男女比率(2024年) 男84%・女16%
応用化学生物学科は、以下の3コースを設置している。
◆生物学コースでは、生物学の専門分野に重みを置き、化学と生物学を総合した考え方と高度なバイオテクノロジーを修得するため、生化学、分子生物学、細胞生物学、生物化学工業などの生物学系専門分野を重点的に学ぶ。
◆有機・高分子化学コースでは、有機化学、高分子化学、有機材料科学などの専門分野を重点的に学び、医薬品や農薬および化学素材の製造や化学的検査・分析における諸課題を解決できる人材を養成する。
◆応用化学コースでは、無機材料科学、電気化学、反応工学、エネルギー変換材料科学などの化学の専門分野を重点的に学び、クリーンエネルギーの創出、環境浄化、脱炭素化社会の実現における諸課題に取り組む人材を養成。
環境数物科学科は、以下の2コースを設置している。
◆数理科学・地球環境学コースでは、数学の代表的な分野(代数学、幾何学、解析学、離散数学等)、理論物理学、地球科学の各分野において、基礎から発展的な内容まで教育し、地球の環境と持続可能社会の実現に貢献する人材を養成する。
◆機能デバイス物理コースでは、材料の機能や用途、デバイスの動作原理や特性、材料機能と電子デバイス特性の相関を学び、数理科学・地球環境学コースとの分野融合で効率化を目指す。
社会システム工学科は、以下の3コースを設置している。
◆モビリティコースでは、機械工学の基礎を成す四力学(材料力学、熱力学、流体力学、機械力学)、モビリティを構成する素材の材料科学・工学までを網羅した教育研究を行う。ほかの2コースと連携した教育研究も実施。
◆電気システムコースでは、輸送機の電動化、再生可能エネルギーの社会導入などを目指し、知的な電気機器や制御システムの設計・開発、電気エネルギーの発生・変換・貯蔵・利用、人間と環境の関わるエンジニアリングデザインに関する教育研究を行う。
◆社会基盤コースでは、持続可能で強靭な地域社会を支える社会基盤の構築とその維持管理を目的として、環境負荷低減機能を重視した新たな地域社会基盤を創出する知識と技術を身につけるための研究と教育を行う。
△新入生の男女比率(2024年) 男84%・女16%
歴史
設置 2025予定
学科定員
情報データ科学100
学部内容
2025年新設予定の学部。情報学とデータサイエンスを体系的に学び、身につけた情報技術の知識とデータ解析スキルを活用して諸課題の解決を図り、新たな価値を創造し実装することができる「デジタル人材」を養成する。
情報学・データサイエンスを「専門」として身につけられる教育課程を編成。1~2年次では、「情報Ⅰ」の内容を包含する情報学の理論、データサイエンス、プログラミングなどのコンピュータサイエンス、ネットワークなどを基礎から学ぶ。また、人間と情報技術の関わりなどを扱う人間情報学のコアとなる科目も学修する。
さらに、情報やデータから新たな価値を見出すアントレプレナーシップを養成する教育課程のもと、1~2年次の基礎教育科目では社会科学の基礎を学ぶ。専門のデジタル社会PBL科目では、社会で活用されているデジタル技術を学ぶ授業や実験などに加え、課題解決型授業を設定している。
3年次進級時に情報学・データサイエンスを応用する分野の授業科目を各自選択履修し、4年次では学んだ知識や技術を活用し、新たな価値を実装する卒業研究を行う。応用分野(研究対象)には、人間情報、防災・エネルギー情報の情報分野、人間生活の支援を行うロボット分野を内包する。
情報学・データサイエンスを「専門」として身につけられる教育課程を編成。1~2年次では、「情報Ⅰ」の内容を包含する情報学の理論、データサイエンス、プログラミングなどのコンピュータサイエンス、ネットワークなどを基礎から学ぶ。また、人間と情報技術の関わりなどを扱う人間情報学のコアとなる科目も学修する。
さらに、情報やデータから新たな価値を見出すアントレプレナーシップを養成する教育課程のもと、1~2年次の基礎教育科目では社会科学の基礎を学ぶ。専門のデジタル社会PBL科目では、社会で活用されているデジタル技術を学ぶ授業や実験などに加え、課題解決型授業を設定している。
3年次進級時に情報学・データサイエンスを応用する分野の授業科目を各自選択履修し、4年次では学んだ知識や技術を活用し、新たな価値を実装する卒業研究を行う。応用分野(研究対象)には、人間情報、防災・エネルギー情報の情報分野、人間生活の支援を行うロボット分野を内包する。
他の大学の情報も確認しよう
秋田大学 の
過去問
秋田大学 の
資料請求
- 入学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。