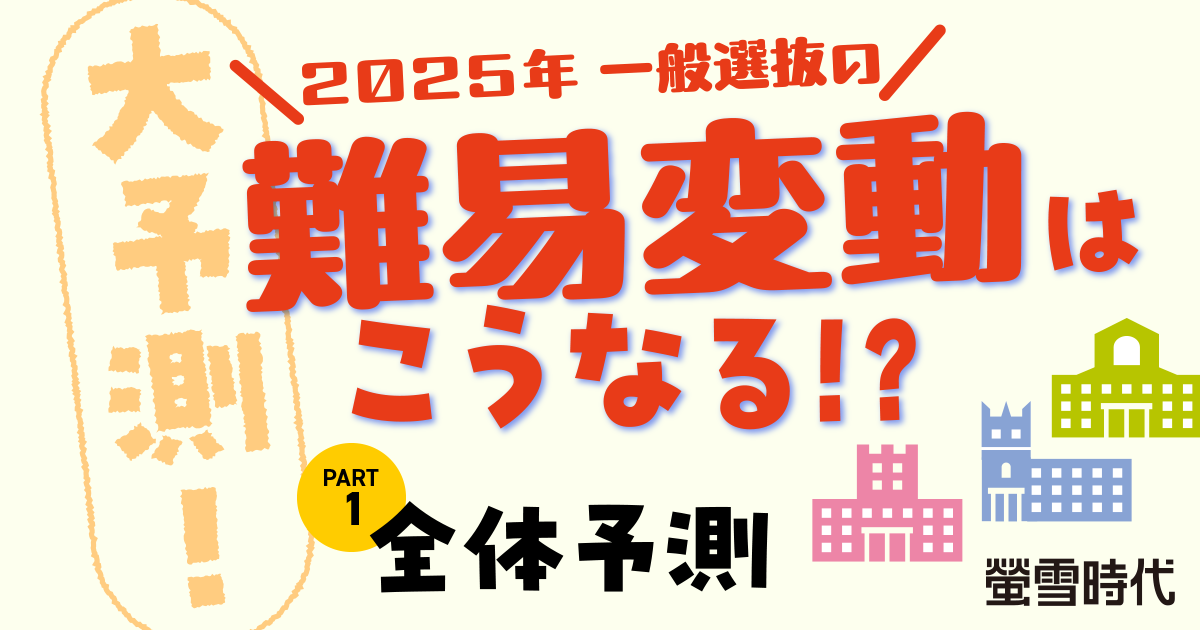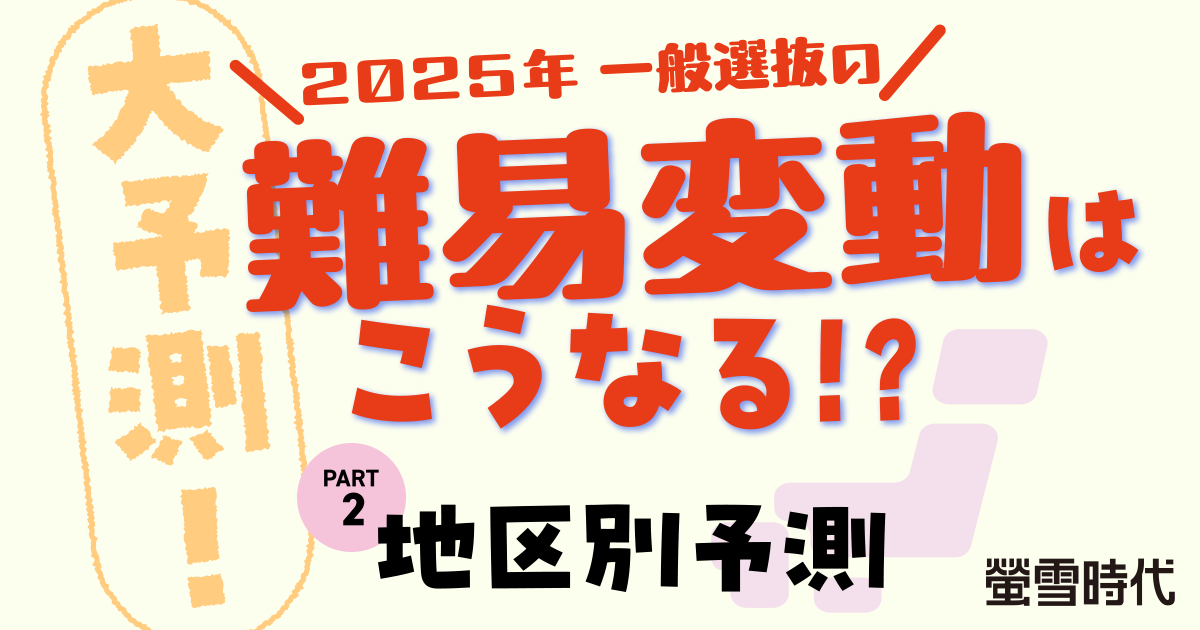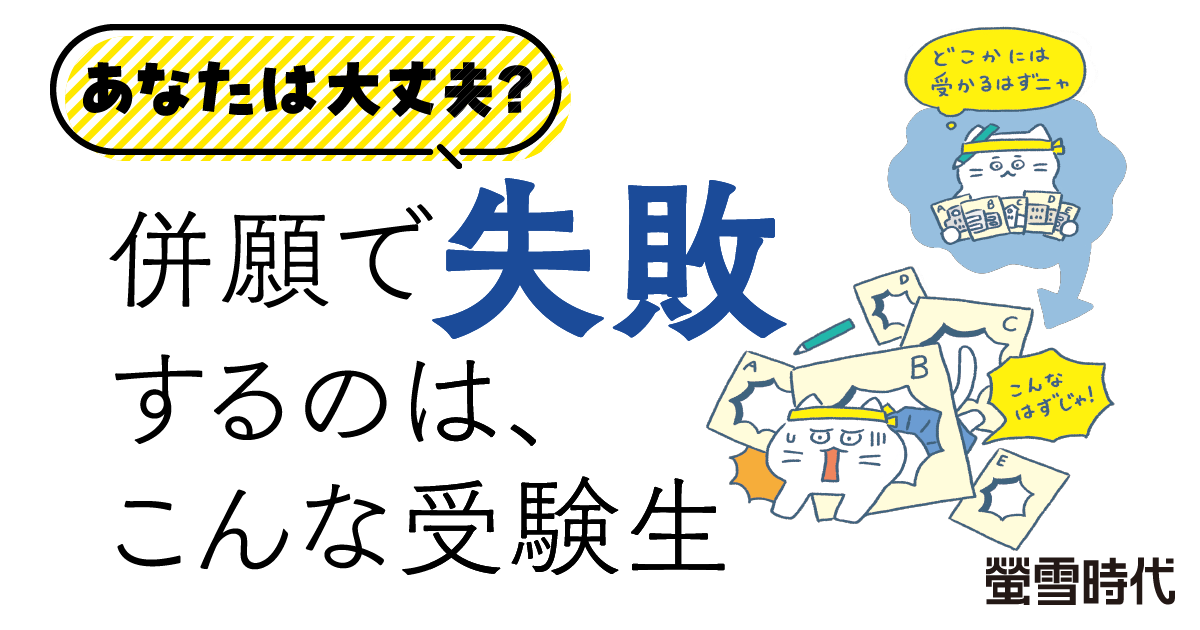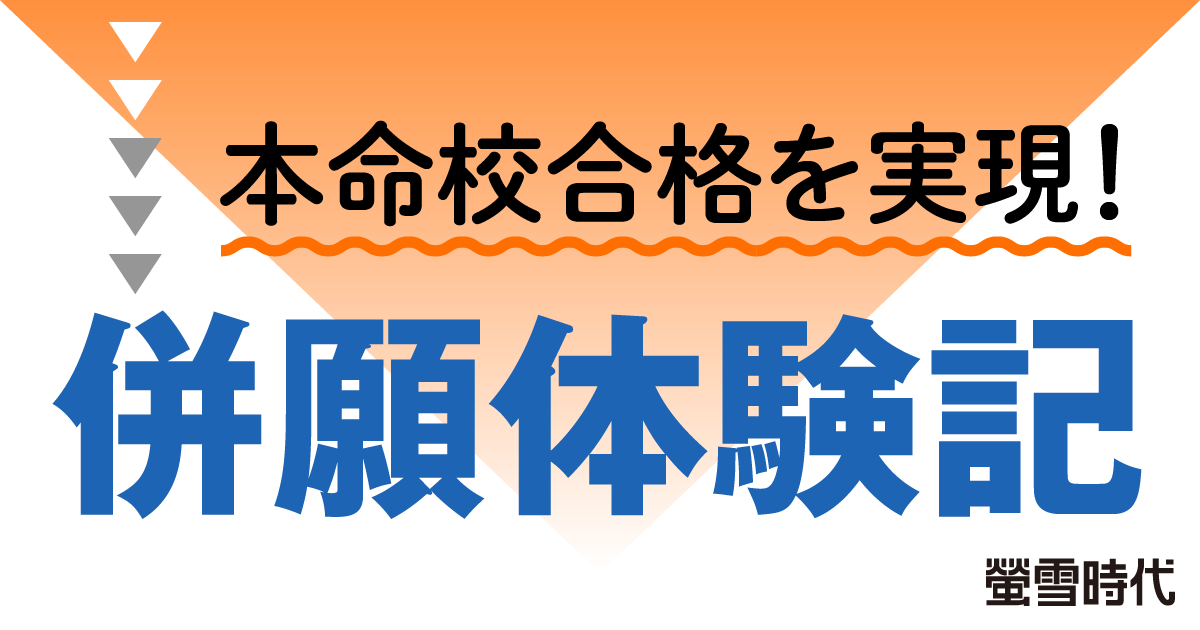学部内容
4系13専攻で構成される。人文社会系には、国語・社会・英語の3専攻、自然科学系には、数学・理科・技術の3専攻、芸術・生活・健康系には、音楽・美術・家政・保健体育の4専攻、教育人間科学系には、教育・教育心理・特別支援教育の3専攻がある。
いずれの専攻もそれぞれ定められた卒業必要単位数を修得すれば、履修コースごとに指定された教員免許状(小学校・中学校・高校・幼稚園・特別支援学校)を取得できる。このほか、社会教育主事補、学芸員、学校図書館司書教諭の資格が取得可能である。
◆人文社会系では、人間の知的環境としての「文化」および生活の場としての「社会」を対象として、多角的視点で、地域の問題からグローバルな問題までを、総合的に探究していく。これらの教育・研究を通じて、幅広い視野、探究的思考力および豊かな人間理解力を持った学校教員の養成を目指す。
◆自然科学系では、科学技術の専門的知識および技能を修得させ、実験・実習・演習を通して応用能力(問題解決能力)を育成する。さらに、子どもと触れ合う総合的・実践的な学習を通して人間を理解する能力を高める。これらの教育・研究を通して、高度情報化社会での教育に対応できる小学校教員や、数学・理科・技術の中学校教員の養成を目指す。
◆芸術・生活・健康系の音楽・美術の各専攻では、視覚芸術としての美術と、聴覚芸術としての音楽のそれぞれの分野において、技術的な表現の教育・研究と哲学的・論理的・宗教学的・文学的などの思想的な表現の研究を行う。これにより、芸術性の理解と創造性を育成し、芸術文化についての豊かな専門的識見と能力の形成を行い、義務教育を中核とした学校教育における美術・音楽系の芸術教育の実践的指導力を培うことができる。
家政・保健体育の各専攻では、現代社会においてわれわれが直面する諸課題を生活・健康をキーワードに探究する。より人間的で豊かなライフステージは、生活文化や生活環境などについての適切な理解と、積極的な活動や休養という身体に対する有効な働きかけによって可能となるものである。
◆教育人間科学系では、教育学、心理学および特別支援教育の知見をベースとして、人間にとっての教育の意義、「学び」や「育ち」のプロセス、教育活動における人間関係などについて総合的に探究する。
△新入生の男女比率(2024年) 男44%・女56%