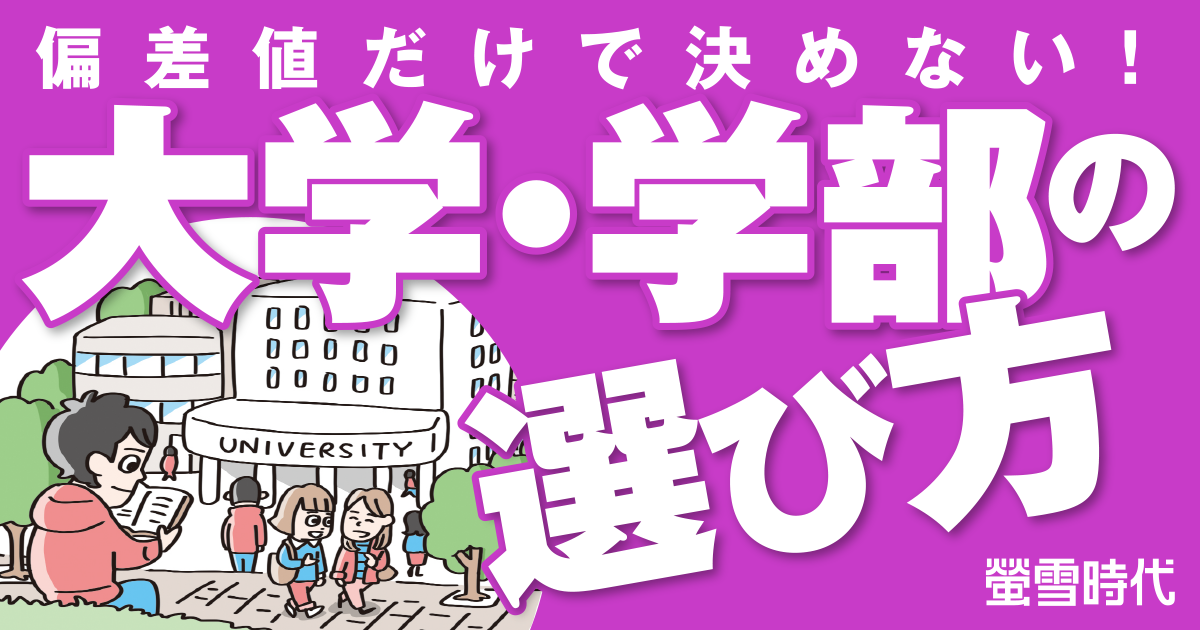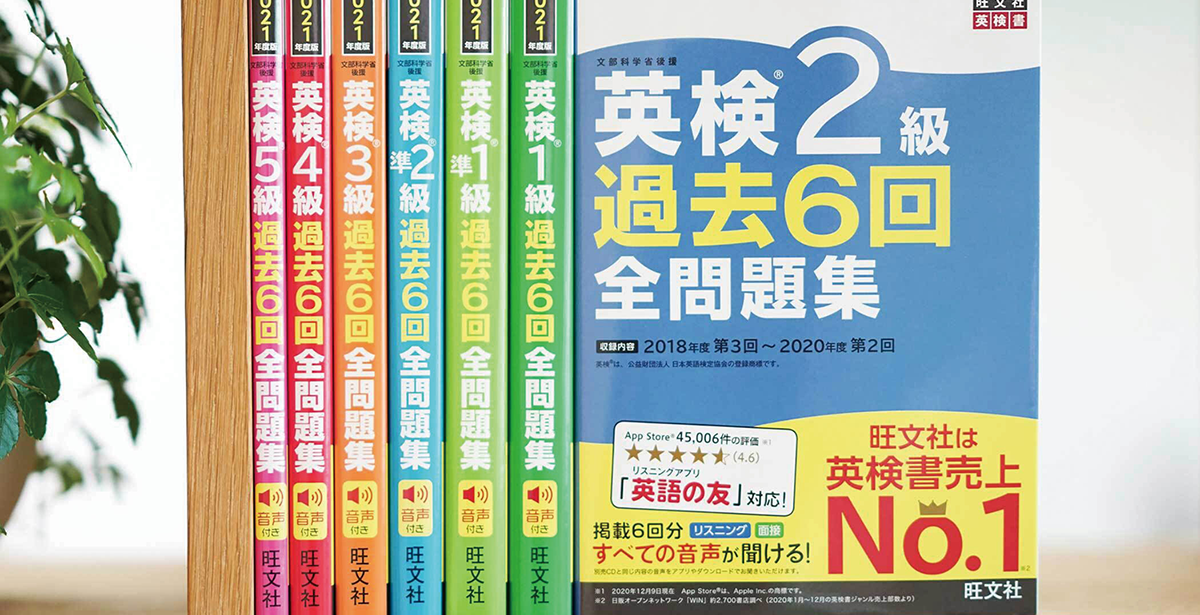学部で絞り込む
歴史
設置 1949、改組 2004
学科定員
地域170<地域創造60、人間形成55、国際地域文化55>
学部内容
地域の公共的課題の探究に関わる自然・社会・文化に関する幅広い知識を修得し、または実践的アプローチを通じて地域に生起するさまざまな諸問題を的確にとらえる深い探究心と、その解決のための論理的思考力、批判的判断力、創造的表現力や他者とのコミュニケーション力などを身につける。地域社会の再生・発展に高い倫理観と責任感を持って貢献できる人材を育成する。次の3コースにおいて専門性を深め、方法論を修得する。
◆地域創造コースでは、地域の現在および将来の課題に対し、積極的かつ主体的に取り組み、人びとの生活や産業など地域社会を支え、地域創造に資するキーパーソンとなり得る人材を育成する。学修を明確化するため、コミュニティマネジメント、ソーシャルビジネス、政策科学の3プログラムを置く。
◆人間形成コースでは、人間形成に関わる諸理論と実践を学び、学校教育を含む生涯にわたる人間形成(生涯発達)の立場から、地域と教育の関係を再構築し、地域の人づくりを支えるキーパーソンを育成する。小学校・幼稚園・特別支援学校教諭免許と保育士資格の取得が可能。学修を明確化するため、発達福祉、学習デザイン、地域と教育の3プログラムを置く。
◆国際地域文化コースでは、さまざまな文化の関係性と、それが生活において持つ意味を理解して、日本を含む世界のさまざまな地域で、異質なものを相互に認め合いながら、「一人ひとりの生活と生の充実」「つながりの創出」を実現するために必要な知識や技法、言語能力や現地感覚・現場感覚を身につけた人材を育成する。学修を明確化するため、日本の歴史と文化、グローバルな文化と地域、創造性とコミュニティの3プログラムを置く。
△新入生の男女比率(2024年) 男46%・女54%
◆地域創造コースでは、地域の現在および将来の課題に対し、積極的かつ主体的に取り組み、人びとの生活や産業など地域社会を支え、地域創造に資するキーパーソンとなり得る人材を育成する。学修を明確化するため、コミュニティマネジメント、ソーシャルビジネス、政策科学の3プログラムを置く。
◆人間形成コースでは、人間形成に関わる諸理論と実践を学び、学校教育を含む生涯にわたる人間形成(生涯発達)の立場から、地域と教育の関係を再構築し、地域の人づくりを支えるキーパーソンを育成する。小学校・幼稚園・特別支援学校教諭免許と保育士資格の取得が可能。学修を明確化するため、発達福祉、学習デザイン、地域と教育の3プログラムを置く。
◆国際地域文化コースでは、さまざまな文化の関係性と、それが生活において持つ意味を理解して、日本を含む世界のさまざまな地域で、異質なものを相互に認め合いながら、「一人ひとりの生活と生の充実」「つながりの創出」を実現するために必要な知識や技法、言語能力や現地感覚・現場感覚を身につけた人材を育成する。学修を明確化するため、日本の歴史と文化、グローバルな文化と地域、創造性とコミュニティの3プログラムを置く。
△新入生の男女比率(2024年) 男46%・女54%
歴史
設置 1949
学科定員
計240 医学80(増員申請中 ※医学部医学科では、前期日程で「地域枠19名」および学校推薦型選抜Ⅱで緊急医師確保対策に基づく「特別養成枠6名」を継続申請予定です。)、生命科学40、保健120<看護学80、検査技術科学40>
学部内容
医学科は、高い倫理観と豊かな人間性を備え、地域特性に合わせた医療の実践や最先端の医学を創造できる医師の養成を教育目標としている。
解剖学、生理学、病理学、感染制御学、社会医学、医学教育学、ゲノム再生医学、病態解析医学、統合内科医学、器官制御外科学、感覚運動医学、脳神経医科学、地域医療学、臨床感染症学の14講座がある。
生命科学科では、医学的な基礎知識を持ったバイオサイエンティストの養成を目指す。一般的な基礎医学を学んだ上で、生命の仕組みを、遺伝子の発現とその制御、生体分子間・細胞間の相互作用といった観点から理解する。さらに、より高次な生体機能としての免疫機能と神経機能を基本に置いて、生命の仕組みの解析に役立つバイオテクノロジーの習得と、医学的な考え方を学ぶ。分子細胞生物学、染色体医工学、機能形態学の3講座がある。
保健学科には、看護学専攻と検査技術科学専攻の2専攻がある。
◆看護学専攻では、豊かな人間性と幅広い教養を身につけながら、医療のなかでの看護の独自性と協調性を学び、実践的な専門知識と技能を習得する。
基礎看護学、成人・老人看護学、母性・小児家族看護学、地域・精神看護学の4講座がある。
◆検査技術科学専攻では、現代医学を支える医療チームの一員にふさわしい人格と教養を身につけながら、論理的・開発的な能力を習得する。主に臨床検査技術学を学ぶ。生体制御学、病態検査学の2講座がある。
△新入生の男女比率(2024年) 男33%・女67%
△2024年医師国家試験合格率(新卒) 92.5%
解剖学、生理学、病理学、感染制御学、社会医学、医学教育学、ゲノム再生医学、病態解析医学、統合内科医学、器官制御外科学、感覚運動医学、脳神経医科学、地域医療学、臨床感染症学の14講座がある。
生命科学科では、医学的な基礎知識を持ったバイオサイエンティストの養成を目指す。一般的な基礎医学を学んだ上で、生命の仕組みを、遺伝子の発現とその制御、生体分子間・細胞間の相互作用といった観点から理解する。さらに、より高次な生体機能としての免疫機能と神経機能を基本に置いて、生命の仕組みの解析に役立つバイオテクノロジーの習得と、医学的な考え方を学ぶ。分子細胞生物学、染色体医工学、機能形態学の3講座がある。
保健学科には、看護学専攻と検査技術科学専攻の2専攻がある。
◆看護学専攻では、豊かな人間性と幅広い教養を身につけながら、医療のなかでの看護の独自性と協調性を学び、実践的な専門知識と技能を習得する。
基礎看護学、成人・老人看護学、母性・小児家族看護学、地域・精神看護学の4講座がある。
◆検査技術科学専攻では、現代医学を支える医療チームの一員にふさわしい人格と教養を身につけながら、論理的・開発的な能力を習得する。主に臨床検査技術学を学ぶ。生体制御学、病態検査学の2講座がある。
△新入生の男女比率(2024年) 男33%・女67%
△2024年医師国家試験合格率(新卒) 92.5%
歴史
設置 1965、改組 2015
学科定員
計450 機械物理系115、電気情報系125、化学バイオ系100、社会システム土木系110
学部内容
「未来の工学、わかる工学、役立つ工学」という3つの工学(広学)に関わるコンセプトをもとに、工学部の主要な研究分野を担う教員の教育組織を生かして、工学の基礎から周辺専門分野の幅広い知識と工学的スキルを体系的に教育できる4学科を設置している。
各学科には、社会ニーズに柔軟に対応できる高度専門教育用の17種類の教育プログラムを設定し、進学希望者に対してより広い選択肢を提供する。
また、工学部附属5センターと連携した実践的工学教育を通じて、工学的諸問題に対して広学的技術を駆使して解決できる人材養成の教育を推進する。
機械物理系学科では、ものづくりを支える機械工学と、ものの原理・仕組みを考究する物理工学を学ぶ。いずれも製造業の基盤をなす重要な分野である。機械工学や物理工学を修得し、ロボティクス、航空宇宙工学、医工学など最先端技術のハード・ソフトの両方の分野にも応用できる能力を有する人材を育成する。
電気情報系学科では、多様化する高度情報社会を支えるハードウェア技術である電気電子工学と、ソフトウェア技術である情報工学の両方の幅広い知識と技術を身につける。基礎からしっかり学べる系統的なカリキュラムにより、ハードとソフトの両面に精通し、情報社会の豊かな発展に寄与できる人材を育成する。
化学バイオ系学科では、化学工業、薬品製造、食品製造、臨床検査などにおいて重要な分野である化学とバイオテクノロジーに関わる生命科学を学ぶ。化学ならびに生命科学を基盤とする幅広い知識とプログラム別の専門知識を修得し、化学・医薬品・食品・エネルギーなどの産業と環境問題の解決、医工連携を通じて健康増進や医療に貢献する材料や製品の創製に応用できる能力を有する人材を育成する。
社会システム土木系学科では、生活や社会経済の営みに関わる社会システム工学と、社会基盤や防災に関わる土木工学を学ぶ。いずれも安全安心な社会構築において重要な分野である。国土と地域社会の計画・建設・管理に必要なハード・ソフトの幅広い知識と応用力を有し、自然と調和した持続可能な社会の構築に貢献できる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男81%・女19%
各学科には、社会ニーズに柔軟に対応できる高度専門教育用の17種類の教育プログラムを設定し、進学希望者に対してより広い選択肢を提供する。
また、工学部附属5センターと連携した実践的工学教育を通じて、工学的諸問題に対して広学的技術を駆使して解決できる人材養成の教育を推進する。
機械物理系学科では、ものづくりを支える機械工学と、ものの原理・仕組みを考究する物理工学を学ぶ。いずれも製造業の基盤をなす重要な分野である。機械工学や物理工学を修得し、ロボティクス、航空宇宙工学、医工学など最先端技術のハード・ソフトの両方の分野にも応用できる能力を有する人材を育成する。
電気情報系学科では、多様化する高度情報社会を支えるハードウェア技術である電気電子工学と、ソフトウェア技術である情報工学の両方の幅広い知識と技術を身につける。基礎からしっかり学べる系統的なカリキュラムにより、ハードとソフトの両面に精通し、情報社会の豊かな発展に寄与できる人材を育成する。
化学バイオ系学科では、化学工業、薬品製造、食品製造、臨床検査などにおいて重要な分野である化学とバイオテクノロジーに関わる生命科学を学ぶ。化学ならびに生命科学を基盤とする幅広い知識とプログラム別の専門知識を修得し、化学・医薬品・食品・エネルギーなどの産業と環境問題の解決、医工連携を通じて健康増進や医療に貢献する材料や製品の創製に応用できる能力を有する人材を育成する。
社会システム土木系学科では、生活や社会経済の営みに関わる社会システム工学と、社会基盤や防災に関わる土木工学を学ぶ。いずれも安全安心な社会構築において重要な分野である。国土と地域社会の計画・建設・管理に必要なハード・ソフトの幅広い知識と応用力を有し、自然と調和した持続可能な社会の構築に貢献できる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男81%・女19%
歴史
設置 1949
学科定員
計255 生命環境農220、共同獣医35
学部内容
生命環境農学科では、ローカルからグローバルまでの広範な課題の解決に農学の立場から貢献する人材の育成を目指す。鳥取の豊かな自然と食資源、学部に隣接した農場と広い教育研究林など農学を極める「地の利」と、鳥取高農設立以来100年を超えて先人が蓄えた「知の利」を生かして、未来を開く農学教育を推進する。1年次に共通科目で基礎を学び、2年次より以下の4コースに分属して専門性を高める。
◆国際乾燥地農学コースでは、乾燥地を中心とした海外諸地域の環境問題や農業問題の本質を理解し、それらの地域における環境保全や農業農村開発に貢献できる人材を育成する。
◆里地里山環境管理学コースでは、人びとの営みが地域の資源・環境に及ぼす影響を自然科学と社会科学の広い視野から理解し、里地里山の持続可能な保全・利用に貢献できる人材を育成する。
◆植物菌類生産科学コースでは、新たに開発する生物資源とニホンナシやキノコなど、鳥取県の特産である既存の生物資源を生産し、高度に活用できる人材を育成する。
◆農芸化学コースでは、生物資源の有効利用ならびに食品の栄養評価・機能性について体系的な知識と技術を有する人材を育成する。
共同獣医学科では、人と動物との共生を目指し、「動物と社会のつながり」「動物と人の健康・福祉」をキーワードに、動物の健康だけでなく、あらゆる命の専門家の育成を目指す。
6年間教育課程を通じ、日本だけでなく国際社会をリードする者に不可欠な教養教育を基盤に、総合的・実践的かつ高度な獣医学教育を鳥取大と岐阜大の教員が展開する。
鳥取大で授業を実施する科目、学生が一方の大学に移動・集合して受講する科目、遠隔教育システムや移動により岐阜大教員が授業を実施する科目を履修する。卒業時は両大学学長連名の学位記が授与される。
△新入生の男女比率(2024年) 男49%・女51%
◆国際乾燥地農学コースでは、乾燥地を中心とした海外諸地域の環境問題や農業問題の本質を理解し、それらの地域における環境保全や農業農村開発に貢献できる人材を育成する。
◆里地里山環境管理学コースでは、人びとの営みが地域の資源・環境に及ぼす影響を自然科学と社会科学の広い視野から理解し、里地里山の持続可能な保全・利用に貢献できる人材を育成する。
◆植物菌類生産科学コースでは、新たに開発する生物資源とニホンナシやキノコなど、鳥取県の特産である既存の生物資源を生産し、高度に活用できる人材を育成する。
◆農芸化学コースでは、生物資源の有効利用ならびに食品の栄養評価・機能性について体系的な知識と技術を有する人材を育成する。
共同獣医学科では、人と動物との共生を目指し、「動物と社会のつながり」「動物と人の健康・福祉」をキーワードに、動物の健康だけでなく、あらゆる命の専門家の育成を目指す。
6年間教育課程を通じ、日本だけでなく国際社会をリードする者に不可欠な教養教育を基盤に、総合的・実践的かつ高度な獣医学教育を鳥取大と岐阜大の教員が展開する。
鳥取大で授業を実施する科目、学生が一方の大学に移動・集合して受講する科目、遠隔教育システムや移動により岐阜大教員が授業を実施する科目を履修する。卒業時は両大学学長連名の学位記が授与される。
△新入生の男女比率(2024年) 男49%・女51%
他の大学の情報も確認しよう
鳥取大学 の
過去問
鳥取大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。