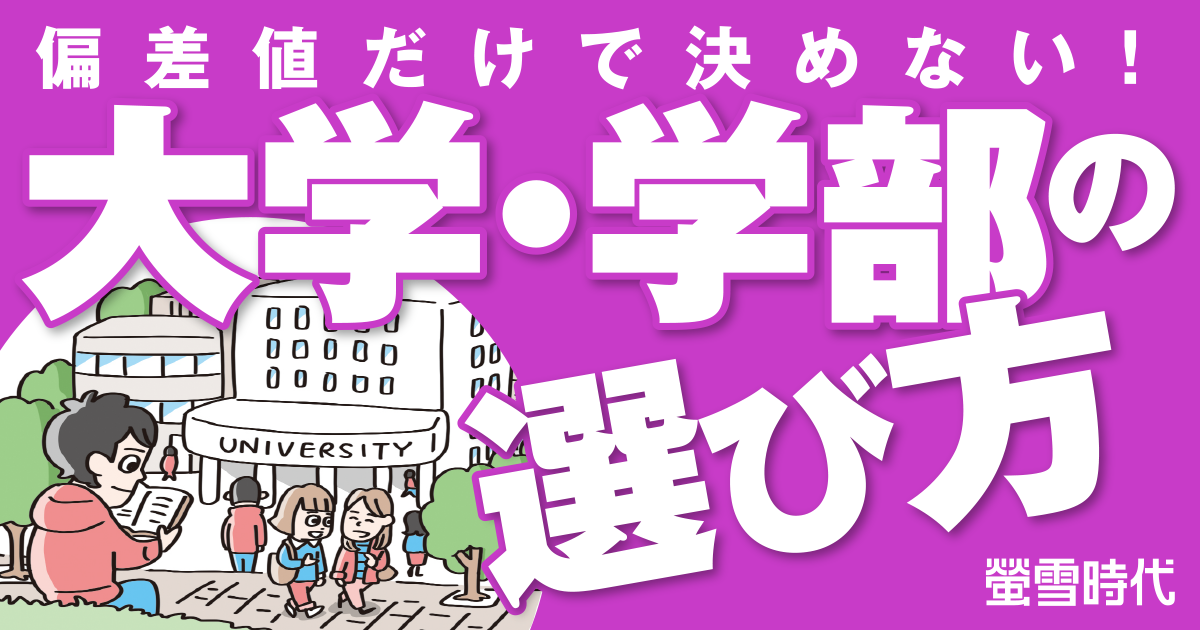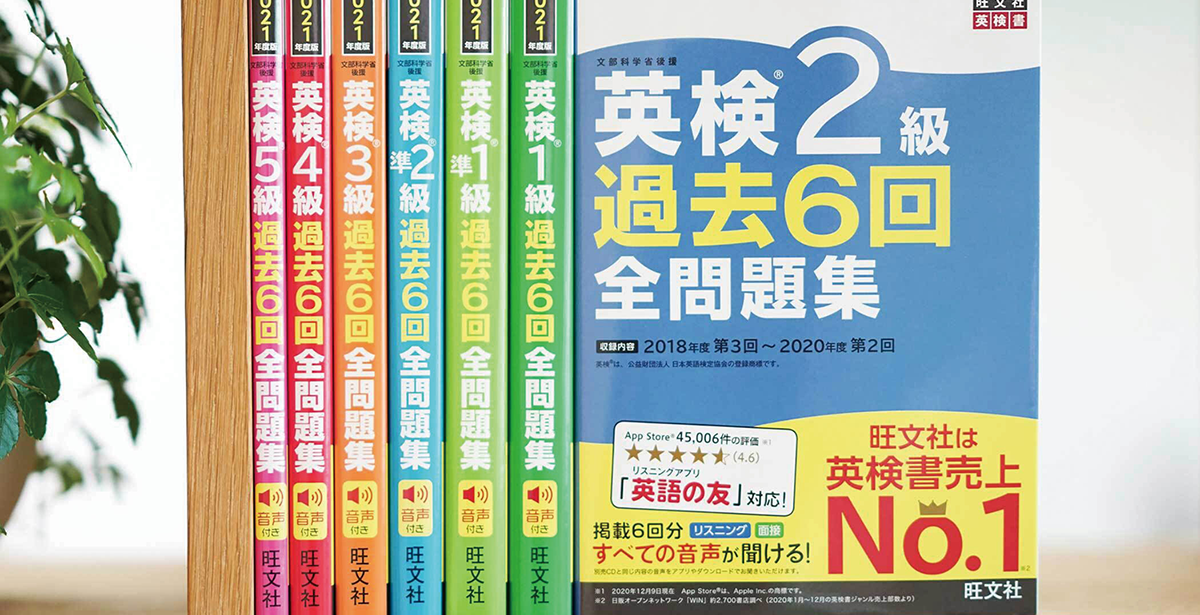学部で絞り込む
歴史
設置 1949、改組 1978
学科定員
計175 法経76、社会文化47、言語文化52
学部内容
法経学科では、法学と経済学の両面から、変化する現代社会について学ぶ。格差の拡大、非正規雇用の拡大、子育て環境の整備や医療・介護・福祉のあり方など、基本的人権に関わる問題がますます重要性を高めるなか、これらの課題解決に必要とされる法学・経済学の基本的な知識と応用力を身につけ、分析能力・政策立案能力や問題処理能力を養う。法学、経済学、司法特別の3コースがあり、3年次に希望するコースを自由に選ぶことができる。
社会文化学科では、社会、歴史、そして文化について、調査や実習等を通じて体験的に学ぶことを重視する。学生は1年次の後期から、以下の2コースに分かれる。
◆現代社会コースでは、人間の行動や活動、家族や地域などの身近な社会からグローバルな社会、私たちの生活環境、そして民俗や伝統、文化についての問題を、社会学・地理学・文化人類学の立場から考えを説明する力を身につけることを目指す。
◆歴史と考古コースは、歴史学と考古学の2分野からなる。歴史学では日本史・東洋史・西洋史・現代史について専門的に学び、考古学では主に日本や韓半島を対象に学ぶ。
言語文化学科では、東洋・西洋の言語文化について古代から現代まで幅広く学ぶことができる。学生は2年次以降、所属する研究室を自由に選び、自分が興味を持つ事柄を深く学びながら、言語文化を理解する方法を習得し、論理的に思考を表現する力を身につけ、語学力を高めていく。
△新入生の男女比率(2024年) 男49%・女51%
社会文化学科では、社会、歴史、そして文化について、調査や実習等を通じて体験的に学ぶことを重視する。学生は1年次の後期から、以下の2コースに分かれる。
◆現代社会コースでは、人間の行動や活動、家族や地域などの身近な社会からグローバルな社会、私たちの生活環境、そして民俗や伝統、文化についての問題を、社会学・地理学・文化人類学の立場から考えを説明する力を身につけることを目指す。
◆歴史と考古コースは、歴史学と考古学の2分野からなる。歴史学では日本史・東洋史・西洋史・現代史について専門的に学び、考古学では主に日本や韓半島を対象に学ぶ。
言語文化学科では、東洋・西洋の言語文化について古代から現代まで幅広く学ぶことができる。学生は2年次以降、所属する研究室を自由に選び、自分が興味を持つ事柄を深く学びながら、言語文化を理解する方法を習得し、論理的に思考を表現する力を身につけ、語学力を高めていく。
△新入生の男女比率(2024年) 男49%・女51%
歴史
設置 1949
学科定員
学校教育課程130
学部内容
山陰地域唯一の教員養成専門学部として、優れた「教師力」を育むために、次のような特色ある教育システム・カリキュラムを構築している。
①「教科の専門性を持った小学校教員」「小学校教育を熟知した中学校教員」を養成するために、小中免許併有を目指す「主・副専攻」制を導入。
主専攻は、小学校教育・特別支援教育・国語科教育・英語科教育・社会科教育・数学科教育・理科教育・保健体育科教育・音楽科教育・美術科教育に分かれている。
②さまざまな教育活動や地域活動に参加して教育実践力を高める「1,000時間体験学修プログラム」の必修化。
③教師力の向上を可視化して次の学びに生かす学部独自の「学修ポートフォリオ」。
④「島根大学未来教師塾」で各種セミナーなどを実施し、教職への道を力強く支援。
△新入生の男女比率(2024年) 男40%・女60%
①「教科の専門性を持った小学校教員」「小学校教育を熟知した中学校教員」を養成するために、小中免許併有を目指す「主・副専攻」制を導入。
主専攻は、小学校教育・特別支援教育・国語科教育・英語科教育・社会科教育・数学科教育・理科教育・保健体育科教育・音楽科教育・美術科教育に分かれている。
②さまざまな教育活動や地域活動に参加して教育実践力を高める「1,000時間体験学修プログラム」の必修化。
③教師力の向上を可視化して次の学びに生かす学部独自の「学修ポートフォリオ」。
④「島根大学未来教師塾」で各種セミナーなどを実施し、教職への道を力強く支援。
△新入生の男女比率(2024年) 男40%・女60%
歴史
設置 2017
学科定員
人間科学80
学部内容
入学後3つのコースに分かれる。
◆心理学コースでは、人の心や行動の仕組みなどについて臨床心理・実験心理の知見から学び、人間へ多様にアプローチする力を養う。
◆福祉社会コースでは、社会福祉学の理論や技術を学び、「人を支える」という視点から社会が抱える問題について考えて実践する力を養う。
◆身体活動・健康科学コースでは、健康科学や運動機能などを学び、地域住民とともに健康課題の解決を進めるための知識・技術・実践力を養う。
△新入生の男女比率(2024年) 男26%・女74%
◆心理学コースでは、人の心や行動の仕組みなどについて臨床心理・実験心理の知見から学び、人間へ多様にアプローチする力を養う。
◆福祉社会コースでは、社会福祉学の理論や技術を学び、「人を支える」という視点から社会が抱える問題について考えて実践する力を養う。
◆身体活動・健康科学コースでは、健康科学や運動機能などを学び、地域住民とともに健康課題の解決を進めるための知識・技術・実践力を養う。
△新入生の男女比率(2024年) 男26%・女74%
歴史
設置 1975、統合 2003
学科定員
計162 医学102、看護60
学部内容
医学科の教育は、医学部附属病院での早期体験実習を通しての医学学習の動機づけ、少人数グループにおける問題解決型学習による積極的学習態度の育成、6年一貫医学英語教育による高い英語力の習得、地域の医療施設での臨床実習による実践的な臨床教育など、さまざまな工夫がなされている。
1年次には、プロフェッショナリズムや早期体験実習のほか、基礎科目や教養育成科目を履修する。1年次後期から3年次前期にかけては解剖学や生理学などの基礎医学、臨床基礎医学、社会医学を中心に履修する。3年次後期からは臓器別・系統別のコースからなる医学チュートリアルを約1年間にわたり履修する。
4~6年次には72週間にわたり臨床実習を行い、それまでに習得した医学知識をもとに実践的な医学知識・技術を学ぶ。臨床実習では医学部附属病院、関連教育病院に加えて、県下の多数の地域医療施設での実習が選択できる。
看護学科では、1年次には一般教養や看護職の基本となる人間の理解、看護のあり方、ケアの倫理、コミュニケーションの方法などについて、2年次には基礎的な医学知識や心理学などとともに、科学的根拠に基づいて看護を実践する方法を学習する。
2・3年次には、生活習慣病やがん患者および重症者のケアなどを学ぶ成人看護学、人間の成長発達に伴って健康を支える小児・母性・老年看護学、心の健康を支える精神看護学、市町村や学校など生活の場で健康を支える地域看護学など、より専門的に学習を進めていく。3・4年次には、実際の看護現場で実習を行いながら看護の知識と技術を高め、4年次には大学での学習の集大成として「総合実習」「卒業研究」に取り組み、自分の看護観を形成し深めていく。
△新入生の男女比率(2024年) 男31%・女69%
△2024年医師国家試験合格率(新卒) 95.9%
1年次には、プロフェッショナリズムや早期体験実習のほか、基礎科目や教養育成科目を履修する。1年次後期から3年次前期にかけては解剖学や生理学などの基礎医学、臨床基礎医学、社会医学を中心に履修する。3年次後期からは臓器別・系統別のコースからなる医学チュートリアルを約1年間にわたり履修する。
4~6年次には72週間にわたり臨床実習を行い、それまでに習得した医学知識をもとに実践的な医学知識・技術を学ぶ。臨床実習では医学部附属病院、関連教育病院に加えて、県下の多数の地域医療施設での実習が選択できる。
看護学科では、1年次には一般教養や看護職の基本となる人間の理解、看護のあり方、ケアの倫理、コミュニケーションの方法などについて、2年次には基礎的な医学知識や心理学などとともに、科学的根拠に基づいて看護を実践する方法を学習する。
2・3年次には、生活習慣病やがん患者および重症者のケアなどを学ぶ成人看護学、人間の成長発達に伴って健康を支える小児・母性・老年看護学、心の健康を支える精神看護学、市町村や学校など生活の場で健康を支える地域看護学など、より専門的に学習を進めていく。3・4年次には、実際の看護現場で実習を行いながら看護の知識と技術を高め、4年次には大学での学習の集大成として「総合実習」「卒業研究」に取り組み、自分の看護観を形成し深めていく。
△新入生の男女比率(2024年) 男31%・女69%
△2024年医師国家試験合格率(新卒) 95.9%
歴史
設置 1949、改組 1995
学科定員
総合理工370
*定員は2025年
学部内容
2025年、物理工学科、物質化学科、地球科学科、数理科学科、知能情報デザイン学科、機械・電気電子工学科、建築デザイン学科の7学科から総合理工学科の1学科に改組予定(設置認可申請中)。
総合理工学科では、専門の学問教育を重視しつつ、その枠にとらわれることなく、自身が目標とする人材像に必要な知識や考え方を修得できるよう、従来の7学科を1学科 (総合理工学科)に再編する。
なお、社会で活躍する人材像を「先端ものづくり分野」「数理データサイエンス・IT・デジタル分野」「自然環境・住環境分野」の「3つの分野」に分類することで、主体的に選択・設計できる柔軟で幅広い教育カリキュラムを用意する。
1年次で全学基礎教育科目と理工学の基礎を学び、2年次で専門分野を決定する。各分野、およびその境界領域での人材像に対応した教育の「標準履修モデル」が示され、それぞれの人材像に必要な専門知識と実践的な理工学の知識を身につけることができる。
先端ものづくり分野では、物理学、化学、機械工学、電気電子工学などの学術分野を中心に、半導体・マイクロプロセッサ関連、ロボット工学・メカトロニクス、先端監視・センサー、蓄電池材料や物質創成など、先端ものづくり分野の技術者・研究者として活躍するための基盤を学ぶ。
数理データサイエンス・IT・デジタル分野では、数学、情報科学などの学術分野を中心に、データサイエンス・データ分析、高度情報通信、情報セキュリティ、人工知能(AI)、機械学習など、次世代情報産業を支える技術者・研究者として活躍するための基盤を学ぶことができる。
自然環境・住環境分野では、化学、環境科学、地球科学、建築学などの学術分野を中心に、脱炭素化・環境の分析と評価、再生可能資源、地球環境変動や自然災害への備え、住まいから都市までの建築デザインなど、持続的社会の実現に向けた技術者・研究者として活躍するための基盤を学ぶことができる。
△新入生の男女比率(2024年) 男80%・女20%
総合理工学科では、専門の学問教育を重視しつつ、その枠にとらわれることなく、自身が目標とする人材像に必要な知識や考え方を修得できるよう、従来の7学科を1学科 (総合理工学科)に再編する。
なお、社会で活躍する人材像を「先端ものづくり分野」「数理データサイエンス・IT・デジタル分野」「自然環境・住環境分野」の「3つの分野」に分類することで、主体的に選択・設計できる柔軟で幅広い教育カリキュラムを用意する。
1年次で全学基礎教育科目と理工学の基礎を学び、2年次で専門分野を決定する。各分野、およびその境界領域での人材像に対応した教育の「標準履修モデル」が示され、それぞれの人材像に必要な専門知識と実践的な理工学の知識を身につけることができる。
先端ものづくり分野では、物理学、化学、機械工学、電気電子工学などの学術分野を中心に、半導体・マイクロプロセッサ関連、ロボット工学・メカトロニクス、先端監視・センサー、蓄電池材料や物質創成など、先端ものづくり分野の技術者・研究者として活躍するための基盤を学ぶ。
数理データサイエンス・IT・デジタル分野では、数学、情報科学などの学術分野を中心に、データサイエンス・データ分析、高度情報通信、情報セキュリティ、人工知能(AI)、機械学習など、次世代情報産業を支える技術者・研究者として活躍するための基盤を学ぶことができる。
自然環境・住環境分野では、化学、環境科学、地球科学、建築学などの学術分野を中心に、脱炭素化・環境の分析と評価、再生可能資源、地球環境変動や自然災害への備え、住まいから都市までの建築デザインなど、持続的社会の実現に向けた技術者・研究者として活躍するための基盤を学ぶことができる。
△新入生の男女比率(2024年) 男80%・女20%
歴史
設置 2023
学科定員
材料エネルギー80
学部内容
全世界で対応が急がれるエネルギー問題を素材・材料の視点から理解し、解決する新しい学部である。材料工学分野の知識・技能に加え、情報科学を活用して材料開発を行う「マテリアルズ・インフォマティクス」を修得する。また、研究成果・技術を社会に生かす「社会実装」方法を考え、新たな価値観を生み出すアントレプレナーシップの教育を行う。海外の大学とも連携し、グローバルな視点からイノベーションを創出し、地域産業の振興に貢献できる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男77%・女23%
△新入生の男女比率(2024年) 男77%・女23%
歴史
設置 1965、改組 2018
学科定員
計200 生命科学70、農林生産60、環境共生科学70
学部内容
生命科学科では、微生物から動物・植物に至る多様な生物が示すさまざまな生命現象についての基本的な理解と根本原理の解明を目指すとともに、これら生物が有するさまざまな有用機能を食品・化学工業、医薬・農薬製造業などの生物・化学産業に役立てるための教育と研究を行う。
農林生産学科では、農林業生産による豊かな人間社会の実現を目指して、農林産物に関する持続可能な生産技術、生産組織の経営や地域経済への影響についての教育と研究を行う。
環境共生科学科では、環境調和型社会の確立を目指し、豊かな自然と食糧生産の基盤である農山村地域をフィールドとして、地域資源および生態環境を適切に調査・評価し、総合的に保全・管理するための知識と技術を養成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男58%・女42%
農林生産学科では、農林業生産による豊かな人間社会の実現を目指して、農林産物に関する持続可能な生産技術、生産組織の経営や地域経済への影響についての教育と研究を行う。
環境共生科学科では、環境調和型社会の確立を目指し、豊かな自然と食糧生産の基盤である農山村地域をフィールドとして、地域資源および生態環境を適切に調査・評価し、総合的に保全・管理するための知識と技術を養成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男58%・女42%
他の大学の情報も確認しよう
島根大学 の
過去問
島根大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。