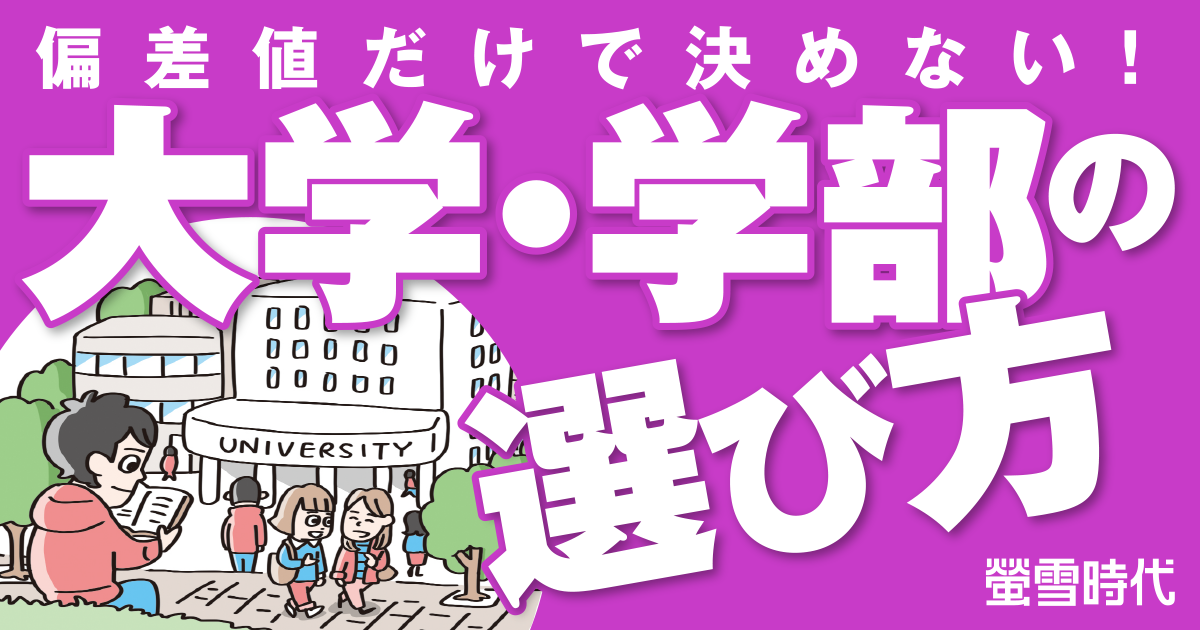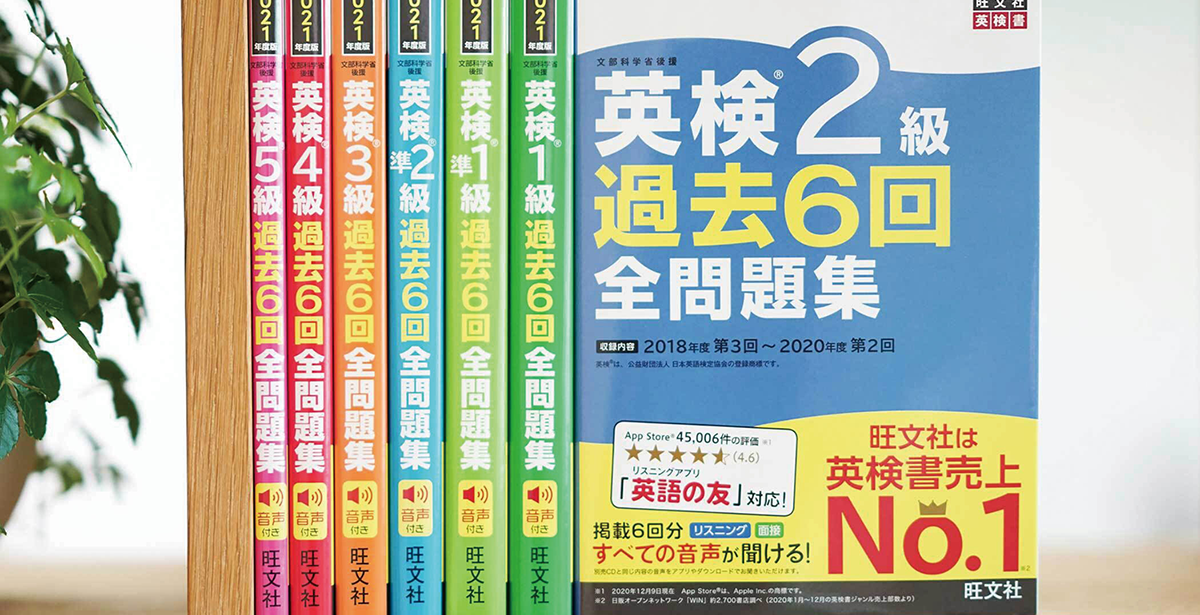学部で絞り込む
歴史
設置 1949、改組 2017
学科定員
計360 現代社会130、法律経済120、人間文化110
学部内容
現代社会学科には以下の2メジャーがある。
◆メディア文化メジャーでは、新聞、放送、インターネット、マンガ、音楽などの現代メディアの特質と、メディアによってつながる現代の社会や文化について学ぶ。情報を的確に読み解く能力を高めるだけでなく、取材、執筆、コンテンツ制作などの情報発信技術を実践的に養う。
◆国際・地域共創メジャーでは、グローバル化した国内外の「地域」を、社会学、地理学、政治学、国際学により理解し、高い調査・分析・提案能力を養う。地域志向と国際志向を両立したフィールドワークや行政・市民との連携授業により、まちづくりや多文化共生といった課題への対応を考える。
法律経済学科には、以下の2メジャーがある。
◆法学メジャーでは、法律を学び、憲法改正論、えん罪事件、子どもの虐待といった現代社会の諸課題を法的にどう解決すべきかを考える。行政学などの関連分野も専門として学ぶ。法学検定試験の受験を前提とした授業も取り入れ、法的思考力を磨く。
◆経済学・経営学メジャーでは、グローバル化した経済活動の仕組みや市場の役割、企業活動の意義について、経済学や経営学の理論と実践の双方から幅広く学ぶ。経済の政策・制度や企業の管理・会計手法を学ぶことで、地域経済や中小企業の課題を統合的に理解することを目指す。
人間文化学科には、以下の3メジャーがある。
◆文芸・思想メジャーでは、文学、哲学、言語学など人間の感情と思想に寄り添ってきた最古の学問領域を学ぶと同時に、「ことば」のセンスを磨き、駆使する能力を深めることで、人々の幸福、理想、誇り、生きがいとは何かについて、人々とともに考える力を養う。
◆歴史・考古学メジャーでは、古今東西の人類の歩みを見つめ、未来を見通す力を磨くため、歴史学と考古学を総合的に学ぶ。「歴史的思考力」を育み、文化遺産を生かしたまちづくりなどで、長期的な視野から地域の将来像を描き提案できる力をつける。
◆心理・人間科学メジャーでは、認知、感情、発達、社会、臨床といった心理学の諸領域を学び、人間の心の働きや行動について理解を深めるとともに、比較文化、比較文明という観点から人間文化の多様性と共通性を学ぶ。観察、面接、実験、心理検査やフィールドワークといった技法習得も重視する。
△新入生の男女比率(2023年) 男41%・女59%
◆メディア文化メジャーでは、新聞、放送、インターネット、マンガ、音楽などの現代メディアの特質と、メディアによってつながる現代の社会や文化について学ぶ。情報を的確に読み解く能力を高めるだけでなく、取材、執筆、コンテンツ制作などの情報発信技術を実践的に養う。
◆国際・地域共創メジャーでは、グローバル化した国内外の「地域」を、社会学、地理学、政治学、国際学により理解し、高い調査・分析・提案能力を養う。地域志向と国際志向を両立したフィールドワークや行政・市民との連携授業により、まちづくりや多文化共生といった課題への対応を考える。
法律経済学科には、以下の2メジャーがある。
◆法学メジャーでは、法律を学び、憲法改正論、えん罪事件、子どもの虐待といった現代社会の諸課題を法的にどう解決すべきかを考える。行政学などの関連分野も専門として学ぶ。法学検定試験の受験を前提とした授業も取り入れ、法的思考力を磨く。
◆経済学・経営学メジャーでは、グローバル化した経済活動の仕組みや市場の役割、企業活動の意義について、経済学や経営学の理論と実践の双方から幅広く学ぶ。経済の政策・制度や企業の管理・会計手法を学ぶことで、地域経済や中小企業の課題を統合的に理解することを目指す。
人間文化学科には、以下の3メジャーがある。
◆文芸・思想メジャーでは、文学、哲学、言語学など人間の感情と思想に寄り添ってきた最古の学問領域を学ぶと同時に、「ことば」のセンスを磨き、駆使する能力を深めることで、人々の幸福、理想、誇り、生きがいとは何かについて、人々とともに考える力を養う。
◆歴史・考古学メジャーでは、古今東西の人類の歩みを見つめ、未来を見通す力を磨くため、歴史学と考古学を総合的に学ぶ。「歴史的思考力」を育み、文化遺産を生かしたまちづくりなどで、長期的な視野から地域の将来像を描き提案できる力をつける。
◆心理・人間科学メジャーでは、認知、感情、発達、社会、臨床といった心理学の諸領域を学び、人間の心の働きや行動について理解を深めるとともに、比較文化、比較文明という観点から人間文化の多様性と共通性を学ぶ。観察、面接、実験、心理検査やフィールドワークといった技法習得も重視する。
△新入生の男女比率(2023年) 男41%・女59%
歴史
設置 1949
学科定員
計275 学校教育教員養成課程240<教育実践科学26、教科教育194、特別支援教育20>、養護教諭養成課程35
学部内容
学校教育教員養成課程は以下の3コース制。
◆教育実践科学コースでは、今日の教育現場で求められている実践的指導力を身につけた教員の養成を行う。学校教育の特性と問題点を理解し、児童・生徒の支援と学習指導について学ぶ。
◆教科教育コースは、言語・社会教育系(国語・社会・英語)、理数教育系(数学・理科)、音楽教育系(音楽)、美術教育系(美術)、保健体育教育系(保健体育)、生活科学教育系(家庭)、技術教育系(技術)で構成されている。
◆特別支援教育コースでは、小学校教員に必要な学習に加えて、障害のある子どもたちの教育の基礎を学ぶ。
養護教諭養成課程は、子どもたちの心身の健康を保持・増進し、教育の支援を行う養護教諭の養成を目指す。医学・看護学に関する科目と教育・保健に関する科目を学ぶ。
△新入生の男女比率(2023年) 男31%・女69%
◆教育実践科学コースでは、今日の教育現場で求められている実践的指導力を身につけた教員の養成を行う。学校教育の特性と問題点を理解し、児童・生徒の支援と学習指導について学ぶ。
◆教科教育コースは、言語・社会教育系(国語・社会・英語)、理数教育系(数学・理科)、音楽教育系(音楽)、美術教育系(美術)、保健体育教育系(保健体育)、生活科学教育系(家庭)、技術教育系(技術)で構成されている。
◆特別支援教育コースでは、小学校教員に必要な学習に加えて、障害のある子どもたちの教育の基礎を学ぶ。
養護教諭養成課程は、子どもたちの心身の健康を保持・増進し、教育の支援を行う養護教諭の養成を目指す。医学・看護学に関する科目と教育・保健に関する科目を学ぶ。
△新入生の男女比率(2023年) 男31%・女69%
歴史
設置 1949、改組 1967
学科定員
理学205
学部内容
以下の6コースを設置している。
◆数学・情報数理コースには、代数学、幾何学、解析学を柱とする数学を深く学ぶ「数学プログラム」と、情報数理の論理とコンピュータ科学・データ科学の手法を学ぶ「情報数理プログラム」がある。
◆物理学コースでは、素粒子物理学(理論・実験)・物性物理学(理論・実験)・宇宙物理学(理論・観測)の領域を対象とする。現代物理学の専門知識と方法を修得し、物事を論理的・体系的に把握し、さまざまな課題について、実験や演習、ゼミなどを通じて取り組んでいく。
◆化学コースでは、現代化学の基礎となっている有機化学、無機化学、生化学、分析化学、物理化学を、講義・演習・実験が一体となった学修法で学ぶ。
◆生物科学コースでは、基礎生命科学・多様性生物学の両分野の学習により、生命現象の根底にある遺伝情報の発現と制御、発生の仕組み、細胞の多様な能力、生物の進化、生物と環境との関わりなどについての理解と、生物学上の未解決の問題を解明するための基礎能力を身につけることを目指す。
◆地球環境科学コースの「地球惑星科学プログラム」では、地球環境問題や、地球における多様な自然現象についての専門知識を身につける。「地球科学技術者養成プログラム」では、環境保全や自然の持続的開発・防災といった地球科学分野の専門技術者を養成するための教育を行う。同プログラム修了者には技術士補相当の資格が与えられる。
◆総合理学コース(2025年学際理学コースから名称変更予定)では、1年次に理学の基礎を学んでから2年進級時に物理学、化学、生物科学、地球環境科学のうち、さらに深めたい1つの専門分野を選択し、対応するコースと同じ専門科目群を履修して卒業する。大学での新たな専門分野との出会いを大切にしながら、熟慮して自身の専門分野を決定することにより、多様な視点から深く考え、科学の諸課題に取り組める人材の育成を目指す。
△新入生の男女比率(2023年) 男71%・女29%
◆数学・情報数理コースには、代数学、幾何学、解析学を柱とする数学を深く学ぶ「数学プログラム」と、情報数理の論理とコンピュータ科学・データ科学の手法を学ぶ「情報数理プログラム」がある。
◆物理学コースでは、素粒子物理学(理論・実験)・物性物理学(理論・実験)・宇宙物理学(理論・観測)の領域を対象とする。現代物理学の専門知識と方法を修得し、物事を論理的・体系的に把握し、さまざまな課題について、実験や演習、ゼミなどを通じて取り組んでいく。
◆化学コースでは、現代化学の基礎となっている有機化学、無機化学、生化学、分析化学、物理化学を、講義・演習・実験が一体となった学修法で学ぶ。
◆生物科学コースでは、基礎生命科学・多様性生物学の両分野の学習により、生命現象の根底にある遺伝情報の発現と制御、発生の仕組み、細胞の多様な能力、生物の進化、生物と環境との関わりなどについての理解と、生物学上の未解決の問題を解明するための基礎能力を身につけることを目指す。
◆地球環境科学コースの「地球惑星科学プログラム」では、地球環境問題や、地球における多様な自然現象についての専門知識を身につける。「地球科学技術者養成プログラム」では、環境保全や自然の持続的開発・防災といった地球科学分野の専門技術者を養成するための教育を行う。同プログラム修了者には技術士補相当の資格が与えられる。
◆総合理学コース(2025年学際理学コースから名称変更予定)では、1年次に理学の基礎を学んでから2年進級時に物理学、化学、生物科学、地球環境科学のうち、さらに深めたい1つの専門分野を選択し、対応するコースと同じ専門科目群を履修して卒業する。大学での新たな専門分野との出会いを大切にしながら、熟慮して自身の専門分野を決定することにより、多様な視点から深く考え、科学の諸課題に取り組める人材の育成を目指す。
△新入生の男女比率(2023年) 男71%・女29%
歴史
設置 1949
学科定員
計515 機械システム工130、電気電子システム工125、物質科学工110、情報工90、都市システム工60
*情報工の定員は2025年
学部内容
機械システム工学科では、多様な問題の解決に意欲的に取り組むことができ、持続可能な循環型社会を見据えた「ものづくり」を担えるエンジニアの養成を目指す。演習形式の授業で応用力を身につけ、実験・実習を通して物理的感覚とコンピュータとメカ技術の融合分野の知識を養う。
電気電子システム工学科では、IoT(モノのインターネット)など、電気電子工学と情報通信工学を融合した分野に対応できる技術者を養成する。また、電気エネルギー、電気・電子機器、通信システムなど、広い範囲の知識を提供し、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせて扱う能力を育む。学生は3年次からエネルギーシステムプログラムとエレクトロニクスシステムプログラムに分かれる。
物質科学工学科では、金属、有機・無機物質、高分子、生体物質、生体材料など多岐にわたる物質の構造と機能を原子・分子レベルで理解し、新しい物質や材料の設計・製造およびハイブリッド化への応用を図ることができる研究者・技術者の育成を目指す。3年次からは、材料工学プログラム、応用化学プログラム、生命工学プログラムのいずれかを選択し、他プログラム科目も横断的に学ぶことで、多様な物質に対応可能な素養を身につける。
情報工学科では、コンピュータとネットワークの未来社会を創造し革新するため、さまざまな分野のソフトウェア技術を学ぶ。情報社会のあらゆる分野で活躍し貢献できることを目標に、国際的標準カリキュラムに基づいたコンピュータサイエンスの講義・演習・実験・卒業研究を通して、学問的基礎や技術を中心に、進化し続ける情報工学の最先端を切り開くための考え方や、論理的に思考し表現できる能力などを身につける。
都市システム工学科では、「安全の創造」に向けて、地震などの自然災害に対する防災や、強くてしなやかな土木・建築技術を学ぶ。また、「環境の創造」に向けて、地球温暖化や水質汚染などの現象と対応策を学ぶ。さらに「快適の創造」に向けて、建築・都市計画などを学ぶ。そして、これら3つの要素を総合的にシステム化することを学ぶ。2年次から社会基盤デザインプログラムと建築デザインプログラムに分かれる。
△新入生の男女比率(2023年) 男84%・女16%
電気電子システム工学科では、IoT(モノのインターネット)など、電気電子工学と情報通信工学を融合した分野に対応できる技術者を養成する。また、電気エネルギー、電気・電子機器、通信システムなど、広い範囲の知識を提供し、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせて扱う能力を育む。学生は3年次からエネルギーシステムプログラムとエレクトロニクスシステムプログラムに分かれる。
物質科学工学科では、金属、有機・無機物質、高分子、生体物質、生体材料など多岐にわたる物質の構造と機能を原子・分子レベルで理解し、新しい物質や材料の設計・製造およびハイブリッド化への応用を図ることができる研究者・技術者の育成を目指す。3年次からは、材料工学プログラム、応用化学プログラム、生命工学プログラムのいずれかを選択し、他プログラム科目も横断的に学ぶことで、多様な物質に対応可能な素養を身につける。
情報工学科では、コンピュータとネットワークの未来社会を創造し革新するため、さまざまな分野のソフトウェア技術を学ぶ。情報社会のあらゆる分野で活躍し貢献できることを目標に、国際的標準カリキュラムに基づいたコンピュータサイエンスの講義・演習・実験・卒業研究を通して、学問的基礎や技術を中心に、進化し続ける情報工学の最先端を切り開くための考え方や、論理的に思考し表現できる能力などを身につける。
都市システム工学科では、「安全の創造」に向けて、地震などの自然災害に対する防災や、強くてしなやかな土木・建築技術を学ぶ。また、「環境の創造」に向けて、地球温暖化や水質汚染などの現象と対応策を学ぶ。さらに「快適の創造」に向けて、建築・都市計画などを学ぶ。そして、これら3つの要素を総合的にシステム化することを学ぶ。2年次から社会基盤デザインプログラムと建築デザインプログラムに分かれる。
△新入生の男女比率(2023年) 男84%・女16%
歴史
設置 1952
学科定員
計160 食生命科学80、地域総合農80
学部内容
地域から世界の「食と農」に貢献する生産・研究開発・流通の専門家を育成する。
食生命科学科では、「1次産業から3次産業までをつなぐ教育・研究」をテーマに、生命科学や食品の加工、流通、安全性に関する知識・技能を修得。生物機能の高度利用や安全な食料・食品の生産、供給を通じて、さまざまな食料問題を解決するための能力や、食品分野で国際的に活躍できる思考力を身につける。
地域総合農学科では、「1次産業から3次産業の循環を総合的に理解する教育・研究」をテーマに、地域の食や農に関する生産から販売までの一貫した知識・技能、地域社会の抱える課題を包括的に把握し、創生・発展につながる思考力・行動力を養い、地域産業振興に貢献する力を総合的に身につける。応用植物科学と地域共生の2コース制。
△新入生の男女比率(2023年) 男47%・女53%
食生命科学科では、「1次産業から3次産業までをつなぐ教育・研究」をテーマに、生命科学や食品の加工、流通、安全性に関する知識・技能を修得。生物機能の高度利用や安全な食料・食品の生産、供給を通じて、さまざまな食料問題を解決するための能力や、食品分野で国際的に活躍できる思考力を身につける。
地域総合農学科では、「1次産業から3次産業の循環を総合的に理解する教育・研究」をテーマに、地域の食や農に関する生産から販売までの一貫した知識・技能、地域社会の抱える課題を包括的に把握し、創生・発展につながる思考力・行動力を養い、地域産業振興に貢献する力を総合的に身につける。応用植物科学と地域共生の2コース制。
△新入生の男女比率(2023年) 男47%・女53%
歴史
設置 2024
学科定員
学科組織なし40
学部内容
2024年学環新設。ビジネスとデータサイエンスを中心とした分野・文理横断型の学びから、地域課題の解決や、新たな価値創出に挑戦する実践的な人材を養成する。
そのため、全ての学生が「ビジネス(経済・経営)」と「データサイエンス」を学び、さらに2年次には、ビジネス(経済・経営)をより深く学ぶための「地域ビジネスデザインプログラム」か、データサイエンスをより深く学ぶための「地域創生データサイエンスプログラム」を選択し、専門性を高める。
また、他大学ではほとんど例のない「コーオプ実習」と呼ばれる新しい実習を特徴とする。この実習では、1か月以上にわたり、茨城県内の企業や自治体で実際に働くなかで、大学で学んだ知識・能力を応用し、高い実践力を身につける。実習内容は大学と実習先が協働して設計する。授業としての単位が付与されるだけでなく、実習先の社員・職員として業務に従事し、給与も支給される。
カリキュラムには、分野・文理を横断した幅広い「課題探究科目」を設置。学生自身が探究する課題や進路を見据えて、自ら選択履修することができる。
そのため、全ての学生が「ビジネス(経済・経営)」と「データサイエンス」を学び、さらに2年次には、ビジネス(経済・経営)をより深く学ぶための「地域ビジネスデザインプログラム」か、データサイエンスをより深く学ぶための「地域創生データサイエンスプログラム」を選択し、専門性を高める。
また、他大学ではほとんど例のない「コーオプ実習」と呼ばれる新しい実習を特徴とする。この実習では、1か月以上にわたり、茨城県内の企業や自治体で実際に働くなかで、大学で学んだ知識・能力を応用し、高い実践力を身につける。実習内容は大学と実習先が協働して設計する。授業としての単位が付与されるだけでなく、実習先の社員・職員として業務に従事し、給与も支給される。
カリキュラムには、分野・文理を横断した幅広い「課題探究科目」を設置。学生自身が探究する課題や進路を見据えて、自ら選択履修することができる。
他の大学の情報も確認しよう
茨城大学 の
過去問
茨城大学 の
資料請求
- 入学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。