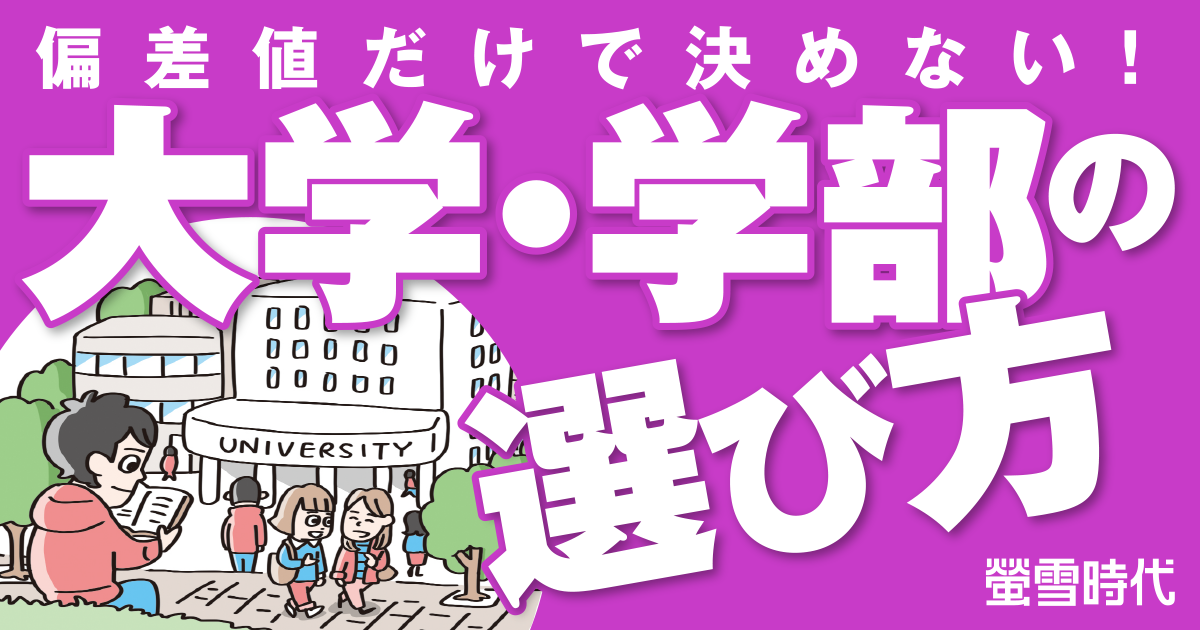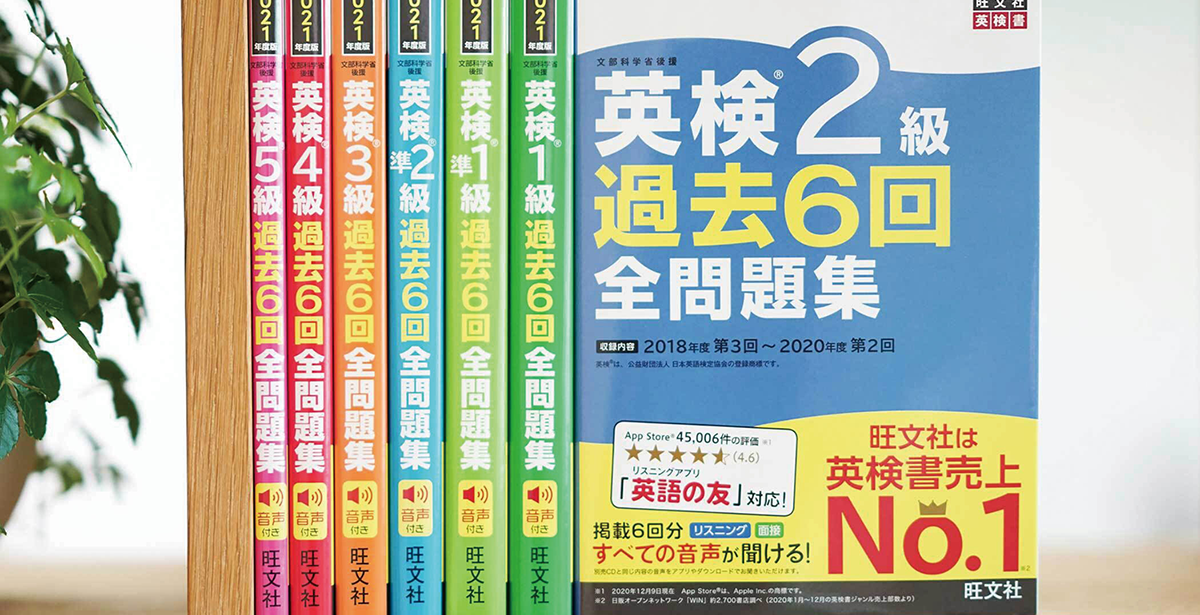学部で絞り込む
歴史
設置 1949、改組 2016
学科定員
学校教育課程120→110(申請中)
学部内容
人間の生涯発達を視野におさめ、教育に対する情熱と課題を解決する高い実践力を備え、豊かな人間生活の構築に寄与する教育人の養成を目指す。
卒業要件として小学校教諭免許の取得を基礎にして、中学・高等学校教諭免許(あるいは幼稚園教諭・特別支援学校教諭免許)を取得し、幼・小・中・高全般を見通した指導力を持つ、現代的ニーズに応える質の高い教員を養成。
基幹となる教職科目を少人数グループワーク型授業とし、それを軸に教員養成カリキュラムの体系化・構造化を図る。また、学生が主体的に教職へのキャリアを積み重ねていけるよう、教育支援室の専任教員などによる進路に関する個人面談、教員採用試験に向けた各種の対策講座や個別指導を実施し、教員就職を手厚くサポートしている。さらに、実践的教師力の深化の場として、教育ボランティアや地域学習アシストの各活動を行い、子どもへの理解を深める機会をつくっている。
そのほか、外国籍児童に対する日本語指導・支援に対応した「日本語教員養成プログラム」も実施している。
△新入生の男女比率(2024年) 男41%・女59%
卒業要件として小学校教諭免許の取得を基礎にして、中学・高等学校教諭免許(あるいは幼稚園教諭・特別支援学校教諭免許)を取得し、幼・小・中・高全般を見通した指導力を持つ、現代的ニーズに応える質の高い教員を養成。
基幹となる教職科目を少人数グループワーク型授業とし、それを軸に教員養成カリキュラムの体系化・構造化を図る。また、学生が主体的に教職へのキャリアを積み重ねていけるよう、教育支援室の専任教員などによる進路に関する個人面談、教員採用試験に向けた各種の対策講座や個別指導を実施し、教員就職を手厚くサポートしている。さらに、実践的教師力の深化の場として、教育ボランティアや地域学習アシストの各活動を行い、子どもへの理解を深める機会をつくっている。
そのほか、外国籍児童に対する日本語指導・支援に対応した「日本語教員養成プログラム」も実施している。
△新入生の男女比率(2024年) 男41%・女59%
歴史
設置 1980、受入 2002
学科定員
計185 医学125、看護60
学部内容
医学科では、卒業後に臨床医・研究医として広く活躍し社会貢献できるよう、基礎から専門的な内容へ順を追って学ぶことができるカリキュラム編成となっている。これらには現代の医療・医学において求められるデータサイエンス、生命科学、行動科学、感染制御学、地域医療学、医学英語、プロフェッショナリズムなども含まれる。3・4年次には複数の診療科が連携して担当する「統合臨床医学」の授業とグループ学習があり、公的資格「臨床実習生(医学)」を取得後、4~6年次に附属病院や学外の病院で行う診療参加型の臨床実習がある。臨床実習以外にも「早期臨床体験実習(ECE)」(1年次)、「救急用自動車同乗実習」(3年次)、「社会医学実習」(6年次)など、学外に出て学修する機会が組まれている。また、医学研究に興味を持つ学生のために「ライフサイエンスコース」を設置している。
看護学科では、グローバルな視点を持って看護学分野の継続的発展を支え、地域社会に貢献できる、質の高い看護職者の育成を目指している。看護学講座の大講座のなかに、基礎看護学、成人看護学、高齢者看護学、母性看護学、小児看護学、精神看護学、在宅看護論、公衆衛生看護学、人間科学、保健学の領域を設け、研究や高度実践の経験を有する専門家による講義や実習を行っている。1年次には豊かな人間性を育み、看護の基礎的な能力を養う。2年次には看護専門領域を学び、3年次には領域別実習、4年次には地域包括・移行期ケア実習や看護研究を実施。これらを通して、将来の活躍に生かせる基礎知識と技術を体系的に学ぶことができるカリキュラムとなっている。
なお、2024年看護師国家試験合格率(新卒)は100.0%、2024年保健師国家試験合格率(新卒)は98.1%、2024年助産師国家試験合格率(新卒)は100.0%となっている。
△新入生の男女比率(2024年) 男48%・女52%
△2024年医師国家試験合格率(新卒) 97.3%
看護学科では、グローバルな視点を持って看護学分野の継続的発展を支え、地域社会に貢献できる、質の高い看護職者の育成を目指している。看護学講座の大講座のなかに、基礎看護学、成人看護学、高齢者看護学、母性看護学、小児看護学、精神看護学、在宅看護論、公衆衛生看護学、人間科学、保健学の領域を設け、研究や高度実践の経験を有する専門家による講義や実習を行っている。1年次には豊かな人間性を育み、看護の基礎的な能力を養う。2年次には看護専門領域を学び、3年次には領域別実習、4年次には地域包括・移行期ケア実習や看護研究を実施。これらを通して、将来の活躍に生かせる基礎知識と技術を体系的に学ぶことができるカリキュラムとなっている。
なお、2024年看護師国家試験合格率(新卒)は100.0%、2024年保健師国家試験合格率(新卒)は98.1%、2024年助産師国家試験合格率(新卒)は100.0%となっている。
△新入生の男女比率(2024年) 男48%・女52%
△2024年医師国家試験合格率(新卒) 97.3%
歴史
設置 1949
学科定員
工学365<クリーンエネルギー化学33、応用化学33、土木環境工学46、コンピュータ理工学75、機械工学48、メカトロニクス45、電気電子工学45、総合工学枠40>
学部内容
2024年学科改組。
2024年に設立100周年を迎え、工学部では従来の7学科を工学科1学科に再編。さらに、新たに7つのコースを設置。クリーンエネルギー化学コース、入学後にコース選択する総合工学クラス、入学試験での女子枠など、幅広いニーズに対応している。「未来世代を思いやるエンジニアリング教育」をキャッチフレーズに掲げ、確かな基礎力とエンジニアとしての総合力(エンジニアリング能力)の育成をカリキュラムの柱に据えている。このため、基礎工学、応用工学とともに、数学・物理学・化学といった工学の基礎となる自然科学にも配慮したカリキュラムを整備している。また、所属コース以外の科目も履修可能であり、自主的な選択を通じて多様な学びを促進している。
学びの特色として、少人数教育、反転授業、自主的な学びスペースの用意などがある。まず、少人数教育については、たとえば卒業研究では教員1名に対して学生3・4名できめ細かな指導が行われている。また反転授業では、教員の作成したオンライン教材を事前に繰り返し聴講し、授業時間内では主としてグループによる演習を行うことによって、学生の学習効果を高めている。このほか、自主的な学びの環境としてフィロス(共創学習支援室)という学習スペースが設置されている。ここでは、学生が学年や学科の壁を越えて気軽に集まり、グループや個人で学習交流を行うことができ、特に専門教員による数学や物理に関するサポートを受けられるようになっている。
◆クリーンエネルギー化学コースでは、無機化学・有機化学・物理化学に関する授業と実験で化学の基礎を身につけ、専門性の高い授業、演習、実験によりエネルギー変換・貯蔵・創製について学ぶ。
◆応用化学コースでは、安全で快適な持続可能社会の実現を目指して、新素材・高機能物質、エネルギー、環境問題に関する基礎知識と応用技術を学ぶ。
◆土木環境工学コースでは、環境と調和した災害に強い快適な社会を実現することを目的として、社会基盤を整備・管理するための知識と技術を学ぶ。
◆コンピュータ理工学コースでは、ソフト・ハードウェアの基礎技術から、人工知能・機械学習・CG・ソフトウェア工学・コンピュータネットワーク・感性情報工学などの応用技術までを学ぶ。
◆機械工学コースでは、基礎知識に加え、自動車、航空宇宙、バイオメカニクス、ロボット、動力エネルギーシステムなどに関する応用知識を習得する。
◆メカトロニクスコースでは、複数の学問領域(機械・電気・情報)にまたがる統合システム(ロボットなど)の構築技術について、基礎から広く学ぶ。
◆電気電子工学コースでは、半導体・太陽光発電・無線電力伝送・大規模集積回路・ホログラフィ・高速光通信システムなど、未来を大きく変える力を持った電気電子工学技術を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男88%・女12%
2024年に設立100周年を迎え、工学部では従来の7学科を工学科1学科に再編。さらに、新たに7つのコースを設置。クリーンエネルギー化学コース、入学後にコース選択する総合工学クラス、入学試験での女子枠など、幅広いニーズに対応している。「未来世代を思いやるエンジニアリング教育」をキャッチフレーズに掲げ、確かな基礎力とエンジニアとしての総合力(エンジニアリング能力)の育成をカリキュラムの柱に据えている。このため、基礎工学、応用工学とともに、数学・物理学・化学といった工学の基礎となる自然科学にも配慮したカリキュラムを整備している。また、所属コース以外の科目も履修可能であり、自主的な選択を通じて多様な学びを促進している。
学びの特色として、少人数教育、反転授業、自主的な学びスペースの用意などがある。まず、少人数教育については、たとえば卒業研究では教員1名に対して学生3・4名できめ細かな指導が行われている。また反転授業では、教員の作成したオンライン教材を事前に繰り返し聴講し、授業時間内では主としてグループによる演習を行うことによって、学生の学習効果を高めている。このほか、自主的な学びの環境としてフィロス(共創学習支援室)という学習スペースが設置されている。ここでは、学生が学年や学科の壁を越えて気軽に集まり、グループや個人で学習交流を行うことができ、特に専門教員による数学や物理に関するサポートを受けられるようになっている。
◆クリーンエネルギー化学コースでは、無機化学・有機化学・物理化学に関する授業と実験で化学の基礎を身につけ、専門性の高い授業、演習、実験によりエネルギー変換・貯蔵・創製について学ぶ。
◆応用化学コースでは、安全で快適な持続可能社会の実現を目指して、新素材・高機能物質、エネルギー、環境問題に関する基礎知識と応用技術を学ぶ。
◆土木環境工学コースでは、環境と調和した災害に強い快適な社会を実現することを目的として、社会基盤を整備・管理するための知識と技術を学ぶ。
◆コンピュータ理工学コースでは、ソフト・ハードウェアの基礎技術から、人工知能・機械学習・CG・ソフトウェア工学・コンピュータネットワーク・感性情報工学などの応用技術までを学ぶ。
◆機械工学コースでは、基礎知識に加え、自動車、航空宇宙、バイオメカニクス、ロボット、動力エネルギーシステムなどに関する応用知識を習得する。
◆メカトロニクスコースでは、複数の学問領域(機械・電気・情報)にまたがる統合システム(ロボットなど)の構築技術について、基礎から広く学ぶ。
◆電気電子工学コースでは、半導体・太陽光発電・無線電力伝送・大規模集積回路・ホログラフィ・高速光通信システムなど、未来を大きく変える力を持った電気電子工学技術を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男88%・女12%
歴史
設置 2012
学科定員
計155→165(申請中) 生命工、地域食物科学、環境科学、地域社会システム
学部内容
「持続的な食料の生産と供給による地域社会の繁栄を実現するために必要となる、生命科学、食物生産・加工、環境・エネルギー、地域経済・企業経営・行政に関し、広い視野を持つ人材を、自然と社会の共生科学に基づき養成する」ことを基本理念とする。
自然と社会の共生科学の視点から、生命・食・環境・経営を中心とする新しい農学分野における応用力を身につけるため、基礎を重視している。また学科間の垣根を低くしており、学科横断的な教育体制を構築する。
生命工学科では、分子生物学、生化学、細胞生理学といった生命科学の基礎を身につける。さらに発生工学や幹細胞生物学、応用微生物学、バイオインフォマティクスなどをはじめとする最先端の生命科学・生命工学を学ぶことで、再生医療(ES細胞、クローン技術)、生殖補助医療(体外受精、発生工学)、食料生産・食品衛生(機能性食品、醸造、発酵工業)、健康増進(医薬品、有用微生物、化粧品、香料)、バイオエネルギー、環境保全などに関する新しい技術を創出する能力を身につける。このほか、「バイオ・メディカルデータサイエンス特別コース」では、生命科学・医学・薬学分野における数理・データサイエンス教育を展開。
地域食物科学科では、食物(食品製造、食品栄養、園芸)およびワイン製造に関する知識・技術(微生物、機能成分、果実遺伝子)を学ぶ。バイオテクノロジーを駆使した果樹や野菜などの農産物の栽培、食品製造の科学的理解、栄養・有用成分の解析と利用、ワイン製造技術などを課題に、食物生産から食品製造までのプロセスを包括的に学ぶ。このほか、地域性に富む「ワイン科学特別コース」を設置している。
環境科学科では、環境問題の背景と概要に関する「基礎知識」や、大気・水・土壌・生物と人間との関わりに関する「専門知識」、人間活動の影響を評価するための「環境計測技術」や、環境管理・修復に不可欠な「環境保全技術」を学び、自然科学の知識と技法に基づく問題解決能力を培う。さらに、主体的に考える力と他者との対話や合意形成のための素養を身につけ、環境に関わる学問的課題や社会的課題を自ら見出し、多様な人びとと協働しながら課題解決に取り組める人材を養成する。
地域社会システム学科では、社会経営 (経済運営、企業経営、行政運営)に関わる理論と実践をバランスよく学ぶことで、地域社会や職場で多様な人びとと仕事をしていくために必要な基礎的な力を養い、国際的な視座と地域密着の姿勢を両立させながら社会のマネジメントを担う能力を持つ人材を養成。
また、「観光政策科学特別コース」を設置し、観光関連分野の専門知識を有し、観光経営や観光政策の立案ができる人材を育成。
△新入生の男女比率(2024年) 男50%・女50%
自然と社会の共生科学の視点から、生命・食・環境・経営を中心とする新しい農学分野における応用力を身につけるため、基礎を重視している。また学科間の垣根を低くしており、学科横断的な教育体制を構築する。
生命工学科では、分子生物学、生化学、細胞生理学といった生命科学の基礎を身につける。さらに発生工学や幹細胞生物学、応用微生物学、バイオインフォマティクスなどをはじめとする最先端の生命科学・生命工学を学ぶことで、再生医療(ES細胞、クローン技術)、生殖補助医療(体外受精、発生工学)、食料生産・食品衛生(機能性食品、醸造、発酵工業)、健康増進(医薬品、有用微生物、化粧品、香料)、バイオエネルギー、環境保全などに関する新しい技術を創出する能力を身につける。このほか、「バイオ・メディカルデータサイエンス特別コース」では、生命科学・医学・薬学分野における数理・データサイエンス教育を展開。
地域食物科学科では、食物(食品製造、食品栄養、園芸)およびワイン製造に関する知識・技術(微生物、機能成分、果実遺伝子)を学ぶ。バイオテクノロジーを駆使した果樹や野菜などの農産物の栽培、食品製造の科学的理解、栄養・有用成分の解析と利用、ワイン製造技術などを課題に、食物生産から食品製造までのプロセスを包括的に学ぶ。このほか、地域性に富む「ワイン科学特別コース」を設置している。
環境科学科では、環境問題の背景と概要に関する「基礎知識」や、大気・水・土壌・生物と人間との関わりに関する「専門知識」、人間活動の影響を評価するための「環境計測技術」や、環境管理・修復に不可欠な「環境保全技術」を学び、自然科学の知識と技法に基づく問題解決能力を培う。さらに、主体的に考える力と他者との対話や合意形成のための素養を身につけ、環境に関わる学問的課題や社会的課題を自ら見出し、多様な人びとと協働しながら課題解決に取り組める人材を養成する。
地域社会システム学科では、社会経営 (経済運営、企業経営、行政運営)に関わる理論と実践をバランスよく学ぶことで、地域社会や職場で多様な人びとと仕事をしていくために必要な基礎的な力を養い、国際的な視座と地域密着の姿勢を両立させながら社会のマネジメントを担う能力を持つ人材を養成。
また、「観光政策科学特別コース」を設置し、観光関連分野の専門知識を有し、観光経営や観光政策の立案ができる人材を育成。
△新入生の男女比率(2024年) 男50%・女50%
他の大学の情報も確認しよう
山梨大学 の
過去問
山梨大学 の
資料請求
- 大学案内(2026年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。