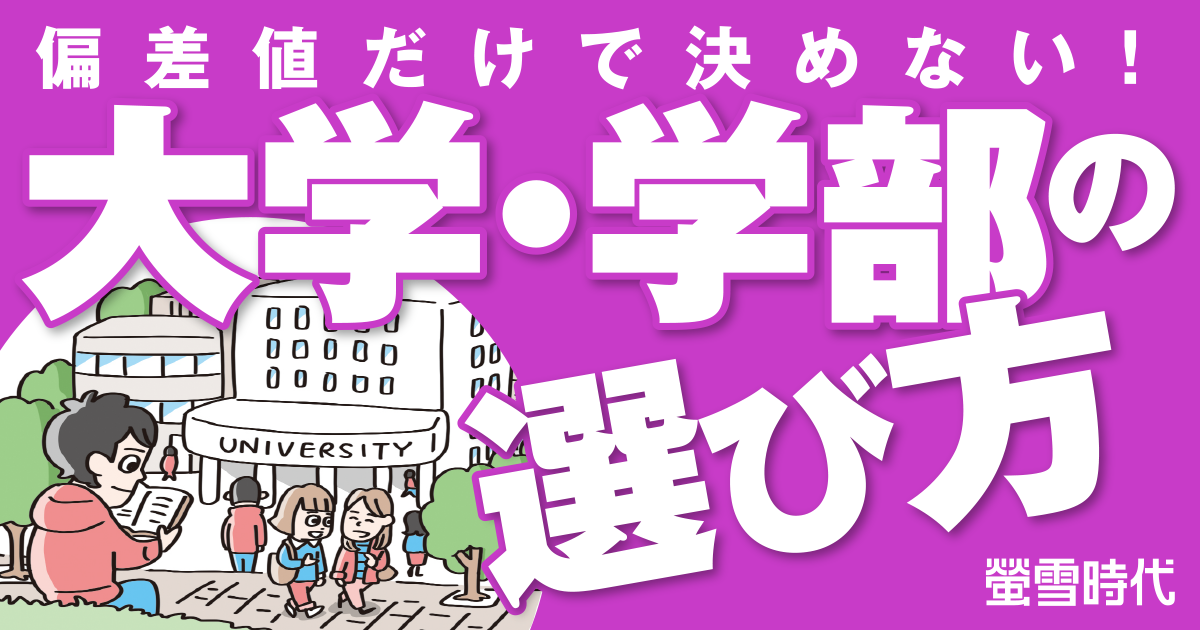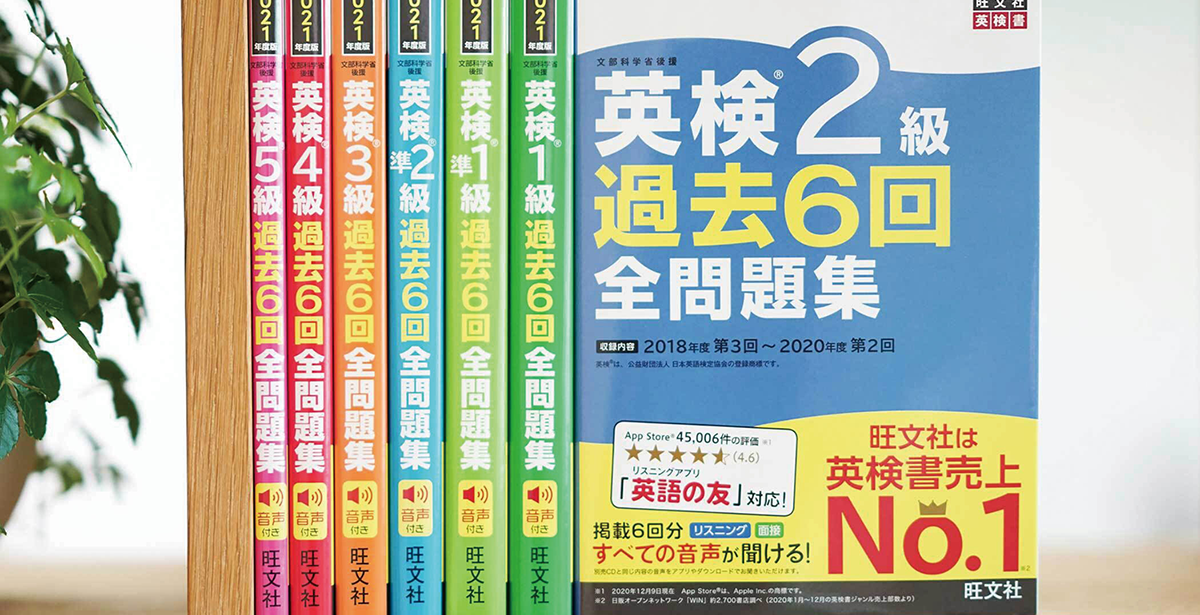神学50
1~2年次では、旧約聖書、新約聖書を中心にキリスト教の歴史と倫理、哲学との関係について学ぶ。2年次からは専門分野が、キリスト教教義学、教会史、司牧神学などを学ぶ神学系、いのちの倫理と社会倫理を学ぶキリスト教倫理系、キリスト教の思想や芸術、聖書を学ぶキリスト教文化系の3系列に分かれ、将来を見据えた集中的な科目履修を行う。
3年次では、卒業論文を書くためのゼミに参加し、4年次で各自の課題を卒業論文としてまとめる。
△新入生の男女比率(2024年) 男24%・女76%
計510 哲学60、史学70、国文60、英文100、ドイツ文50、フランス文50、新聞120
史学科では、専門は大きく「アジア・日本史系」と「ヨーロッパ・アメリカ史系」の2分野に分かれ、さらに古代・中世・近世・近現代に細分化される。1年次には基本的な歴史研究方法を学び、2年次から徐々に分野・時代別の専門を学ぶ。
国文学科では、4年次の卒業論文に至るまで、「国文学」「国語学」「漢文学」の3分野を有機的に連関させながら、自ら研究テーマを見つけ、検討・分析・追究を行い、新たな発想に立つ問題解決能力を培う。
英文学科では、コース別(English Studies、American Studies、Languages Studies)による体系的なカリキュラムを導入している。異文化交渉での諸問題を深い知性を用いて対処するため、専門的知識の学びとスキルの積み上げに重点を置いている。
ドイツ文学科では、1・2年次にドイツ語能力を身につけ、ドイツ文化の基礎的な知識・考え方を学ぶ。3・4年次はドイツ語圏の文学、芸術、言語を体系的・多面的に学び、柔軟かつ鋭敏な洞察力、高度な言語表現・文化発信力を身につける。
フランス文学科では、フランス的精神の根本にある複眼的思考、異質なものへの寛容さ、批判を尊ぶ精神に触れることを目指す。
1・2年次はフランス語と文学研究の基礎を養い、3・4年次で履修する専門分野は「フランス文学研究」「フランス語学研究」「フランス文化研究」の3系列から学ぶ。
新聞学科では、1年次からコミュニケーション論、演習(新聞/放送)などの基本科目を履修する。2年次以降は、メディア・コミュニケーション、ジャーナリズム、情報社会についてより専門的に学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男26%・女74%
計305 教育60、心理55、社会60、社会福祉60、看護70
教育学の研究分野は広範囲に及び、学校教育だけでなく、家庭、地域社会、都市、教育産業、企業、マスコミ、異文化教育、国際教育、宗教教育などが研究対象となる。
心理学科では、実験心理学と臨床心理学の領域があり、どちらも学べるようになっている。
1年次には、心理学基礎論や心理学研究法などを学ぶ。演習では心理学の英語原書を読む。2年次には、深層心理学や認知心理学など、数多くの心理学の講義が編成されている。演習では、心理学と社会の関わりを学ぶ。3年次では、各教員のゼミに所属し、研究を深め、4年次に自分の定めた研究テーマに沿ってデータを収集、分析して卒業研究にまとめる。
社会学科では、社会と人間の相互関係の視点を基本に、ミクロからマクロまでの多くの社会集団や社会制度を研究する。理論的・実証的な知見から、現実社会への応用力の育成も行う。
1・2年次から社会学の基礎を、ゼミ形式で学ぶと同時に2年次で多様な社会学の専攻科目を学び、3・4年次では各自の関心に沿って個別の分野を少人数のゼミ形式で学ぶ。
社会福祉学科では、社会福祉の経営・運営管理・政策分野を重点的に学び、研究する福祉政策運用管理系と福祉臨床系の2つの科目群を設けている。
社会福祉臨床の実践を担う高度専門職業人や政策立案・運営管理の専門家、さらに社会福祉に関する研究者・教育者など、福祉社会の実現に多角的に貢献する人材を育成する。
看護学科では、特定の専門に偏ることなく、科学、臨床、政策・運営、それぞれの分野の知識を幅広く学び、看護教育と教養教育の両立を実現する。
1年次に学部共通科目などから教養と看護学の基礎を学び、2年次から専門基礎を本格的に学ぶ。
3年次から看護実践能力を養う実習が中心となり、4年間かけて総合的教養教育と職業専門教育を融合した看護教育を展開する。
△新入生の男女比率(2024年) 男11%・女89%
計330 法律160、国際関係法100、地球環境法70
1年次は、「法学入門」「導入演習」を手はじめに、基本的人権を中心に学ぶ「憲法」と市民の日常の生活関係を規律する「民法」など、法律学の基礎を学習する。
2年次は統治機構を学ぶ「憲法」や「債権法」「刑法」などを必修とするほか、将来を見据えた履修モデル案に沿って学ぶことができる。
国際関係法学科では、国際社会における諸問題に対処する能力を身につけるため、国際法や国際私法を中心とした国際関係に関する法科目を学ぶ。また、英語で学ぶ多数の専門科目を開講し、英語能力を高め国際的な交流に貢献するための科目配置をしている。
地球環境法学科では、環境問題に関する世界と日本の法システムに関する素養と法的思考力を身につけることを目指す。
憲法、民法、刑法などの法学部本来の諸科目を踏まえ、環境法総論、環境訴訟法、自治体環境法、国際環境法、企業環境法など、環境法関連の科目を多数設けている。
△新入生の男女比率(2024年) 男34%・女66%
計330 経済165、経営165
経済学科では、1・2年次の基礎科目(必須科目)からはじまり、2年次以降に基本科目(選択必修科目)や専門科目(選択科目)と順に積み上げていくことにより、経済学を効率よく体系的に学べる。
選択科目では経営/法律系科目を学ぶことで、視野を広げることもできる。3・4年次は演習(ゼミ)を通じて、現実の多様な社会・経済現象の背後に潜む本質を理解するために、経済学を応用する力を養う。
経営学科では、1年次では「経営学概論」で経営学の学習方法(問題発見、文献・情報・データの収集、分析、発表方法など)を修得し、2年次からの専門講義科目で段階的に専門的知識を学ぶ。3年次からは講義や演習で専門知識を深く学習する。特に「演習(ゼミナール)」での体系的な専門知識の修得を重視している。
企業の経営活動に関する専門知識を体系的に学習すると同時に、経営活動を理解し、経営に関する合理的な意思決定により社会に貢献できる人材の育成を目指す。
△新入生の男女比率(2024年) 男51%・女49%
計500 英語180、ドイツ語60、フランス語70、イスパニア語70、ロシア語60、ポルトガル語60
外国語学部の学生は、2つの専攻を履修する。「第一主専攻」として、それぞれの学科の専攻語科目と言語圏の基礎科目を学ぶ。ここでは、語学の4技能(話す、聞く、読む、書く)を徹底的に学ぶとともに、その言語を使用する地域における政治、社会、思想、歴史、文化などを学ぶ。
「第二主専攻」では、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、ロシア・ユーラシア、言語、アジア、中東・アフリカ、国際政治論、市民社会・国際協力論の9つの研究コースから各人が関心あるコースを1つ選び、その研究コースに用意されている専門性の高い科目群を体系的に履修していくことで、ある地域や学問分野について系統的な学習と研究を行う。
△新入生の男女比率(2024年) 男29%・女71%
総合グローバル220
国際関係論と地域研究を専門として学ぶ。「国際政治論」か「市民社会・国際協力論」のどちらか、「アジア研究」か「中東・アフリカ研究」のどちらか(それ以外の地域の選択も可能)を選択し組み合わせることで、複合的な視座の獲得を目指す。
△新入生の男女比率(2024年) 男27%・女73%
計410 物質生命理工137、機能創造理工137、情報理工136
物質生命理工学科では、従来の物理学、化学、生物学、環境学、材料工学などの学問分野を包括的・複合的に融合し、原子から高分子、生命現象にわたる物質の基礎を理解していく。
機能創造理工学科では、伝統ある少人数教育・きめ細かい指導体制はそのままに、自然科学の基礎をしっかり身につける。その土台の上に、専門科目としての機械工学、電気・電子工学、物理学などを、選択しながら学ぶ。
情報理工学科では、計算機科学、人間情報学、電子情報学、数理情報学を基礎とし、人文・社会科学との学際的な融合を図った教育を展開。“情報”を通して人間と社会に対して深い理解を持つ、創造力豊かな人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男69%・女31%
国際教養186
また、広く世界から留学生を受け入れ、日本語・日本教育研究を行うとともに、英語を用いて世界に向けて「日本」を発信できる日本人学生の育成にも力を注ぐ。
なお、本学部は全ての授業が英語で行われ、入学時期が4月と9月となっている。
選抜は書類選考のみで、出願するためには、SAT、TOEFLの公式スコアの提出が必要。詳細は入学センターへ問合せのこと。
△新入生の男女比率(2024年) 男32%・女68%
上智大学の入試対策におすすめの参考書(by 旺文社 StudiCo)
※StudiCo(スタディコ)は、旺文社が運営する「大学受験の参考書検索サイト」です。

合格した先輩の「使い方レポート」集 ~英語・世界史・日本史編~
毎年多くの受験生が合格を目指している名門・上智大学。その入試は私立大学の中でも難関といわれています。
この記事では、上智大学に合格した先輩たちがStudiCoに投稿してくれた、参考書の「使い方レポート」を紹介します。今回は文系科目の英語、世界史・日本史の参考書をピックアップ。先輩たちがどの参考書をどのように使って勉強し、上智大学の合格を勝ち取ったのか見てみましょう!
英語の参考書
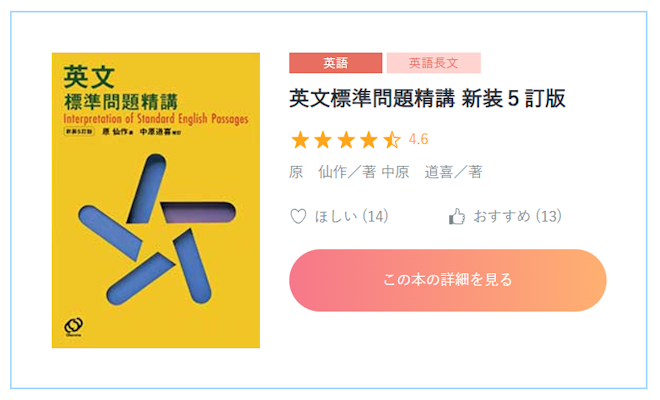
『英文標準問題精講 新装 5訂版』(旺文社) ※旺文社 StudiCoにリンク
半世紀以上にわたって受験生たちから支持されてきた英文問題集。良質な英文が程よい長さで収録されており、さまざまな設問形式も用意されているので、使い終える頃には確実に実力がついています。
<合格者の使い方レポート>
◎英文学科志望は必読!
上智の文学部(英文学科)で問われる英文は非常に長く難解なため、速さの前に、まずは正確に読み取れるようになろう!と思って使いました。
※「1ヶ月で」と書いてあるが、絶対に1ヶ月では終わらないと思う。
1問解くのにもかなり時間をかけて、
・まずは何も見ずに訳してみる
・解説を読み、1文1文を正確に訳せているかチェックする
→頭で分かっていたけど訳せていなかった部分は、自分に厳しくバツとした
・訳せていなかった部分を中心に、どの部分がどこにかかっているか、図解を参考にチェックする
・全文訳と比較して、読み取れていなかった内容をチェックする
→日本語ベースでどの部分を読み違えていたか/抜け落ちていたかチェックし、英文ベースでどの部分を読み間違えていた/読み落としていたかチェックする
・単語をチェックする
→一般的ではない方の品詞で使ってくることが非常に多いので、名詞として知っていた単語でも動詞として使っていたらしっかり覚え直す
という使い方をしていました。
使われている英文自体が有名な文学作品や演説だったりするので、日本語にした後も「なるほど」となる内容で、やりごたえがあると共に、飽きずに精読に集中することができました。
(ユーザー名:ksk020202さん 文学部合格)
使い始めた時期:高校3年生・4月
使用期間:1年以上
★〈使い方レポート〉のページはこちら (旺文社 StudiCoにリンク)
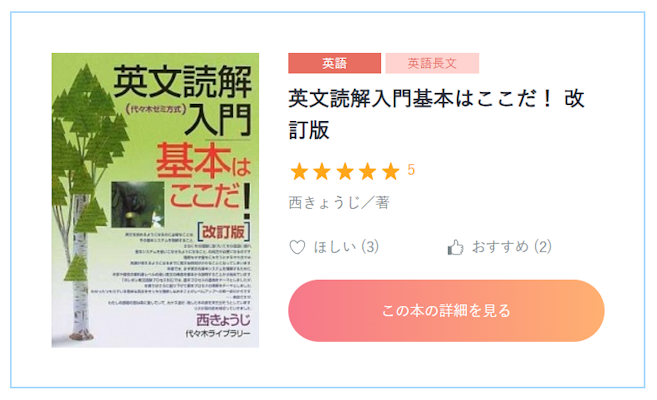
『英文読解入門基本はここだ! 改訂版』 (代々木ライブラリー) ※旺文社 StudiCoにリンク
基礎から標準レベルの読解力を鍛えることができる参考書。英文の読解に欠かせない文法や文構造をしっかりと学ぶことができます。
<合格者の使い方レポート>
◎英文読解に必要不可欠な読解力を養える。
英語を読む上で必要不可欠なことは「精読」です。もちろん、単語力・文法理解等は言わずもがなです。英語が出来ない人の特徴として「なんとなく読んでいる」という点があるように思えます。正直、なんとなくでもある程度は読めてしまうため、「精読の重要性」は見過ごされがちです。
本書は「基本的な英語の読み方」を習得することができます。講義形式で進められているため、私は読書感覚で何周も読みました。書き込みはしませんでした。他にも精読用の参考書を使っていたので本書はあくまでも「読み物」として使用していました。多くの参考書に手を出して失敗する人をよく見受けますが、まずは本書を徹底的に読み込み、分からない箇所がなくなるまでやりきりましょう。そうするとセンター模試で7割は切らなくなります。
(ユーザー名:리쿠さん 外国語学部合格)
使い始めた時期:高校3年生・4月
使用期間:1年以上
★〈使い方レポート〉のページはこちら(旺文社 StudiCoにリンク)
他の大学の情報も確認しよう
掲載情報について
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。