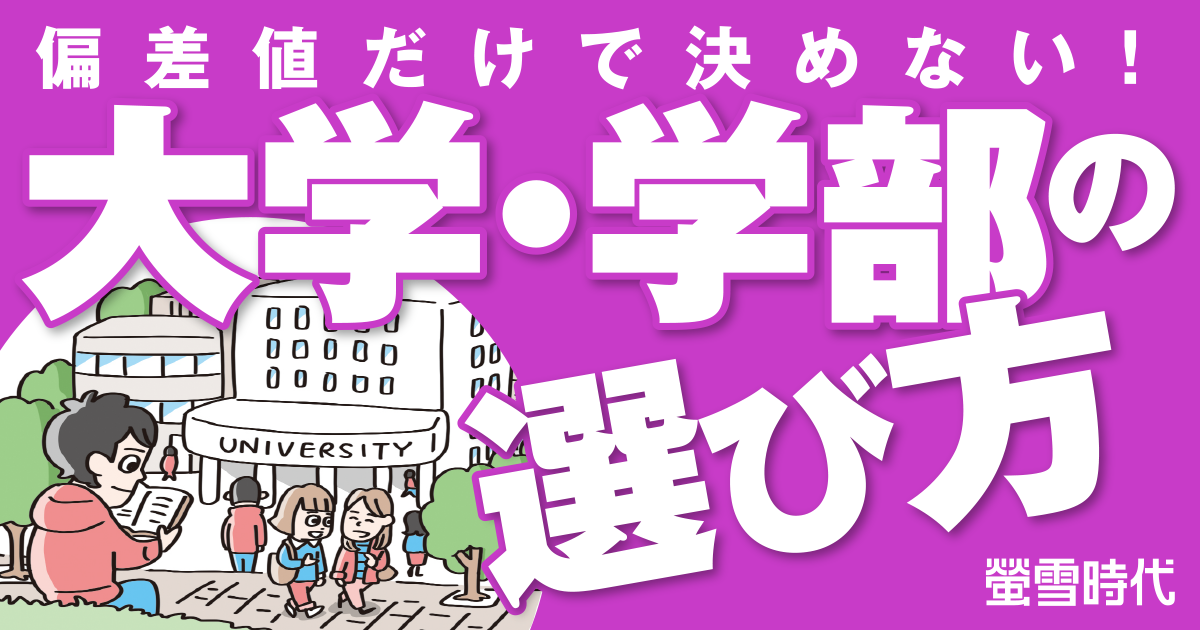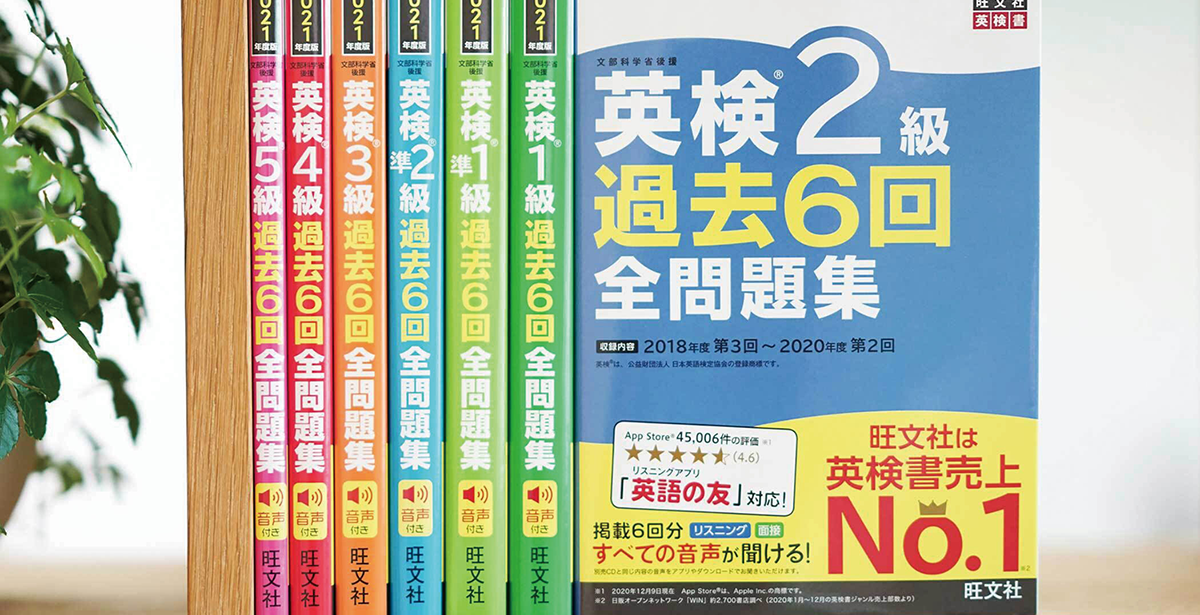学部で絞り込む
歴史
設置 1950、改組 1967
学科定員
法学400
学部内容
複雑化する現代社会で求められる法的思考力を養うために、法律学や政治学を中心に幅広く専門科目を学ぶ。2年次からは、希望する進路などに合わせて、「法専門コース」「行政専門コース」「法総合コース」の3コースを選択する。
△新入生の男女比率(2024年) 男63%・女37%
△新入生の男女比率(2024年) 男63%・女37%
歴史
設置 1949、改組 2000
学科定員
計310 経営215、国際経営95
学部内容
経営学科では、経営に関わる専門的な知識を習得し、企業が直面する課題の解決に必要な能力を養い、社会で即戦力として活躍できる人材を育成する。マネジメントコース、マーケティングコース、会計・ファイナンスコースの3コースを設置。
国際経営学科では、国際経営学に精通したグローバルで活躍できる人材を育成する。グローバルに通用する経営知識とコミュニケーション力を習得し、国際的なビジネス様式や地域文化を学ぶ。海外の現地の企業視察や学生との交流などを行うプログラム、国際フィールドワークを通じて国際感覚や異文化理解力を鍛える。
△新入生の男女比率(2024年) 男47%・女53%
国際経営学科では、国際経営学に精通したグローバルで活躍できる人材を育成する。グローバルに通用する経営知識とコミュニケーション力を習得し、国際的なビジネス様式や地域文化を学ぶ。海外の現地の企業視察や学生との交流などを行うプログラム、国際フィールドワークを通じて国際感覚や異文化理解力を鍛える。
△新入生の男女比率(2024年) 男47%・女53%
歴史
設置 1949、改組 2000
学科定員
計310 経済210、産業社会100
学部内容
経済学科では、経済データ分析などを通じて現代社会の問題を理解し、解決策を書き出せる実践力を養う。理論・歴史・政策の研究を通じて、経済・社会の多方面で貢献できる人材を育てる。国際金融・環境経済・アジア経済などの実態にも踏み込み、多様化・複雑化する社会の動きに柔軟に対応する。
産業社会学科では、産業の仕組みから最先端の動きまでを知り、経済学的な視点から産業や地域社会のあり方を考える。経済学を実社会に生かすための商業経済・産業技術・地域福祉などの各論を幅広く取り扱う。「現場」に入って学ぶフィールドワークを重視。
△新入生の男女比率(2024年) 男71%・女29%
産業社会学科では、産業の仕組みから最先端の動きまでを知り、経済学的な視点から産業や地域社会のあり方を考える。経済学を実社会に生かすための商業経済・産業技術・地域福祉などの各論を幅広く取り扱う。「現場」に入って学ぶフィールドワークを重視。
△新入生の男女比率(2024年) 男71%・女29%
歴史
設置 2016
学科定員
国際英語130
学部内容
国境、分野を超えた共修と協働を実現する世界人材を育成する。そのために必要な、実践的な「英語力」、世界の人びととともに学び、多様な価値観を知る「国際理解」、実社会で専門の異なる人びととチームで活躍するための「協働力」を、実践型英語カリキュラムと豊富な留学・国際研修、企業や海外大学とのコラボ授業、副専攻制度などを通じて養う。
△新入生の男女比率(2024年) 男31%・女69%
△新入生の男女比率(2024年) 男31%・女69%
歴史
設置 2003
学科定員
人間220
学部内容
心理、社会・教育、国際・コミュニケーションの3領域を学び、現代社会で広く活躍できる「実践的教養人」を目指す。ネイティブ教員による語学教育やフィールドワーク、ボランティア、インターンシップ、海外研修などの体験科目にも力を入れている。
△新入生の男女比率(2024年) 男25%・女75%
△新入生の男女比率(2024年) 男25%・女75%
歴史
設置 1995
学科定員
都市情報235
学部内容
都市の未来を探求する。経済学や行政学、地域学、環境学、観光学、情報科学などの知識を身につけるとともに、情報処理技術の習得、フィールドワークなどを通じて、「これからのまちを考える」ための広い視野と分析力、創造力を磨く。まちの未来、都市の未来のために必要な人材を育成する。1・2年次は指導教員制(担任制)、3・4年次は8人前後の少人数ゼミナールで授業を実施する。
△新入生の男女比率(2024年) 男72%・女28%
△新入生の男女比率(2024年) 男72%・女28%
歴史
設置 2022
学科定員
情報工180
学部内容
「総合コース」と「先進プロジェクトコース」を配置。情報工学の広い領域にまたがるフィジカルコンピューティング、データエンジニアリング、ヒューマン・メディア、ネットワークシステムの4つのプログラムを組み合わせた多彩な学びを展開する。
◆総合コースでは、4つの領域の中から自らが選んだプログラムを中心に、情報工学の考え方や技術を深く体系的に学ぶ。
◆先進プロジェクトコースでは、PBL(Project Based Learning)を導入し、実社会で利用されている情報工学を実践的・体系的に学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男83%・女17%
◆総合コースでは、4つの領域の中から自らが選んだプログラムを中心に、情報工学の考え方や技術を深く体系的に学ぶ。
◆先進プロジェクトコースでは、PBL(Project Based Learning)を導入し、実社会で利用されている情報工学を実践的・体系的に学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男83%・女17%
歴史
設置 1950、改組 2013
学科定員
計1,035 数学100、電気電子工160、材料機能工80、応用化学70、機械工125、交通機械工105、メカトロニクス工80、社会基盤デザイン工90、環境創造工80、建築145
学部内容
数学科では、「代数学」「解析学」「幾何学」「数理情報」「計算機科学」の5分野を柱にカリキュラムを編成。論理的な思考力や直観力を養うことで、数学の魅力を理解し発信する力を身につける。教職課程選択者も多く、高い採用実績を誇る。大学院進学希望者への対応も手厚い。
電気電子工学科には、次の2コースがある。「電気工学コース」では、電気エネルギー、半導体、ナノテクの分野を専門的に学ぶ。「電子システムコース」では、ロボットやAI、情報通信、組込みシステムの分野を専門的に学ぶ。工業用の発電機からスマートフォンなど日常生活で使用している電気製品から情報システムまで幅広く学び、現代産業の核心を担う電気電子技術者・研究者を育成する。
材料機能工学科では、物性物理工学と材用化学を基礎とし、発光ダイオードやレーザーに応用される半導体材料など、「新材料」を研究する。ナノテクノロジー材料、半導体材料、機能性材料、機械材料、生体材料など、今後の社会に大きな貢献が期待される材料の研究開発と人材育成に取り組む。
応用化学科では、つくる(合成化学領域)、はかる(物質・材料化学領域)、つかう(環境・エネルギー材料領域)の3領域を設置。次世代テクノロジーをさらに進化させ、原子・分子の領域でのナノ材料開発を目指す。現代社会の問題を化学の力で解決する「ものづくり」に関わる。
機械工学科では、機械工学の核となる力学の理解に必要な数学・物理学を学んだ上で、4つの専門領域へと学びを進め、あらゆる産業の基盤としての機械工学の核心を体系的に身につける。3年次には、小型機械やロボットを設計・製作する。主要産業を支える基盤技術者を育成する。
交通機械工学科では、機械工学の基礎と自転車、鉄道、航空宇宙工学などの応用科目を学び、交通機械を通して社会貢献できる技術者を育成する。模型飛行機用の小型エンジンを分解・組み立てする実践課題をはじめ、実験・実習を重視した「実感教育」を推進している。
メカトロニクス学科では、機械、電気電子、情報工学の基礎を固め、総合力を養うことで、多様な分野で活躍できる技術者を育成する。機械工学分野(機械力学、機構学、制御工学など)、電気電子工学分野(電磁気学、電気回路基礎、電子回路基礎、アナログ電子回路など)、情報工学分野(コンピュータプログラミングなど)といった、ものづくりに必要となる知識をバランスよく学ぶ。
社会基盤デザイン工学科では、美しさ、機能、環境、安全、それらを兼ね備えた「まちづくり」を実現する総合的能力を育成する。都市計画、防災計画、交通計画といったまちづくりのプランニングから、橋や道路をはじめとするハードウエアの設計・建設まで、幅広い領域を学び、社会基盤を形にできる技術者を育てる。
環境創造工学科では、持続可能な経済社会システム構築を目指し「環境創造工学」に基づいた教育と人材育成を推進する。エネルギー工学、生態学、気象学、土木工学、建築学、住環境学といった幅広い分野を学び、身近な環境から地球環境まで、自然と人間の共生をデザインする。
建築学科では、工学、技術から芸術まで、建築を総合的に学ぶ。まちづくりに取り組む市民団体や市町村との連携プロジェクトへの参加や、学外から招いた著名な建築家から指導を受けるなど、アクティブな学びの機会を豊富に用意。一級建築士の受験資格を得ることもできる。また、3次元の地震を再現可能な振動台も設置している。
△新入生の男女比率(2024年) 男82%・女18%
電気電子工学科には、次の2コースがある。「電気工学コース」では、電気エネルギー、半導体、ナノテクの分野を専門的に学ぶ。「電子システムコース」では、ロボットやAI、情報通信、組込みシステムの分野を専門的に学ぶ。工業用の発電機からスマートフォンなど日常生活で使用している電気製品から情報システムまで幅広く学び、現代産業の核心を担う電気電子技術者・研究者を育成する。
材料機能工学科では、物性物理工学と材用化学を基礎とし、発光ダイオードやレーザーに応用される半導体材料など、「新材料」を研究する。ナノテクノロジー材料、半導体材料、機能性材料、機械材料、生体材料など、今後の社会に大きな貢献が期待される材料の研究開発と人材育成に取り組む。
応用化学科では、つくる(合成化学領域)、はかる(物質・材料化学領域)、つかう(環境・エネルギー材料領域)の3領域を設置。次世代テクノロジーをさらに進化させ、原子・分子の領域でのナノ材料開発を目指す。現代社会の問題を化学の力で解決する「ものづくり」に関わる。
機械工学科では、機械工学の核となる力学の理解に必要な数学・物理学を学んだ上で、4つの専門領域へと学びを進め、あらゆる産業の基盤としての機械工学の核心を体系的に身につける。3年次には、小型機械やロボットを設計・製作する。主要産業を支える基盤技術者を育成する。
交通機械工学科では、機械工学の基礎と自転車、鉄道、航空宇宙工学などの応用科目を学び、交通機械を通して社会貢献できる技術者を育成する。模型飛行機用の小型エンジンを分解・組み立てする実践課題をはじめ、実験・実習を重視した「実感教育」を推進している。
メカトロニクス学科では、機械、電気電子、情報工学の基礎を固め、総合力を養うことで、多様な分野で活躍できる技術者を育成する。機械工学分野(機械力学、機構学、制御工学など)、電気電子工学分野(電磁気学、電気回路基礎、電子回路基礎、アナログ電子回路など)、情報工学分野(コンピュータプログラミングなど)といった、ものづくりに必要となる知識をバランスよく学ぶ。
社会基盤デザイン工学科では、美しさ、機能、環境、安全、それらを兼ね備えた「まちづくり」を実現する総合的能力を育成する。都市計画、防災計画、交通計画といったまちづくりのプランニングから、橋や道路をはじめとするハードウエアの設計・建設まで、幅広い領域を学び、社会基盤を形にできる技術者を育てる。
環境創造工学科では、持続可能な経済社会システム構築を目指し「環境創造工学」に基づいた教育と人材育成を推進する。エネルギー工学、生態学、気象学、土木工学、建築学、住環境学といった幅広い分野を学び、身近な環境から地球環境まで、自然と人間の共生をデザインする。
建築学科では、工学、技術から芸術まで、建築を総合的に学ぶ。まちづくりに取り組む市民団体や市町村との連携プロジェクトへの参加や、学外から招いた著名な建築家から指導を受けるなど、アクティブな学びの機会を豊富に用意。一級建築士の受験資格を得ることもできる。また、3次元の地震を再現可能な振動台も設置している。
△新入生の男女比率(2024年) 男82%・女18%
歴史
設置 1950
学科定員
計330 生物資源110、応用生物化学110、生物環境科学110
学部内容
生物資源学科では、動植物や微生物などの生物資源の有効利用と生産方法を研究し、持続可能な農と食のスペシャリストを目指す。生物生産学、遺伝育種学、生物保護学、経営・経済学の4領域を学び、自然科学の基礎から、植物の生産・管理技術、農産物の流通、最新のバイオテクノロジーにいたるまで、幅広い専門知識とスキルを身につける。
応用生物化学科では、生物や食物の機能を解析し、食と健康に役立つ新たな物質の発見や、化粧品・医療関連産業の製品開発に貢献できる専門家を育てる。生命科学、食品科学、分子化学、生物制御科学の4領域を学び、バイオテクノロジーや、分子生物学・遺伝子工学的手法による糖質・脂質・タンパク質などの機能解明に取り組む。
生物環境科学科では、生物、人、自然との調和について学び、生物環境の評価・保全・創造に関する知識と技術を養う。生態保全学、緑地創造学、生物機能調節化学、環境化学の4領域において実習実験を交えて広く学び、附属農場や里山などで実習も行うなど、実践的な学びを展開する。
△新入生の男女比率(2024年) 男44%・女56%
応用生物化学科では、生物や食物の機能を解析し、食と健康に役立つ新たな物質の発見や、化粧品・医療関連産業の製品開発に貢献できる専門家を育てる。生命科学、食品科学、分子化学、生物制御科学の4領域を学び、バイオテクノロジーや、分子生物学・遺伝子工学的手法による糖質・脂質・タンパク質などの機能解明に取り組む。
生物環境科学科では、生物、人、自然との調和について学び、生物環境の評価・保全・創造に関する知識と技術を養う。生態保全学、緑地創造学、生物機能調節化学、環境化学の4領域において実習実験を交えて広く学び、附属農場や里山などで実習も行うなど、実践的な学びを展開する。
△新入生の男女比率(2024年) 男44%・女56%
他の大学の情報も確認しよう
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。