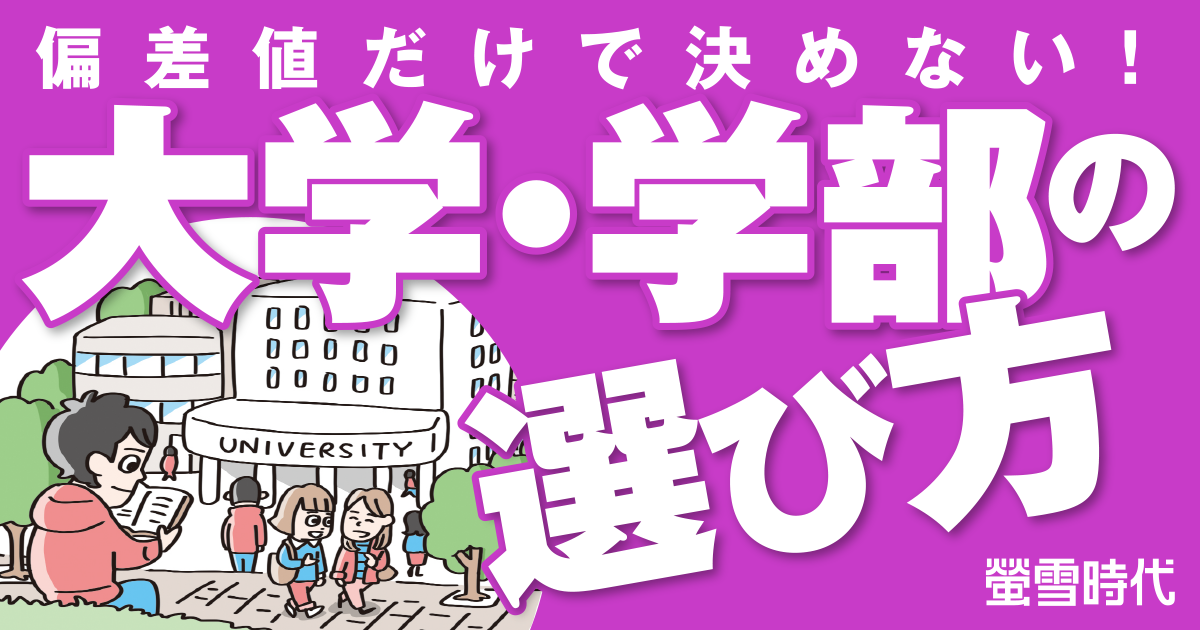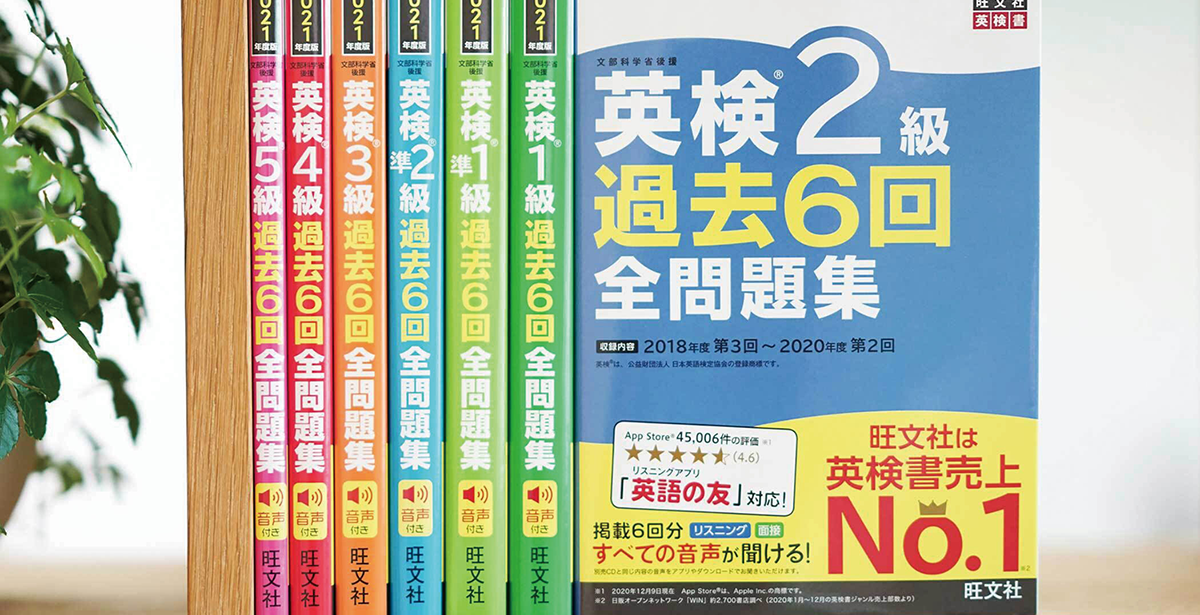学部で絞り込む
歴史
設置 1948、改組 2008
学科定員
法学政治715
学部内容
法律学・政治学の両分野に精通し、現代の法化社会を生きる力量を身につけた人材の育成を目指す。全ての学生が法律学・政治学の両分野において、その基礎を修得し、それぞれの志向や進路に向けた段階的学習ができるカリキュラムを導入している。
1年次では、学部で必要とされる基本的な学習技術・方法のトレーニングを行う。また、憲法や民法、政治学について全分野にわたって必要な知識基盤を確立する。
2~4年次では、法律学と政治学について、分野を横断する学習で、多角的・総合的な視野を養う。同時に、法現象、政治現象を専門的に観察・分析して理解することを学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男57%・女43%
1年次では、学部で必要とされる基本的な学習技術・方法のトレーニングを行う。また、憲法や民法、政治学について全分野にわたって必要な知識基盤を確立する。
2~4年次では、法律学と政治学について、分野を横断する学習で、多角的・総合的な視野を養う。同時に、法現象、政治現象を専門的に観察・分析して理解することを学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男57%・女43%
歴史
設置 1948
学科定員
総合人文770
学部内容
1年次に各専修の学びにふれ興味・関心を見極め、2年次から下記16専修のいずれかに分属。専門分野の研究に取り組む。
◆英米文学英語学専修では、英米の文学作品や文化を研究する英米文学研究と、音韻論・文法論・翻訳論・意味論などを研究する英語学研究の2分野から1分野を選択して学ぶ。
◆英米文化専修では、英米を中心とする英語圏の文化を幅広い視野から総合的・学際的に研究する。
◆国語国文学専修では、古代から現代に至るまでの“日本語”で表現された文学作品を読み解くことにより、芸術・文学の本質を追究し、その時代の人間の存在や社会のあり方を考えていく。
◆哲学倫理学専修では、自己と他者、時間と空間、道徳と規範などといった伝統的な哲学的倫理学的問題について深く考察する。また、環境保護、生命・医療をめぐる問題、ネット社会のあり方、心と脳など、現代特有の問題についても考察する。
◆比較宗教学専修では、「国際化時代に必要な宗教理解」をキーワードに世界の諸宗教を幅広く学ぶとともに、「宗教文化士」という認定資格に挑戦することができる。
◆芸術学美術史専修では、「芸術とは何か」「美とは何か」という問いを、理論的・実証的に追究する。
◆ヨーロッパ文化専修は、ドイツ・フランスを中心とするヨーロッパの豊かな文化が学べる専修であり、ドイツ言語文化コースとフランス言語文化コースを設けている。
◆日本史・文化遺産学専修では、古代・中世から近世・近現代に至る日本の歴史のなかから自由にテーマを選ぶことができ、考古学や民俗学も学ぶことができる。
◆世界史専修では、古代・中世から近現代まで世界の諸地域の歴史のなかから関心のあるテーマを選んで学ぶ。
◆地理学・地域環境学専修では、従来の人文地理学と自然地理学に加えて、「地域環境」をキーワードに新しい地平を切りひらくことを目指している。
◆教育文化専修では、生涯にわたる人間形成のあらゆる現象を教育・学習と広くとらえ、「教える」「学ぶ」に関わるグローバル化や情報化などの社会変化を見据えながら、多面的なアプローチから社会と文化のあり方について考える。
◆初等教育学専修では、豊かな教養と人間性を備えた小学校教員を育成する。英語や情報教育、特別支援などの今日の教育課題についても取り組む。
◆心理学専修では、現代の家庭や学校、地域社会で生じるさまざまな心理学的諸問題を視野に入れ、人間の理解と人間形成を目指す。
◆映像文化専修では、映画を中心とするグローバルな映像メディア文化を学び、映像メディア全般を批判的に読み解く能力を磨く。
◆文化共生学専修では、ヨーロッパ・地中海・イスラームの文化をはじめ、現代日本のジェンダー文化などを幅広く学び、共生の実現に向けて行動する力を育成する。
◆アジア文化専修では、「伝統文化」はもちろん、「現代のアジア」という視点からもアジア諸国の文化をトータルに理解する国際人を育成することを目指す。アジア文化と中国言語文化の2コース制。
△新入生の男女比率(2024年) 男38%・女62%
◆英米文学英語学専修では、英米の文学作品や文化を研究する英米文学研究と、音韻論・文法論・翻訳論・意味論などを研究する英語学研究の2分野から1分野を選択して学ぶ。
◆英米文化専修では、英米を中心とする英語圏の文化を幅広い視野から総合的・学際的に研究する。
◆国語国文学専修では、古代から現代に至るまでの“日本語”で表現された文学作品を読み解くことにより、芸術・文学の本質を追究し、その時代の人間の存在や社会のあり方を考えていく。
◆哲学倫理学専修では、自己と他者、時間と空間、道徳と規範などといった伝統的な哲学的倫理学的問題について深く考察する。また、環境保護、生命・医療をめぐる問題、ネット社会のあり方、心と脳など、現代特有の問題についても考察する。
◆比較宗教学専修では、「国際化時代に必要な宗教理解」をキーワードに世界の諸宗教を幅広く学ぶとともに、「宗教文化士」という認定資格に挑戦することができる。
◆芸術学美術史専修では、「芸術とは何か」「美とは何か」という問いを、理論的・実証的に追究する。
◆ヨーロッパ文化専修は、ドイツ・フランスを中心とするヨーロッパの豊かな文化が学べる専修であり、ドイツ言語文化コースとフランス言語文化コースを設けている。
◆日本史・文化遺産学専修では、古代・中世から近世・近現代に至る日本の歴史のなかから自由にテーマを選ぶことができ、考古学や民俗学も学ぶことができる。
◆世界史専修では、古代・中世から近現代まで世界の諸地域の歴史のなかから関心のあるテーマを選んで学ぶ。
◆地理学・地域環境学専修では、従来の人文地理学と自然地理学に加えて、「地域環境」をキーワードに新しい地平を切りひらくことを目指している。
◆教育文化専修では、生涯にわたる人間形成のあらゆる現象を教育・学習と広くとらえ、「教える」「学ぶ」に関わるグローバル化や情報化などの社会変化を見据えながら、多面的なアプローチから社会と文化のあり方について考える。
◆初等教育学専修では、豊かな教養と人間性を備えた小学校教員を育成する。英語や情報教育、特別支援などの今日の教育課題についても取り組む。
◆心理学専修では、現代の家庭や学校、地域社会で生じるさまざまな心理学的諸問題を視野に入れ、人間の理解と人間形成を目指す。
◆映像文化専修では、映画を中心とするグローバルな映像メディア文化を学び、映像メディア全般を批判的に読み解く能力を磨く。
◆文化共生学専修では、ヨーロッパ・地中海・イスラームの文化をはじめ、現代日本のジェンダー文化などを幅広く学び、共生の実現に向けて行動する力を育成する。
◆アジア文化専修では、「伝統文化」はもちろん、「現代のアジア」という視点からもアジア諸国の文化をトータルに理解する国際人を育成することを目指す。アジア文化と中国言語文化の2コース制。
△新入生の男女比率(2024年) 男38%・女62%
歴史
設置 1948
学科定員
経済726
学部内容
以下の4コース制。
◆経済政策コースでは、財政、社会保障、雇用、地方創生など政府活動に関わる問題を考察する。消費税、年金、東京一極集中の是正、環境問題など、さまざまな社会問題に対処する政府の経済政策を学ぶ。
◆産業・企業経済コースでは、ビジネスの現場で起きているさまざまな現象の本質を読み解くために、企業の行動原理やビジネスデータを分析・活用する方法を学ぶ。
◆歴史・思想コースでは、経済や社会思想が発展してきた過程を歴史的に考察する。過去を知ることにより、現代経済の問題を解決するための新たな糸口を模索する。
◆国際経済コースでは、ヒト・モノ・サービス・カネが国や地域を越えて移動するグローバル社会を考察する。モノの移動を考える国際貿易、カネの移動を考える国際金融など世界経済の仕組みを理解するとともに、経済発展著しい中国・インドなど、個別の国の経済事情を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男68%・女32%
◆経済政策コースでは、財政、社会保障、雇用、地方創生など政府活動に関わる問題を考察する。消費税、年金、東京一極集中の是正、環境問題など、さまざまな社会問題に対処する政府の経済政策を学ぶ。
◆産業・企業経済コースでは、ビジネスの現場で起きているさまざまな現象の本質を読み解くために、企業の行動原理やビジネスデータを分析・活用する方法を学ぶ。
◆歴史・思想コースでは、経済や社会思想が発展してきた過程を歴史的に考察する。過去を知ることにより、現代経済の問題を解決するための新たな糸口を模索する。
◆国際経済コースでは、ヒト・モノ・サービス・カネが国や地域を越えて移動するグローバル社会を考察する。モノの移動を考える国際貿易、カネの移動を考える国際金融など世界経済の仕組みを理解するとともに、経済発展著しい中国・インドなど、個別の国の経済事情を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男68%・女32%
歴史
設置 1948
学科定員
商学726
学部内容
3年次から以下の5専修に分かれる。
◆流通専修では、流通のメカニズムや企業活動に関する知識・理論を学ぶ。
◆ファイナンス専修では、金融機関の構造を資金運用、リスクなどを中心に学ぶ。
◆国際ビジネス専修では、国際関係、貿易、世界経済などをグローバルな視点で研究する。
◆マネジメント専修では、管理、労務、情報、戦略など、企業・経営の実務を学ぶ。
◆会計専修では、簿記や会計情報を読み解く実務と理論を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男52%・女48%
◆流通専修では、流通のメカニズムや企業活動に関する知識・理論を学ぶ。
◆ファイナンス専修では、金融機関の構造を資金運用、リスクなどを中心に学ぶ。
◆国際ビジネス専修では、国際関係、貿易、世界経済などをグローバルな視点で研究する。
◆マネジメント専修では、管理、労務、情報、戦略など、企業・経営の実務を学ぶ。
◆会計専修では、簿記や会計情報を読み解く実務と理論を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男52%・女48%
歴史
設置 1967
学科定員
社会792
学部内容
以下の4専攻がある。
◆社会学専攻には、家族、都市、民族、意識、メディア、若者、福祉、差別など、多彩なテーマを研究する教員スタッフがそろっており、知的刺激にあふれた環境で、多面的な切り口で問題を分析していく。
◆心理学専攻では、個人‐集団‐社会に焦点を当て、「仮説の提示」と「事実による検証」によって、人間の心と行動の仕組みについて科学的に解明していく。コンピュータを用いた高度な情報処理技術を学修し、解明のための科学的プロセスを身につける。
◆メディア専攻では、メディア社会の本質を見つめ、未来のマスコミのあるべき姿を考える。
◆社会システムデザイン専攻では、社会学・経済学・経営学・科学技術論などの学問領域を通して現代社会についての知識を身につけ、より良い社会・組織をデザインし、その構築の方法を考えるプロセスを学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男38%・女62%
◆社会学専攻には、家族、都市、民族、意識、メディア、若者、福祉、差別など、多彩なテーマを研究する教員スタッフがそろっており、知的刺激にあふれた環境で、多面的な切り口で問題を分析していく。
◆心理学専攻では、個人‐集団‐社会に焦点を当て、「仮説の提示」と「事実による検証」によって、人間の心と行動の仕組みについて科学的に解明していく。コンピュータを用いた高度な情報処理技術を学修し、解明のための科学的プロセスを身につける。
◆メディア専攻では、メディア社会の本質を見つめ、未来のマスコミのあるべき姿を考える。
◆社会システムデザイン専攻では、社会学・経済学・経営学・科学技術論などの学問領域を通して現代社会についての知識を身につけ、より良い社会・組織をデザインし、その構築の方法を考えるプロセスを学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男38%・女62%
歴史
設置 2007
学科定員
計350 政策250、国際アジア100
学部内容
政策学科では、グローバル化、環境問題、日本の少子高齢化など、国内外の社会問題に対し、解決のための政策を柔軟かつ総合的に判断・提案する能力を養う。「政治経済」「地域経営」の2専修制。2年次に専修に分かれた後は、それぞれの関心に応じてより専門性の高い学びを深めることができる。
国際アジア学科では、激動する国際関係、国際経済を読み解くため、経済、政治、法律の基礎を身につけ、アジアをはじめとした世界各国・地域の経済、政治、社会、法律を比較して、それぞれの特徴を理解する。今後、世界がどのような問題に直面するのか。その問題を解決するためにはどうしたらよいのか。そのために必要な、考える力と行動力「考動力」を養う。
△新入生の男女比率(2024年) 男53%・女47%
国際アジア学科では、激動する国際関係、国際経済を読み解くため、経済、政治、法律の基礎を身につけ、アジアをはじめとした世界各国・地域の経済、政治、社会、法律を比較して、それぞれの特徴を理解する。今後、世界がどのような問題に直面するのか。その問題を解決するためにはどうしたらよいのか。そのために必要な、考える力と行動力「考動力」を養う。
△新入生の男女比率(2024年) 男53%・女47%
歴史
設置 2009
学科定員
外国語165
学部内容
優れた外国語科目担当教員の養成と、実践知性としての高度なコミュニケーション能力を備え、国際舞台で幅広く活躍できるリーダーの養成を目指す。
原則として2年次生全員が、海外の大学に1年間留学するStudy Abroadプログラムを設け、言語運用能力の着実な向上を目指している。
3年次からは、自らの興味・関心に応じて選択可能な以下の5つのプログラムを設定している。
◆外国語教育では、言語習得やコミュニケーションの基礎理論と外国語(日・英・中)の学び方、教え方を実践的かつ科学的に学ぶ。
◆エリア・スタディーズでは地域固有の言語文化の理解を深めるとともにグローバル社会に求められる視点を得る。
◆異文化コミュニケーションでは、人間の文化と心理、異文化接触・交渉について学際的に学ぶ。
◆通訳翻訳では、通訳翻訳の理論や方法を系統的かつ体験的に学ぶ。
◆国際協力・地域協力では、社会における共生や協働について、グローバル、ローカル両面から系統的かつ体験的に学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男26%・女74%
原則として2年次生全員が、海外の大学に1年間留学するStudy Abroadプログラムを設け、言語運用能力の着実な向上を目指している。
3年次からは、自らの興味・関心に応じて選択可能な以下の5つのプログラムを設定している。
◆外国語教育では、言語習得やコミュニケーションの基礎理論と外国語(日・英・中)の学び方、教え方を実践的かつ科学的に学ぶ。
◆エリア・スタディーズでは地域固有の言語文化の理解を深めるとともにグローバル社会に求められる視点を得る。
◆異文化コミュニケーションでは、人間の文化と心理、異文化接触・交渉について学際的に学ぶ。
◆通訳翻訳では、通訳翻訳の理論や方法を系統的かつ体験的に学ぶ。
◆国際協力・地域協力では、社会における共生や協働について、グローバル、ローカル両面から系統的かつ体験的に学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男26%・女74%
歴史
設置 2010
学科定員
人間健康330
学部内容
「こころ」「からだ」「くらし」を総合的にとらえ、人間の幸福を実現するための健康に関わる諸問題の解決策を探究する。以下の2コースがある。
◆スポーツと健康コースでは、生涯スポーツ活動を通しての人間形成やコミュニティの再生、あるいはスポーツ教育を通した新たな人間の健康のあり方を探り、地域コミュニティにおいて活動できるスポーツ指導者などの養成を目指す。
◆福祉と健康コースでは、これまでの社会福祉のあり方や実践を、主体的に生きる人間の生活環境と健康との関係でとらえ直し、子どもや高齢者を「援助を必要とする弱者」と見るのではなく、「地域コミュニティを創造する主体者」としてとらえ、地域コミュニティにおける福祉文化の諸課題を教育・研究する。
△新入生の男女比率(2024年) 男55%・女45%
◆スポーツと健康コースでは、生涯スポーツ活動を通しての人間形成やコミュニティの再生、あるいはスポーツ教育を通した新たな人間の健康のあり方を探り、地域コミュニティにおいて活動できるスポーツ指導者などの養成を目指す。
◆福祉と健康コースでは、これまでの社会福祉のあり方や実践を、主体的に生きる人間の生活環境と健康との関係でとらえ直し、子どもや高齢者を「援助を必要とする弱者」と見るのではなく、「地域コミュニティを創造する主体者」としてとらえ、地域コミュニティにおける福祉文化の諸課題を教育・研究する。
△新入生の男女比率(2024年) 男55%・女45%
歴史
設置 1994
学科定員
総合情報500
学部内容
社会のさまざまな領域を「情報」という視点から探究し、幅広い視野を養うことを目指す。カリキュラムは以下の3系から構成される。
◆メディア情報系では、インターネットをはじめ多様化が進む情報メディアとコミュニケーションに関する専門分野を中心に学ぶ。
◆社会情報システム系では、企業や自治体などの組織を経営・管理・運営するにあたり、情報をどのように活用するかを中心に学ぶ。
◆コンピューティング系では、高度化が進む情報社会に求められる最新技術とともに、人間と共存・協調できるコンピュータの可能性を追究していく。
△新入生の男女比率(2024年) 男62%・女38%
◆メディア情報系では、インターネットをはじめ多様化が進む情報メディアとコミュニケーションに関する専門分野を中心に学ぶ。
◆社会情報システム系では、企業や自治体などの組織を経営・管理・運営するにあたり、情報をどのように活用するかを中心に学ぶ。
◆コンピューティング系では、高度化が進む情報社会に求められる最新技術とともに、人間と共存・協調できるコンピュータの可能性を追究していく。
△新入生の男女比率(2024年) 男62%・女38%
歴史
設置 2010
学科定員
安全マネジメント275
学部内容
現代社会の安全を脅かすさまざまな問題を解決するために、法学、政治学、経済学、経営学、心理学、社会学、理学、情報学、工学、社会医学などを幅広く学び、安全・安心な社会の構築に寄与する人材の育成を目指す。
以下の2つの専門科目群を設置している。
◆社会災害マネジメント科目では、人為的な社会災害に関わる安全・安心を実現するための組織や経営制度、企業倫理、ヒューマンエラー、人間心理、社会心理、公共政策、安全規制と法などの科目を学ぶ。
◆自然災害マネジメント科目では、自然災害に関わる安全・安心を実現するための地震災害・防災危機管理、災害復興、被災者の救援と支援などの防災・減災関連の科目を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男67%・女33%
以下の2つの専門科目群を設置している。
◆社会災害マネジメント科目では、人為的な社会災害に関わる安全・安心を実現するための組織や経営制度、企業倫理、ヒューマンエラー、人間心理、社会心理、公共政策、安全規制と法などの科目を学ぶ。
◆自然災害マネジメント科目では、自然災害に関わる安全・安心を実現するための地震災害・防災危機管理、災害復興、被災者の救援と支援などの防災・減災関連の科目を学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男67%・女33%
歴史
設置 2025
学科定員
ビジネスデータサイエンス350
学部内容
スマートフォンやIoTの普及によって、あらゆる種類の膨大なデータが蓄積できるようになり、データを起点に新たな価値を創出するデータサイエンスの知見が必要とされる現代社会において、高度なデータサイエンスのスキルを持ち、それをビジネスの現場で生かせる人材の育成を目指す。
以下の3つの力を身につけられるカリキュラムを編成する。
まず「ビジネス力」として、経営学や会計・金融などのビジネスに関する基礎知識、実際のビジネスの場で必要とされる課題解決力やコミュニケーション力を養う。
また、「データサイエンス力」として、AI(人工知能)やデータサイエンス、データエンジニアリングを体系的に学び、高度な分析力や構想力を身につける。
さらに「人間力」として、社会の諸問題に対処する適応力や、世の中の変化に応じて自らをアップデートし続ける自己研鑽力も磨いていく。
以下の3つの力を身につけられるカリキュラムを編成する。
まず「ビジネス力」として、経営学や会計・金融などのビジネスに関する基礎知識、実際のビジネスの場で必要とされる課題解決力やコミュニケーション力を養う。
また、「データサイエンス力」として、AI(人工知能)やデータサイエンス、データエンジニアリングを体系的に学び、高度な分析力や構想力を身につける。
さらに「人間力」として、社会の諸問題に対処する適応力や、世の中の変化に応じて自らをアップデートし続ける自己研鑽力も磨いていく。
歴史
設置 1958、改組 2007
学科定員
計501 数学、物理・応用物理、機械工、電気電子情報工
学部内容
数学科では、数学の論理的構造をじっくり学び、さまざまな事象に内在する本質を見抜く洞察力を養成する。
物理・応用物理学科では、物理学の研究成果を社会に還元し、世界の発展に貢献できる技術者・研究者の育成を目指す。基礎・計算物理、応用物理の2コースがある。
機械工学科では、機械製作に必要な材料や力学特性、エネルギー変換の原理と技術、運動や振動現象などについて理解するとともに、機械を構成する要素や機構の設計、組み立て方法、情報・計測・制御の基礎理論についても学ぶ。
電気電子情報工学科では、電気電子工学と情報工学の両分野を幅広く学ぶ。数学や物理学などをベースに、電気・電子系の演習を通じて、実践的能力や応用力を育成する。電気電子工学、情報通信工学、応用情報工学の3コースを設置している。
△新入生の男女比率(2024年) 男91%・女9%
物理・応用物理学科では、物理学の研究成果を社会に還元し、世界の発展に貢献できる技術者・研究者の育成を目指す。基礎・計算物理、応用物理の2コースがある。
機械工学科では、機械製作に必要な材料や力学特性、エネルギー変換の原理と技術、運動や振動現象などについて理解するとともに、機械を構成する要素や機構の設計、組み立て方法、情報・計測・制御の基礎理論についても学ぶ。
電気電子情報工学科では、電気電子工学と情報工学の両分野を幅広く学ぶ。数学や物理学などをベースに、電気・電子系の演習を通じて、実践的能力や応用力を育成する。電気電子工学、情報通信工学、応用情報工学の3コースを設置している。
△新入生の男女比率(2024年) 男91%・女9%
歴史
設置 1958、改組 2007
学科定員
計325 建築、都市システム工、エネルギー環境・化学工
学部内容
より快適な未来の都市を創造・再生するために、環境、都市デザインなどをキーワードとして新しい総合的な科学技術を構築し、研究する。
建築学科では、身近な環境としての建物の構造や、人間心理、自然現象といった理系・文系分野の知識をバランスよく学び、防災に優れた建造物の構造を研究したり、伝統的な建造物を災害から守る方法を考えたりする。
都市システム工学科では、災害の被害を最小限に食い止めるため、道路や鉄道、河川、海岸、ライフラインなどに着目し、都市のあり方をあらゆる側面から検討する。災害時の情報提供についても考える。都市インフラ設計、社会システム計画の2コースを設置している。
エネルギー環境・化学工学科では、有害な排気ガスを無害化する技術や高機能な浄水・排水技術をはじめ、省エネルギー、新エネルギー、リサイクル、環境再生など、より良いまちづくりに必要な化学システムについて学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男77%・女23%
建築学科では、身近な環境としての建物の構造や、人間心理、自然現象といった理系・文系分野の知識をバランスよく学び、防災に優れた建造物の構造を研究したり、伝統的な建造物を災害から守る方法を考えたりする。
都市システム工学科では、災害の被害を最小限に食い止めるため、道路や鉄道、河川、海岸、ライフラインなどに着目し、都市のあり方をあらゆる側面から検討する。災害時の情報提供についても考える。都市インフラ設計、社会システム計画の2コースを設置している。
エネルギー環境・化学工学科では、有害な排気ガスを無害化する技術や高機能な浄水・排水技術をはじめ、省エネルギー、新エネルギー、リサイクル、環境再生など、より良いまちづくりに必要な化学システムについて学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 男77%・女23%
歴史
設置 1958、改組 2007
学科定員
計347 化学・物質工、生命・生物工
学部内容
化学・物質工学科では、新物質・新素材の機能設計や創成とそれらを製造するためのプロセス技術の開発などを通じて、科学技術の発展に貢献することを目指す。化学知識を深めながら、基礎物理学や生物学的な知識も修得する。マテリアル科学、応用化学、バイオ分子化学の3コースがある。
生命・生物工学科では、DNAやタンパク質の構造・機能を理解し、それらの相互作用に基づく高次の生命現象を学習する。さらに、今日の研究者・技術者に求められる高い倫理観も養う。バイオテクノロジー、ライフサイエンスの2コースを設置している。
△新入生の男女比率(2024年) 男58%・女42%
生命・生物工学科では、DNAやタンパク質の構造・機能を理解し、それらの相互作用に基づく高次の生命現象を学習する。さらに、今日の研究者・技術者に求められる高い倫理観も養う。バイオテクノロジー、ライフサイエンスの2コースを設置している。
△新入生の男女比率(2024年) 男58%・女42%
他の大学の情報も確認しよう
関西大学 の
過去問
関西大学 の
資料請求
- 大学案内・入試ガイド2026無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。