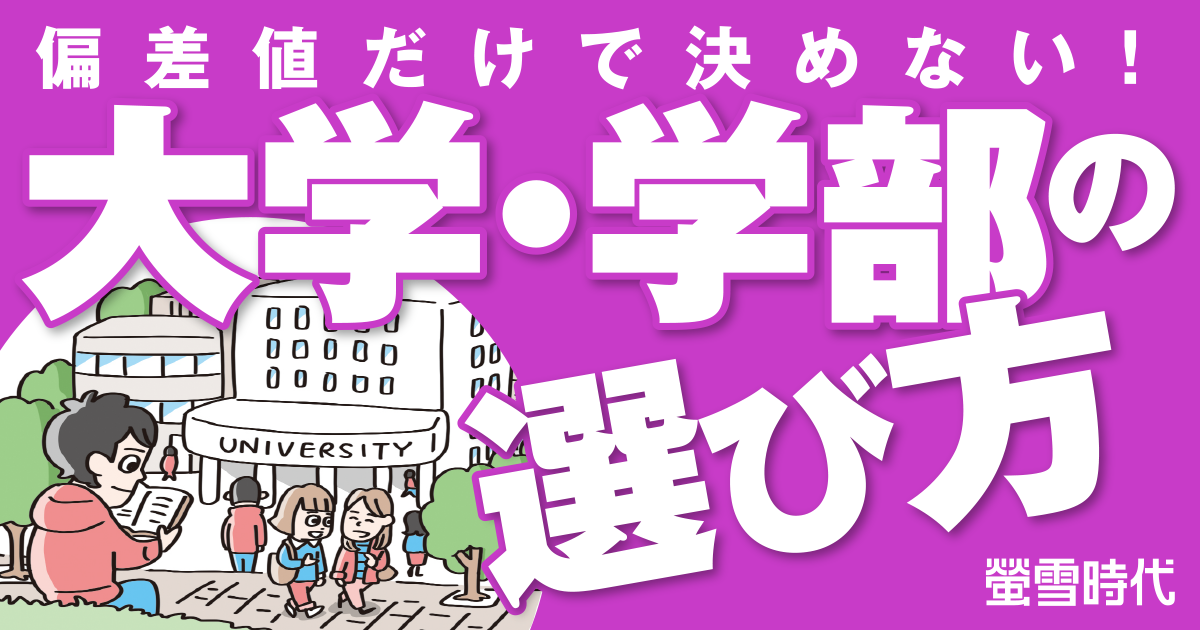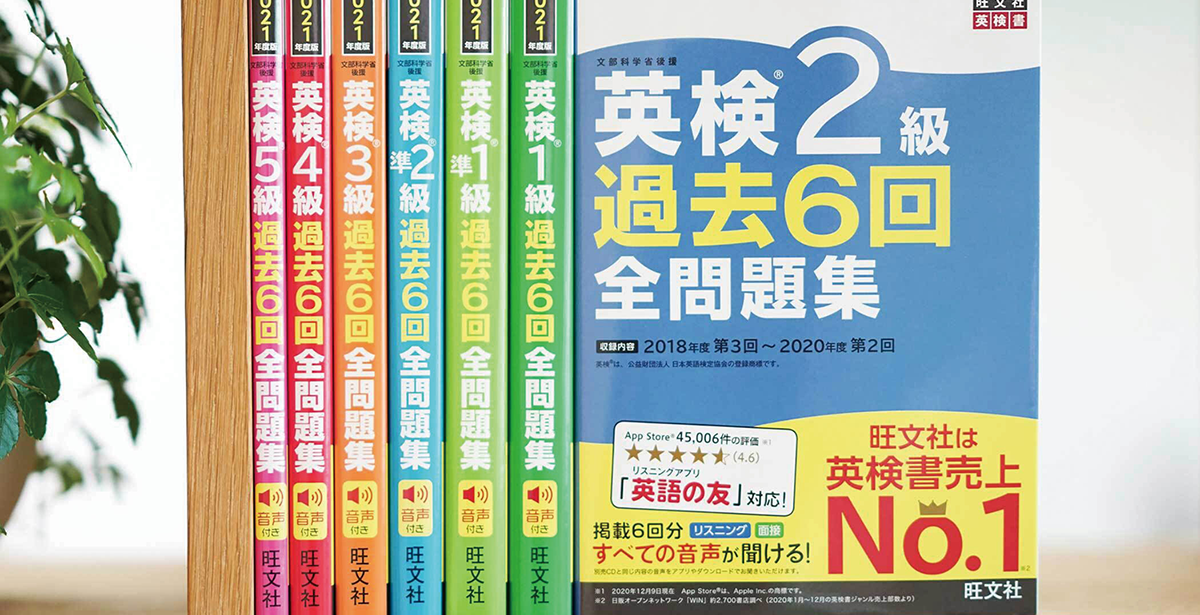学部で絞り込む
歴史
設置 1949
学科定員
〈1部〉
計849 哲学100、東洋思想文化100、日本文学文化133、英米文133、史学133、教育150<人間発達100、初等教育50>、国際文化コミュニケーション100
〈イブニングコース(2部)〉
計120 東洋思想文化30、日本文学文化50、教育40
学部内容
哲学科では、「講義」によって哲学的な知識を身につけ、その知識を基にして、「演習」において精密にテキストを読解し、徹底的に討論や対話を行う。学びと思索を繰り返しながら、哲学者たちから発せられる真のメッセージを読み解いていく。
東洋思想文化学科では、東洋の歴史のなかで培われた思想や文化を広く学ぶとともに、それぞれの興味に応じた4つのコース(「インド思想」「中国語・中国哲学文学」「仏教思想」「東洋芸術文化」)で専門性を高める。
日本文学文化学科では、日本の文学や文化を、グローバルな視点から考察し、理解を深め、その内容を世界に向けて発信できる人財を目指す。
英米文学科では、英語を「文学」と「語学」の両面から学び、文学的・語学的読解力と、思考力、表現力を身につける。
史学科では、文献史料などから、過去に生きた人びとの社会や暮らしを分析し、歴史像を組み立てる。「日本史」「東洋史」「西洋史」の3つの専攻で、ゼミナールを中心に学びを深める。
教育学科は以下の2専攻に分かれる。
◆人間発達専攻では、全ての世代が発達の過程にあるとする「生涯発達」の捉え方を軸に、教育を多面的に考える。多様化する教育へのニーズに応えるため、教育学だけでなく、多様な学問へと学びの領域を広げ、現代社会が直面する問題に主体的に関わる力の獲得を目指す。
◆初等教育専攻では、豊かな人間性と、実践的な指導力、確かな「授業力」を備えた教員を目指す。4年間を通じて行う「往還型教育実習」により教室で学んだことを現場で確かめ、現場での経験と課題を大学で研究する。その繰り返しにより、高度な専門性と教員としての実践的指導力を養う。
国際文化コミュニケーション学科では、お互いを尊重し、国や価値観の違いを越えて理解し、信頼し合える関係性をつくりだすために、相手と自らの文化に対する深い理解と、多言語で文化を受発信できるコミュニケーション能力の獲得を目指す。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男55%・女45%、2部:男55%・女45%
東洋思想文化学科では、東洋の歴史のなかで培われた思想や文化を広く学ぶとともに、それぞれの興味に応じた4つのコース(「インド思想」「中国語・中国哲学文学」「仏教思想」「東洋芸術文化」)で専門性を高める。
日本文学文化学科では、日本の文学や文化を、グローバルな視点から考察し、理解を深め、その内容を世界に向けて発信できる人財を目指す。
英米文学科では、英語を「文学」と「語学」の両面から学び、文学的・語学的読解力と、思考力、表現力を身につける。
史学科では、文献史料などから、過去に生きた人びとの社会や暮らしを分析し、歴史像を組み立てる。「日本史」「東洋史」「西洋史」の3つの専攻で、ゼミナールを中心に学びを深める。
教育学科は以下の2専攻に分かれる。
◆人間発達専攻では、全ての世代が発達の過程にあるとする「生涯発達」の捉え方を軸に、教育を多面的に考える。多様化する教育へのニーズに応えるため、教育学だけでなく、多様な学問へと学びの領域を広げ、現代社会が直面する問題に主体的に関わる力の獲得を目指す。
◆初等教育専攻では、豊かな人間性と、実践的な指導力、確かな「授業力」を備えた教員を目指す。4年間を通じて行う「往還型教育実習」により教室で学んだことを現場で確かめ、現場での経験と課題を大学で研究する。その繰り返しにより、高度な専門性と教員としての実践的指導力を養う。
国際文化コミュニケーション学科では、お互いを尊重し、国や価値観の違いを越えて理解し、信頼し合える関係性をつくりだすために、相手と自らの文化に対する深い理解と、多言語で文化を受発信できるコミュニケーション能力の獲得を目指す。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男55%・女45%、2部:男55%・女45%
歴史
設置 1950
学科定員
〈1部〉
計616 経済250、国際経済183、総合政策183
〈イブニングコース(2部)〉
経済150
学部内容
ゼミナールを中心に主体的に学び、議論を重ねることで、課題の発見力と解決策の提案力を磨く。
経済学科では、最先端の経済理論と、実社会で起きている経済現象を学びながら、経済政策や関連する制度についての専門知識を身につける。「理論」「実証」「政策」の3つに重点を置いて学びを深める。
国際経済学科では、具体的な事例を通して、欧米やアジアの経済・社会事情、国際金融、貿易、国際開発などについて学びながら、国際的な経済理論を身につける。
総合政策学科では、現代社会が直面する問題と課題について、自ら考え、問題を掘り下げ、それを解決するための政策と企画を描くとともに、行動し、他の人びととともに「よりよい方向」へと社会を導いていく力、社会における問題解決のための、実践的能力を身につける。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男43%・女57%、2部:男80%・女20%
経済学科では、最先端の経済理論と、実社会で起きている経済現象を学びながら、経済政策や関連する制度についての専門知識を身につける。「理論」「実証」「政策」の3つに重点を置いて学びを深める。
国際経済学科では、具体的な事例を通して、欧米やアジアの経済・社会事情、国際金融、貿易、国際開発などについて学びながら、国際的な経済理論を身につける。
総合政策学科では、現代社会が直面する問題と課題について、自ら考え、問題を掘り下げ、それを解決するための政策と企画を描くとともに、行動し、他の人びととともに「よりよい方向」へと社会を導いていく力、社会における問題解決のための、実践的能力を身につける。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男43%・女57%、2部:男80%・女20%
歴史
設置 1966
学科定員
〈1部〉
計682 経営316、マーケティング150、会計ファイナンス216
〈イブニングコース(2部)〉
経営110
学部内容
グローバル化と情報化に伴い多様さ複雑さを増す企業活動の変化に対応する幅広い視野の獲得を目指す。そのため、社会経済や環境問題、世界情勢などのさまざまな分野を学ぶ。
経営学科では、マネジメントのプロフェッショナルとして活躍する人財の育成を目標としている。経営学に関わる幅広い知識と応用力を備え、経営目標を実現するための方策を戦略的、論理的、創造的に考える力を養う。
マーケティング学科では、商品企画・開発、広告宣伝、流通を連携させて「売れる仕組み」をつくる「マーケティング」について、各分野を体系的に学ぶ。
会計ファイナンス学科では、会計とファイナンスをベースに、関連する各領域について専門的に学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男72%・女28%、2部:男68%・女32%
経営学科では、マネジメントのプロフェッショナルとして活躍する人財の育成を目標としている。経営学に関わる幅広い知識と応用力を備え、経営目標を実現するための方策を戦略的、論理的、創造的に考える力を養う。
マーケティング学科では、商品企画・開発、広告宣伝、流通を連携させて「売れる仕組み」をつくる「マーケティング」について、各分野を体系的に学ぶ。
会計ファイナンス学科では、会計とファイナンスをベースに、関連する各領域について専門的に学ぶ。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男72%・女28%、2部:男68%・女32%
歴史
設置 1956
学科定員
〈1部〉
計500 法律250、企業法250
〈イブニングコース(2部)〉
法律120
学部内容
法学の基本をしっかりと学んだ上で、社会で生じる法的問題を解決するために必要な専門知識、法の運用能力を身につけることを目指す。
法律学科では、法治国家で求められる法的知識と、それを現実問題に活用するためのリーガルマインドを習得する。社会で不断に生起する問題について、自らの頭で考え、法に基づいて解決することのできる能力を有する人財の養成を目指す。
企業法学科では、企業人・国際人として不可欠の法的知識とビジネス知識の修得を目指す。これによって国際社会で活躍する企業人として必要な能力とスキルを身につけた人財を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男63%・女37%、2部:男65%・女35%
法律学科では、法治国家で求められる法的知識と、それを現実問題に活用するためのリーガルマインドを習得する。社会で不断に生起する問題について、自らの頭で考え、法に基づいて解決することのできる能力を有する人財の養成を目指す。
企業法学科では、企業人・国際人として不可欠の法的知識とビジネス知識の修得を目指す。これによって国際社会で活躍する企業人として必要な能力とスキルを身につけた人財を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男63%・女37%、2部:男65%・女35%
歴史
設置 1959
学科定員
〈1部〉
計600 社会150、国際社会150、メディアコミュニケーション150、社会心理150
〈イブニングコース(2部)〉
社会130
学部内容
「理論」と「実証」を共通の軸にして、授業で学んだ知識をもとに実社会を調査する「統計分析」や「フィールドワーク」で「実践」に向けて現代社会の問題解決を模索する。
社会学科では、現代社会への理解を深め、そこにある問題を解決するための広い視野を養う。社会学の基礎理論をはじめ、環境、地域、労働、グローバル化、家族、教育、地理などさまざま視点から学びを深める。
国際社会学科では、世界が人びとの多様性を理解し、持続可能な国際社会の創出に貢献する人材を求めていることに対して、現場体験型の学びを通じて、多文化共生を実践的に担うことのできる「地球市民(グローバル・シティズン)」を育てる。
メディアコミュニケーション学科では、現代社会の特性を「メディア」と「情報」を手がかりとして解明し、これからの社会をリードするスペシャリストを養成する。
社会心理学科では、社会の出来事を心理学的視点でとらえる「社会現象の心理学」と、個人や人間関係を対象とする「人間関係の心理学」の両面から、現代社会の問題にアプローチしていく。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男64%・女36%、2部:男57%・女43%
社会学科では、現代社会への理解を深め、そこにある問題を解決するための広い視野を養う。社会学の基礎理論をはじめ、環境、地域、労働、グローバル化、家族、教育、地理などさまざま視点から学びを深める。
国際社会学科では、世界が人びとの多様性を理解し、持続可能な国際社会の創出に貢献する人材を求めていることに対して、現場体験型の学びを通じて、多文化共生を実践的に担うことのできる「地球市民(グローバル・シティズン)」を育てる。
メディアコミュニケーション学科では、現代社会の特性を「メディア」と「情報」を手がかりとして解明し、これからの社会をリードするスペシャリストを養成する。
社会心理学科では、社会の出来事を心理学的視点でとらえる「社会現象の心理学」と、個人や人間関係を対象とする「人間関係の心理学」の両面から、現代社会の問題にアプローチしていく。
△新入生の男女比率(2024年) 1部:男64%・女36%、2部:男57%・女43%
歴史
設置 2017
学科定員
計390 グローバル・イノベーション100、国際地域290<国際地域210、地域総合*80>
*地域総合専攻はイブニングコース
学部内容
経済、貧困、資源、環境、紛争など、世界のさまざまな問題を解決するため、グローバルな視野と諸問題に関する知識を身につけ、実践的な能力を獲得する。
グローバル・イノベーション学科では、グローバル社会のさまざまな領域のイノベーターとして活動するための知識と哲学、対話・行動力を身につける。具体的には、グローバル企業での国際ビジネスの現場、国家間の交渉や国際機関での活動などにおいて、経済と社会のバランスの取れたイノベーション実現のための知識、さらに日本の経済・社会・文化の深い理解に基づいた国際的な視野の獲得を目指す。
国際地域学科は以下の2専攻制。
◆国際地域専攻では、世界の国々や地域、そしてコミュニティにおけるさまざまな課題・問題を、世界的・地球的(グローバル)な視点と思考から捉える力を身につける。
◆地域総合専攻はイブニングコース(2部)。たとえば、日中の業務などを通して発見した社会の課題を素材として、夕方からの講義で知識を深め、思考し、解決策を探る。時間と自らの経験を有効に活用しながら学ぶことができる。
△新入生の男女比率(2024年) 男43%・女57%
グローバル・イノベーション学科では、グローバル社会のさまざまな領域のイノベーターとして活動するための知識と哲学、対話・行動力を身につける。具体的には、グローバル企業での国際ビジネスの現場、国家間の交渉や国際機関での活動などにおいて、経済と社会のバランスの取れたイノベーション実現のための知識、さらに日本の経済・社会・文化の深い理解に基づいた国際的な視野の獲得を目指す。
国際地域学科は以下の2専攻制。
◆国際地域専攻では、世界の国々や地域、そしてコミュニティにおけるさまざまな課題・問題を、世界的・地球的(グローバル)な視点と思考から捉える力を身につける。
◆地域総合専攻はイブニングコース(2部)。たとえば、日中の業務などを通して発見した社会の課題を素材として、夕方からの講義で知識を深め、思考し、解決策を探る。時間と自らの経験を有効に活用しながら学ぶことができる。
△新入生の男女比率(2024年) 男43%・女57%
歴史
設置 2017
学科定員
国際観光366
学部内容
グローバル市場化した観光産業・政策のエキスパートとして活躍できる人財を目指す。「観光政策・ツーリズム系領域」「ホスピタリティ系領域」の2つを柱に、一人ひとりの希望進路に応じたコース設定により、夢の実現を強力にバックアップしていく。実際の観光業界に則した知識と実践能力を身につけるとともに、「観光とは何か」「観光産業はどうあるべきか」「観光政策の課題解決に向けた取組とは」などを探り、これからの「観光」をつくる力を習得する。
△新入生の男女比率(2024年) 男33%・女67%
△新入生の男女比率(2024年) 男33%・女67%
歴史
設置 2017
学科定員
情報連携300
学部内容
デジタル技術による変革、DXの実現が社会のキーワードになる今、新しいデジタル時代に向けて、コンピュータ・サイエンスを基盤に7つの科目群を設置している。それぞれの専門分野の連携と融合により、イノベーションを起こさせる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男83%・女17%
△新入生の男女比率(2024年) 男83%・女17%
歴史
設置 2023
学科定員
計476 社会福祉216、子ども支援100、人間環境デザイン160
学部内容
誰もが尊重され、すこやかに生きられる社会の実現と発展に貢献する人財を目指す。
社会福祉学科では、誰もがその人らしくありながら、ともに暮らす「共生社会」の実現に向け、社会福祉の学びに基づき、支援の現場で求められる知識と実践的技能を身につける。
また、社会・経済の変化に対応する政策や制度、福祉ビジネスなどについても学びを深め、創造力とリーダーシップを持って国内外の幅広い分野に貢献できる人財を目指す。
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の国家試験受験資格が取得可能。
子ども支援学科では、保育学・幼児教育学・子ども家庭福祉学を基礎とした学びによって、子どもと保護者、家庭、地域社会に関わるさまざまな問題への理解を深める。また、「子どものウェル・ビーイング」を支え、よりよい地域社会づくりに貢献し、協働する専門職としての知識と技能を身につける。さらに、国内外において多文化共生社会の実現に貢献する、子ども支援のプロフェッショナルを目指す。
保育士、幼稚園教諭一種、社会福祉士(国家試験受験資格)などの資格が取得できる。
人間環境デザイン学科では、多様な人びとが暮らす社会、まち、住まい、そして生活の場における「ユニバーサルデザイン」について、ものづくりを通して学修する。
イメージを具体化するデザインの知識や技術を身につけるとともに、社会・経済的な課題についても理解を深めることで、実社会におけるデザインの役割と可能性にも視野を広げ、人の営みを総合的に考える視点を養う。
一級建築士、二級建築士、木造建築士などの資格が取得できる。
△新入生の男女比率(2024年) 男26%・女74%
社会福祉学科では、誰もがその人らしくありながら、ともに暮らす「共生社会」の実現に向け、社会福祉の学びに基づき、支援の現場で求められる知識と実践的技能を身につける。
また、社会・経済の変化に対応する政策や制度、福祉ビジネスなどについても学びを深め、創造力とリーダーシップを持って国内外の幅広い分野に貢献できる人財を目指す。
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の国家試験受験資格が取得可能。
子ども支援学科では、保育学・幼児教育学・子ども家庭福祉学を基礎とした学びによって、子どもと保護者、家庭、地域社会に関わるさまざまな問題への理解を深める。また、「子どものウェル・ビーイング」を支え、よりよい地域社会づくりに貢献し、協働する専門職としての知識と技能を身につける。さらに、国内外において多文化共生社会の実現に貢献する、子ども支援のプロフェッショナルを目指す。
保育士、幼稚園教諭一種、社会福祉士(国家試験受験資格)などの資格が取得できる。
人間環境デザイン学科では、多様な人びとが暮らす社会、まち、住まい、そして生活の場における「ユニバーサルデザイン」について、ものづくりを通して学修する。
イメージを具体化するデザインの知識や技術を身につけるとともに、社会・経済的な課題についても理解を深めることで、実社会におけるデザインの役割と可能性にも視野を広げ、人の営みを総合的に考える視点を養う。
一級建築士、二級建築士、木造建築士などの資格が取得できる。
△新入生の男女比率(2024年) 男26%・女74%
歴史
設置 2023
学科定員
計330 健康スポーツ科学230、栄養科学100
学部内容
スポーツを通じた人びとのQOL(Quality of Life=生活の質)向上への貢献、少子高齢化やグローバル化によってもたらされた社会課題の解決を目指す。健康やスポーツ、食や栄養に関する先端的かつ専門的な知識と技術を学び、その新たな可能性を創造する。
健康スポーツ科学科では、健康問題をはじめとした、少子高齢化・人口減少社会におけるさまざまな課題について、スポーツを通じた解決策を探る。機能的、社会・文化的な側面から健康スポーツ科学を学び、科学的思考を伴った専門的知識と技術を修得する。健康づくり、アスリートのパフォーマンス向上、そしてQOL向上に貢献できる人財を目指す。
栄養科学科では、栄養学を基盤として、栄養科学とスポーツ科学の両面を探求することにより、食・栄養の観点からスポーツパフォーマンス向上や健康づくり、QOL向上に貢献する人材を目指す。学際的な専門知識や技術を生かし、スポーツ栄養科学領域における新たな価値創造を図る。
△新入生の男女比率(2024年) 男53%・女47%
健康スポーツ科学科では、健康問題をはじめとした、少子高齢化・人口減少社会におけるさまざまな課題について、スポーツを通じた解決策を探る。機能的、社会・文化的な側面から健康スポーツ科学を学び、科学的思考を伴った専門的知識と技術を修得する。健康づくり、アスリートのパフォーマンス向上、そしてQOL向上に貢献できる人財を目指す。
栄養科学科では、栄養学を基盤として、栄養科学とスポーツ科学の両面を探求することにより、食・栄養の観点からスポーツパフォーマンス向上や健康づくり、QOL向上に貢献する人材を目指す。学際的な専門知識や技術を生かし、スポーツ栄養科学領域における新たな価値創造を図る。
△新入生の男女比率(2024年) 男53%・女47%
歴史
設置 1961、改組 2009
学科定員
計698 機械工180、電気電子情報工113、応用化学146、都市環境デザイン113、建築146
学部内容
機械工学科では、「機械の設計・製作と利用」の基礎となる知識と専門的な知識を関連づけながら学び、幅広い分野に応用できる基礎力を確実に身につけていく。その上で、産業基盤を担う技術者・研究者となるため、多角的な視点を培い、世の中の変化に対応できる柔軟さを身につける。
電気電子情報工学科では、エネルギー・制御分野、エレクトロニクス分野、情報通信分野について、系統立てて学ぶ。「電気工学」「電子工学」「情報通信工学」をベースに現代社会を支える技術について理解し、広い視野と倫理観を持って新しい技術を創造する技術者の育成を目指す。
応用化学科では、化学の力で社会貢献できる、実践的な研究者・技術者・教育者を目指す。実験と講義で確かな基礎力と柔軟な応用力を身につける。
都市環境デザイン学科では、建設技術についての理解を基礎として、人びとが安全で快適に暮らせる空間づくりを学ぶ。実験や演習を通して、都市環境を構築するデザイン力と、都市づくりに生かされる創造力や経営力を身につける。
建築学科では、建築の工学的側面のみならず、地域に残るストックや歴史といった文化的側面も考えながら、建築と「まち」をトータルデザインできる人材を養成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男82%・女18%
電気電子情報工学科では、エネルギー・制御分野、エレクトロニクス分野、情報通信分野について、系統立てて学ぶ。「電気工学」「電子工学」「情報通信工学」をベースに現代社会を支える技術について理解し、広い視野と倫理観を持って新しい技術を創造する技術者の育成を目指す。
応用化学科では、化学の力で社会貢献できる、実践的な研究者・技術者・教育者を目指す。実験と講義で確かな基礎力と柔軟な応用力を身につける。
都市環境デザイン学科では、建設技術についての理解を基礎として、人びとが安全で快適に暮らせる空間づくりを学ぶ。実験や演習を通して、都市環境を構築するデザイン力と、都市づくりに生かされる創造力や経営力を身につける。
建築学科では、建築の工学的側面のみならず、地域に残るストックや歴史といった文化的側面も考えながら、建築と「まち」をトータルデザインできる人材を養成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男82%・女18%
歴史
設置 2009
学科定員
総合情報260<メディア情報100、心理・スポーツ情報80、システム情報80>
*定員は2025年予定
学部内容
目の行き届いた親身でわかりやすい授業を一人ひとりに行う。各分野での実績と経験を持つ教員が授業の内外で、一人ひとりに的確で丁寧な支援を行い、オール総合情報体制でサポートする。もっとも教育に人と時間をかける学部の一つであること、そして社会で役立つ多様で豊富な資格取得が可能であることが特長。
△新入生の男女比率(2024年) 男77%・女23%
△新入生の男女比率(2024年) 男77%・女23%
歴史
設置 1997
学科定員
計339 生命科学113、生体医工113、生物資源113
学部内容
生命科学科では、さまざまな生物が見せる生命現象について理解を深め、その原理としくみの解明に挑む。人びとの健康と医療、自然環境や生物多様性などに関するグローバルな課題に取り組み、社会と地球環境の持続的な発展に貢献できる人財を育成する。
2024年新設の生体医工学科では、生命科学を応用する学びによって生体と関連技術への理解を「ものづくり」につなげ、社会を支える人財を育成する。医療・福祉・生活の質の向上、持続可能な社会と環境の実現に貢献する。
2024年新設の生物資源学科では、「生物資源」である植物と微生物について深く学び、それらの活用について先端研究を行う。植物や微生物の生命現象を理解し活用することで、健康医療問題や地球規模の諸問題の解決に貢献する人財を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男60%・女40%
2024年新設の生体医工学科では、生命科学を応用する学びによって生体と関連技術への理解を「ものづくり」につなげ、社会を支える人財を育成する。医療・福祉・生活の質の向上、持続可能な社会と環境の実現に貢献する。
2024年新設の生物資源学科では、「生物資源」である植物と微生物について深く学び、それらの活用について先端研究を行う。植物や微生物の生命現象を理解し活用することで、健康医療問題や地球規模の諸問題の解決に貢献する人財を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男60%・女40%
歴史
設置 2013
学科定員
計339 食環境科学126、フードデータサイエンス113、健康栄養100
学部内容
食環境科学科では、食を取り巻く多様な分野でリーダーシップを発揮し、食環境科学に関する専門知識を持って、次世代の食を創造する人財を目指す。段階的に専門性を高める学びによって、持続可能な社会、食関連産業を実現するための能力を培う。
2024年新設のフードデータサイエンス学科では、「フードシステム学」と「データサイエンス」との文理融合の学びにより、食を取り巻く問題の解決に挑む。社会で実践的にデータサイエンスを使って活躍し、食の未来を創造する「フードデータサイエンティスト」を育成する。
健康栄養学科では、管理栄養士としての能力を育むとともに、社会における実践力、自然科学と人文科学分野の基礎的知識を養う。多角的な視点から食と健康への理解を深め、さまざまな分野で健康栄養科学の側面からリーダーシップを発揮できる人財を目指す。
△新入生の男女比率(2024年) 男39%・女61%
2024年新設のフードデータサイエンス学科では、「フードシステム学」と「データサイエンス」との文理融合の学びにより、食を取り巻く問題の解決に挑む。社会で実践的にデータサイエンスを使って活躍し、食の未来を創造する「フードデータサイエンティスト」を育成する。
健康栄養学科では、管理栄養士としての能力を育むとともに、社会における実践力、自然科学と人文科学分野の基礎的知識を養う。多角的な視点から食と健康への理解を深め、さまざまな分野で健康栄養科学の側面からリーダーシップを発揮できる人財を目指す。
△新入生の男女比率(2024年) 男39%・女61%
東洋大学の学びをWebで体験
東洋大学で実際にどういう授業をしているか、下の分野の中から興味ある学びを選んで体験授業を見てみよう!
- 人の行動や考え方や文化、社会のあり方を学びたい 文化・ことば・哲学・心理
- 教育やスポーツ、福祉を学び、社会に貢献していきたい 教育・福祉・スポーツ
- 時代の先端を見つめ、社会にあるさまざまな問題を解決したい 政治経済・ビジネス・法律
- 国際的な視野で、文化・地域・社会を学びその魅力を伝えていきたい 国際交流・観光
- 進化するメディアや技術によって、未来の可能性を広げていきたい メディア・情報・テクノロジー
- ものづくりやデザインを通して豊かな社会を創造したい ものづくり・デザイン
- 健康や食・医療を通じて人々の支えになりたい 健康・食・医療
- 人々の暮らし、都市計画、自然との共存などよい暮らしを創りたい まちづくり・環境・暮らし
他の大学の情報も確認しよう
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。