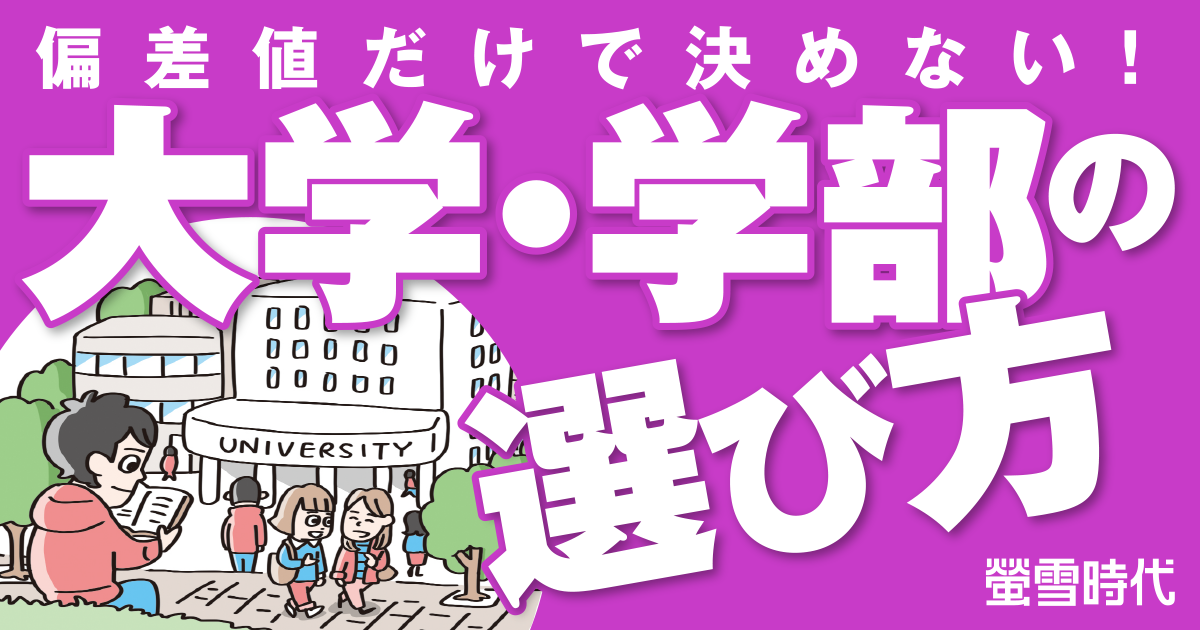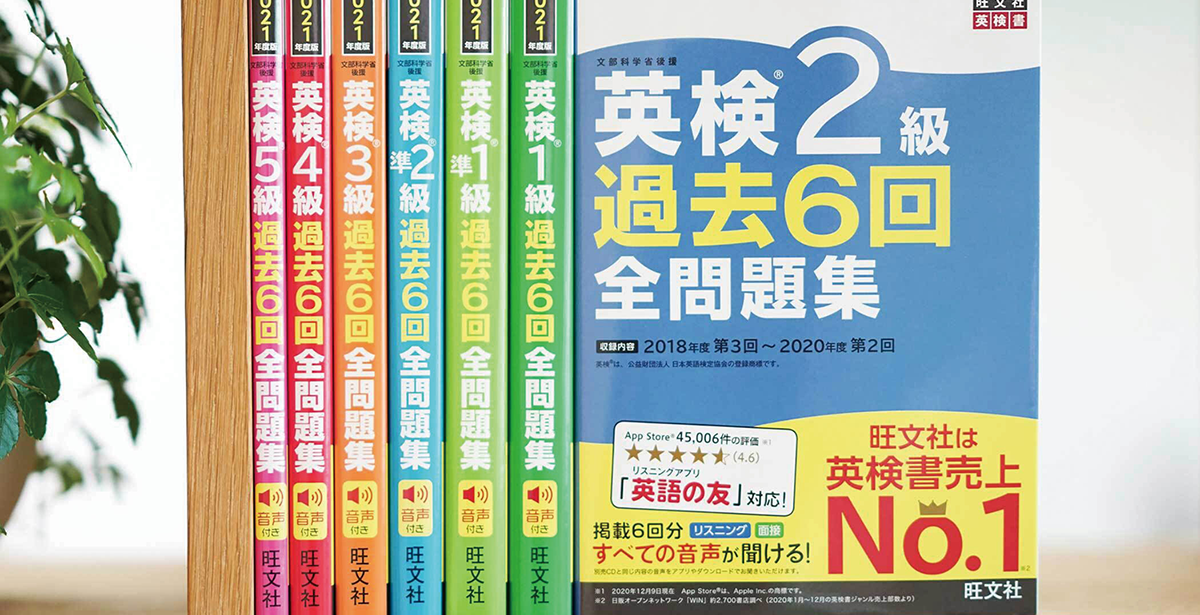学部で絞り込む
歴史
設置 1949、改組 1965
学科定員
計600 法律400、自治行政200
学部内容
法律学科では、「法律職」「ビジネス法」「現代社会」の3コースから柔軟な思考力とリーガルマインドを修得。4年間を通じてゼミナール形式での体験型授業で「生きた法律」を身につける。
自治行政学科では、地方分権が推進され、地域のニーズに応じた特色ある行政や効率的な行政運営が求められるなか、地域の視点から環境、防災、福祉をはじめとするテーマに取り組み、新時代の地方自治を開拓する人材の育成を目的とする。
△新入生の男女比率(2024年) 男64%・女36%
自治行政学科では、地方分権が推進され、地域のニーズに応じた特色ある行政や効率的な行政運営が求められるなか、地域の視点から環境、防災、福祉をはじめとするテーマに取り組み、新時代の地方自治を開拓する人材の育成を目的とする。
△新入生の男女比率(2024年) 男64%・女36%
歴史
設置 1949、改組 1965
学科定員
計950 経済650<現代経済580、経済データ分析70>、現代ビジネス300
学部内容
経済学科は、2つの専攻と5つのコースがある。
経済学を幅広く学ぶ「現代経済専攻」は、「福祉・環境・公共政策」「市場・企業・産業」「国際経済・社会」の3コース制。政策やデータ処理を学ぶ「経済データ分析専攻」(2025年経済分析専攻から名称変更予定)には、「政策分析コース」と「市場分析コース」(2025年データ分析コースから名称変更予定)がある。
現代ビジネス学科では、グローバルな視点からビジネスの理論と実践力を身につけ、ビジネスを成功へと導くスキルを育成する。「貿易・国際ビジネス」「経営・マーケティング」「企業・会計」の3コースからなる。
△新入生の男女比率(2024年) 男75%・女25%
経済学を幅広く学ぶ「現代経済専攻」は、「福祉・環境・公共政策」「市場・企業・産業」「国際経済・社会」の3コース制。政策やデータ処理を学ぶ「経済データ分析専攻」(2025年経済分析専攻から名称変更予定)には、「政策分析コース」と「市場分析コース」(2025年データ分析コースから名称変更予定)がある。
現代ビジネス学科では、グローバルな視点からビジネスの理論と実践力を身につけ、ビジネスを成功へと導くスキルを育成する。「貿易・国際ビジネス」「経営・マーケティング」「企業・会計」の3コースからなる。
△新入生の男女比率(2024年) 男75%・女25%
歴史
設置 1989
学科定員
国際経営530
学部内容
国際経営学科では、グローバル時代を生き抜くための経営理論と実践的なスキルを身につけるため、“自らの頭で考え、解決する力”を独自のカリキュラム体系の中で養う。
希望の進路に必要な専門科目を選べる独自のキャリア・ショップシステムを採用。「マネジメント」「会計」「マーケティング・デザイン経営」「国際理解」の4つの専門科目群を組み合わせた学びが可能。また、学科独自プログラムの留学制度や、学内外コンテストなどで学びと実社会をつなぎ、国際化時代に活躍できる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男58%・女42%
希望の進路に必要な専門科目を選べる独自のキャリア・ショップシステムを採用。「マネジメント」「会計」「マーケティング・デザイン経営」「国際理解」の4つの専門科目群を組み合わせた学びが可能。また、学科独自プログラムの留学制度や、学内外コンテストなどで学びと実社会をつなぎ、国際化時代に活躍できる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男58%・女42%
歴史
設置 1965
学科定員
計350 英語英文200
学部内容
英語英文学科では、2年次の留学が必修の「GEC」プログラムと、従来のカリキュラムを再編した「IES」プログラムを設定。世界の多様な文化と価値観が学べる。ネイティブ教員による授業や「言語・文化・文学・英語教育」の専門科目が充実している。
スペイン語学科では、スペイン語修得とともに、ラテンアメリカを含むスペイン語圏の文化・歴史・文学・社会・政治・経済などについて幅広く学修。少人数でスペイン語のレッスンを受けられる「Spanish Express」を開講している。
中国語学科では、少人数制のきめ細かな指導で中国語運用能力を高め、日中のみならずアジアを舞台に活躍できる人材を育成する。学科独自の留学制度も充実し、2年次からは「言語コース」「社会文化コース」に分かれる。
△新入生の男女比率(2024年) 男45%・女55%
スペイン語学科では、スペイン語修得とともに、ラテンアメリカを含むスペイン語圏の文化・歴史・文学・社会・政治・経済などについて幅広く学修。少人数でスペイン語のレッスンを受けられる「Spanish Express」を開講している。
中国語学科では、少人数制のきめ細かな指導で中国語運用能力を高め、日中のみならずアジアを舞台に活躍できる人材を育成する。学科独自の留学制度も充実し、2年次からは「言語コース」「社会文化コース」に分かれる。
△新入生の男女比率(2024年) 男45%・女55%
歴史
設置 2020
学科定員
計300 国際文化交流170、日本文化60、歴史民俗70
学部内容
国際文化交流学科では、確かな外国語運用能力を磨き、日本文化発信と異文化交流に貢献する人材を育成する。
◆文化交流コースでは、世界のさまざまな文化を的確に理解し、国際的な文化交流ができる人材を育成する。
◆観光文化コースでは、観光が生み出す文化とそれに関わる人びととの関係を理解し、その知識を観光関連産業や国際的な相互理解の場で活用できる人材を育成する。
◆言語・メディアコースでは、言葉とコミュニケーションに関する知識と洞察力、メディアに関する実践的な知識と分析力により、新時代を切り開く人材を育成する。
◆国際日本学コースでは、国内外の専門家とともに、「日本」を見つめ直し、日本文化を複眼的に理解する。
日本文化学科では、博物館、美術館や劇場などを実際に訪れ、さまざまなアート体験を積むフィールドワークも実施。日本語学、日本文学、文化・表象の3分野の学びから、日本文化の本質を探究する。
歴史民俗学科では、アジア・日本の歴史や文化、身近な民衆の暮らしを学ぶ民俗学を通して、グローバルな視点から考察する。
△新入生の男女比率(2024年) 男34%・女66%
◆文化交流コースでは、世界のさまざまな文化を的確に理解し、国際的な文化交流ができる人材を育成する。
◆観光文化コースでは、観光が生み出す文化とそれに関わる人びととの関係を理解し、その知識を観光関連産業や国際的な相互理解の場で活用できる人材を育成する。
◆言語・メディアコースでは、言葉とコミュニケーションに関する知識と洞察力、メディアに関する実践的な知識と分析力により、新時代を切り開く人材を育成する。
◆国際日本学コースでは、国内外の専門家とともに、「日本」を見つめ直し、日本文化を複眼的に理解する。
日本文化学科では、博物館、美術館や劇場などを実際に訪れ、さまざまなアート体験を積むフィールドワークも実施。日本語学、日本文学、文化・表象の3分野の学びから、日本文化の本質を探究する。
歴史民俗学科では、アジア・日本の歴史や文化、身近な民衆の暮らしを学ぶ民俗学を通して、グローバルな視点から考察する。
△新入生の男女比率(2024年) 男34%・女66%
歴史
設置 2006
学科定員
人間科学300
学部内容
人間科学科では、人間を「こころ・からだ・社会」の側面から多角的・総合的にとらえ、現代社会のさまざまな問題を解決する力を養う。心理・教育・福祉の視点から人間のこころの発達や特性を学ぶ「心理発達」、スポーツ科学と健康科学の視点からからだの発達や健康を学ぶ「スポーツ健康」、社会的存在としての人間を学ぶ「人間社会」の3コース制。横断的な学びで、専門知識と複眼的な思考、実践力を磨く。
△新入生の男女比率(2024年) 男46%・女54%
△新入生の男女比率(2024年) 男46%・女54%
歴史
設置 1989
学科定員
理学275<数学40、物理40、化学70、生物70、地球環境科学30、総合理学25>
学部内容
1学科6コース制により、数学から地学まで幅広く理学全域の学びを網羅する。
入試時に6コースから興味関心のあるコースを1つ選び、学びを深める。
在学中には興味関心に応じ、コースの領域を超えて自由に学ぶことができる。基礎から応用の学び、実験・実習などを通し、社会で役立つ科学的なものの見方を身につけ、論理的思考力を養う。
◆数学コースでは、解析、代数、幾何、確率・統計の各分野を基礎から応用まで、講義と演習を通して広く深く学ぶ。
◆物理コースでは、演習を交え、力学、電磁気学、量子力学、熱・統計力学といった基軸となる4科目を学修する。
◆化学コースでは、物理化学、有機化学、無機・分析化学の3分野をバランスよく学んでいく。
◆生物コースでは、マクロな形態・生態から、発生・生理、さらにはミクロな細胞・分子の世界まで、生物学のほぼ全ての分野について学ぶ。
◆地球環境科学コースの学びは、地球を知ることからスタートする。宇宙の中の地球、地球の構成、そして化石から地球上での生物の進化について学ぶ。
◆総合理学コースでは、従来の数学、物理学、化学、生物学に加えて、地球環境科学を含めたより広い視点で分野横断的に科学を理解していく。
△新入生の男女比率(2024年) 男79%・女21%
入試時に6コースから興味関心のあるコースを1つ選び、学びを深める。
在学中には興味関心に応じ、コースの領域を超えて自由に学ぶことができる。基礎から応用の学び、実験・実習などを通し、社会で役立つ科学的なものの見方を身につけ、論理的思考力を養う。
◆数学コースでは、解析、代数、幾何、確率・統計の各分野を基礎から応用まで、講義と演習を通して広く深く学ぶ。
◆物理コースでは、演習を交え、力学、電磁気学、量子力学、熱・統計力学といった基軸となる4科目を学修する。
◆化学コースでは、物理化学、有機化学、無機・分析化学の3分野をバランスよく学んでいく。
◆生物コースでは、マクロな形態・生態から、発生・生理、さらにはミクロな細胞・分子の世界まで、生物学のほぼ全ての分野について学ぶ。
◆地球環境科学コースの学びは、地球を知ることからスタートする。宇宙の中の地球、地球の構成、そして化石から地球上での生物の進化について学ぶ。
◆総合理学コースでは、従来の数学、物理学、化学、生物学に加えて、地球環境科学を含めたより広い視点で分野横断的に科学を理解していく。
△新入生の男女比率(2024年) 男79%・女21%
歴史
設置 1949
学科定員
計440 機械工145、電気電子情報工145、経営工90、応用物理60
学部内容
機械工学科では、伝統的な科目と同時に機械解剖、メカトロデザインなど、機械に触れる科目を学んだ上でロボット・AI、宇宙エレベーター、ビークル、ロケット、複合材料、精密加工・工作機械、金属材料、燃焼、熱・流体機械などの研究に取り組む。
電気電子情報工学科では、発展拡大を続ける先端的領域を学ぶ。電子技術と情報技術を修得。電気(エネルギー問題)、電子(半導体)、情報(人工知能、データ処理)、通信(高速データ通信)を含む幅広い分野を横断的に学ぶ。
経営工学科では、モノづくりの現場をマネジメントする力を養う。経営管理系、生産システム工学系、人間・環境系、知識ものづくり技術系の4科目群を設定している。世界を舞台に活躍するグローバル人材の育成を目指し、「国際コミュニケーション」「英語ディスカッション」「工業中国語」などの科目を設置している。
応用物理学科では、「宇宙」のなぞから「ナノ」の新技術まで、物理学の幅広い応用領域を扱う。宇宙観測、ナノサイエンス、データサイエンスなどの教育プログラムと先端研究を通じて、実験・観測装置の開発、データ解析やシミュレーションなど、ハードからソフトまで幅広く扱える技術者を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男92%・女8%
電気電子情報工学科では、発展拡大を続ける先端的領域を学ぶ。電子技術と情報技術を修得。電気(エネルギー問題)、電子(半導体)、情報(人工知能、データ処理)、通信(高速データ通信)を含む幅広い分野を横断的に学ぶ。
経営工学科では、モノづくりの現場をマネジメントする力を養う。経営管理系、生産システム工学系、人間・環境系、知識ものづくり技術系の4科目群を設定している。世界を舞台に活躍するグローバル人材の育成を目指し、「国際コミュニケーション」「英語ディスカッション」「工業中国語」などの科目を設置している。
応用物理学科では、「宇宙」のなぞから「ナノ」の新技術まで、物理学の幅広い応用領域を扱う。宇宙観測、ナノサイエンス、データサイエンスなどの教育プログラムと先端研究を通じて、実験・観測装置の開発、データ解析やシミュレーションなど、ハードからソフトまで幅広く扱える技術者を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男92%・女8%
歴史
設置 2022
学科定員
建築200<建築120、都市生活80>
学部内容
建築学系と都市生活学系の2つの学系、構造、環境、デザイン、住生活創造、まち再生の5つのコースを設置。
従来の建築学だけでなく、あらゆる視点から幅広い学問分野の知識を取り込み、より包括的な意味での「建築学」を理解し、課題解決能力を修得した専門性と技術を持つ人材を育てる。
全コースで建築士国家試験の受験資格の取得が可能な科目群が配置され、受験に必要な数学や物理学関連の学修サポートが用意されている。
△新入生の男女比率(2024年) 男68%・女32%
従来の建築学だけでなく、あらゆる視点から幅広い学問分野の知識を取り込み、より包括的な意味での「建築学」を理解し、課題解決能力を修得した専門性と技術を持つ人材を育てる。
全コースで建築士国家試験の受験資格の取得が可能な科目群が配置され、受験に必要な数学や物理学関連の学修サポートが用意されている。
△新入生の男女比率(2024年) 男68%・女32%
歴史
設置 2023
学科定員
計190 応用化学110、生命機能80
学部内容
化学・生物学の分野を融合的に学び、化学現象や生命現象の仕組みを知るだけではなく、それを「どのように社会に役立てていくか」という視点を持って、技術開発やモノづくりにつなげていく。
応用化学科では、現代社会に役立つ化学技術を身につけることを目標とし、電池や燃料電池などのエネルギー化学、触媒化学、固体化学、セラミックス・高分子といった材料化学などを扱う応用化学を中心に学ぶ。
生命機能学科では、生化学、分子生物学、細胞生物学、遺伝学、タンパク質工学などを扱う生命機能学を中心に学ぶ。生命現象や生体機能について生命科学の視点から学ぶことで、問題を発見し、解決する生命科学の技術を身につけることを目標とし、人々の幸せに貢献できる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男48%・女52%
応用化学科では、現代社会に役立つ化学技術を身につけることを目標とし、電池や燃料電池などのエネルギー化学、触媒化学、固体化学、セラミックス・高分子といった材料化学などを扱う応用化学を中心に学ぶ。
生命機能学科では、生化学、分子生物学、細胞生物学、遺伝学、タンパク質工学などを扱う生命機能学を中心に学ぶ。生命現象や生体機能について生命科学の視点から学ぶことで、問題を発見し、解決する生命科学の技術を身につけることを目標とし、人々の幸せに貢献できる人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男48%・女52%
歴史
設置 2023
学科定員
計200 計算機科学80、システム数理80、先端情報領域プログラム40
学部内容
計算機科学科では、情報と計算の基礎を修得し情報処理を科学的に理解する。国のコンピュータ関連学会ACMとIEEEによる世界標準の情報教育カリキュラムを組む。情報学の基礎となる計算機科学をしっかり身につける。
システム数理学科では、社会のあらゆるシステムを対象として、システムのあり方や作り方、そのための根幹となるモデリングを情報学と数学に基づいた数理的観点から考え、問題解決に取り組む。
先端情報領域プログラムでは、計算機・システム動作、ソフトウェアの振る舞い、セキュリティログ、フェイク音声・画像、創作物(文学、音楽、絵画)、行動ログ、社会現象(自然災害、流行、疾病ほか)などの幅広いデータを対象に、データの倫理的側面も理解した上で、データを扱える人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男89%・女11%
システム数理学科では、社会のあらゆるシステムを対象として、システムのあり方や作り方、そのための根幹となるモデリングを情報学と数学に基づいた数理的観点から考え、問題解決に取り組む。
先端情報領域プログラムでは、計算機・システム動作、ソフトウェアの振る舞い、セキュリティログ、フェイク音声・画像、創作物(文学、音楽、絵画)、行動ログ、社会現象(自然災害、流行、疾病ほか)などの幅広いデータを対象に、データの倫理的側面も理解した上で、データを扱える人材を育成する。
△新入生の男女比率(2024年) 男89%・女11%
他の大学の情報も確認しよう
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。